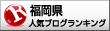山口県下関市の山間の静かな場所に、明治維新の発火点となった長州藩の高杉晋作が
眠る東行庵(とうぎょうあん)があります。
梅雨入り前後のこの時期に、様々な花菖蒲が東行池を彩ります。
高杉晋作は、江戸時代から明治に変わる際に武士ではなく農民などから創設した奇兵隊によって
長州藩を佐幕から倒幕に変え、島津藩とともに明治維新への橋掛かりを作った人です。
これほどのことをわずか29歳でこの世を去るまでになし得た長州の星です。
晋作は、死後奇兵隊のそばで眠るという遺言によります。
下関で晋作を世話をした「おうの(梅処)」は晋作が眠るこの地で晋作が生前「おうの」に伝えていた号の東行の名を取り
東行庵とし終生を弔ったそうです。
東行庵入り口
静かな雰囲気が醸し出されていました。
東行池の中心にある朱橋
朱色の橋の左の池には花菖蒲、右の池には蓮が咲いています。
朱橋の左手の池
緑に覆われた中の花菖蒲
朱橋の右手の睡蓮と錦鯉
左側の池を散策
左の池は一周散策できます。
朱橋の対岸から見たもので、数人の観光者がいました。
朱橋と大きな石塔のコラbが素敵でした。
同上のクローズアップ
散策路
快い木陰の中を散歩できました。
池を一周して花菖蒲と朱橋のコラボ
朱橋の右側の池
白い花菖蒲が水面に映えていました。
東行庵
この家で「おうの」は終生を捧げて晋作を弔いました。
高杉晋作の銅像
池の入り口にあり、2016年に新たにできたものです。
それまでは東行庵のある清水山(しみずやま)の頂上付近にある銅像だけで
一度行きましたが大変疲れました。
銅像の揮毫は元安倍首相です。
高杉晋作は、小説や映画やTVも気がついたものは目を通し、関係ある史跡にもかなり行きました。
その間に高杉晋作という方のイメージが私の中で、すごい人→なりたい人→とてもなれない人と歳とともに変わりました。
また、東行庵は筆者の生まれ育った場所から比較的近いところでしたが、
30年前には車もなく、今のようにナビもない時代で長く東行庵の場所がわかりませんでした。
現在の科学の進歩に感謝です。。
北九州市戸畑区にある菖蒲池は深い森の奥にある神秘的な美しい花菖蒲が咲いていました。
菖蒲池が展望できる東屋
目的の菖蒲池から見ると高台にあります。
森に囲われてとても気持ち良く寛げます。
中段から見た菖蒲池
東屋を少し抜けるとはっきりと菖蒲池が見渡せるようになりました。
中段の前側で見た菖蒲池
菖蒲池が緑に囲まれ神秘的に見えます、石橋を境に手前と奥側では花菖蒲の配置のデザインが変わります。
石橋と手前の菖蒲池
奥側の菖蒲池
石橋側から見ています。
池に中にできた島毎に品種が分かれていて池の周りを散策しながら
それぞれの花菖蒲の花姿と名前を見ながら楽しみしました。
奥側菖蒲池
反石橋側から見ています。
遠くに高台にある東屋がありそこからここまで降りてきました。
お気に入り花菖蒲2点
背景が水面の状態が個人的に好みです。
愛知の輝
新紫式部
紫式部は、NHKの大河で放映中です、平安時代のことはほとんど知らないので楽しく見ています。
****************************************
戻り道
来た時と違った雰囲気に見えるので楽しみながら戻ります。
手前の菖蒲池と中段
中段までの階段
両サイドはあじさいが楽しめました。
}
下から見た東屋
天気のよいは後光が指すように見える東屋が気に入っています。
夜宮公園の菖蒲池は高台にある東屋側から深緑の森を抜けながら行くととても素敵です。
ところが菖蒲池の傍を通る道路(なんじゃもんじゃ通り)脇から降りて行けるのですが、
全くというほど雰囲気が出ません。
それで、道路から行くと楽で良いのですが、あえて遠い東屋から見に行っています。
火の山の展望台からの眺望と透き通ったような水色の花・ネモフィラが見るために、
山口県下関市にある関門海峡に面した火の山に行きました。
火の山付近詳細
日の山展望台の駐車場から見た眺望
夕日に響灘の海が光っていました。
下関市街と響灘
響灘 六連島
火の山展望台から見た眺望
下関市内が見渡せ、巌流島、海峡ゆめタワーが見えます。
***************************************************************
火の山展望台からの眺望を見たあと、ネモフィラを見たいというので
麓の火の山トルコチューリップ園に寄りました。
火の山トルコチューリップ園 別称『オルハン・スヨルジュ記念園』
公園入口にある像 、愛情と優しさに満ち溢れていました。
この公園は、下関市とイスタンブール市とは「海峡」という地理的類似性があることから
1972年姉妹友好都市となった記念公園です。
5万株のトルコ国花のチューリップがあり、
すべてイスタンブール市から寄贈されたものです。
初めて来園した公園ですが、別称『オルハン・スヨルジュ記念園』に興味を引き調べると
胸を熱くする物語が隠れていました。
このチューリップ園の名称『オルハン・スヨルジュ記念園』とは、1985年3月、イラン・イラク戦争の最中に
テヘランに取り残されていた日本人215名を救出した元トルコ航空機機長オルハン・スヨルジュ氏(1926−2013)を
顕彰するために付けられたものです。
イラン・イラク戦争時、イラク大統領サダム・フセインは「48時間の猶予期間後にイラン上空を飛ぶ機体を
すべて撃墜する」と宣言しました。
当時の日本にはイランへ行き来する航空便がなく、他国の航空会社も自国民の救出に精一杯で
タイムリミットまでに日本へ帰国することは困難でした。
日本人の窮状を知ったトルコ政府は、日本人救出に乗り出しタイムリミット直前に、
200名以上の日本人をイランから脱出させてくれたのです。
***********************************************
当時のトルコ政府が危険を覚悟で救出しようとした背景
起点は、1890年におきた「エルトゥールル号事件」です
1887年、小松宮彰仁親王同妃両殿下が欧州訪問の帰途にオスマン帝国を公式訪問し、
その答礼として、1890年にトルコ側は特使としてオスマン提督を日本に派遣します。
トルコの艦船がオスマン帝国へ帰路の途中に和歌山県串本町沖にて台風と遭遇して、
エルトゥールル号が座礁・沈没してしまいます。
その際、近隣の紀伊大島の住民が救助活動の末に69名を救出しました。
日本人のこのような無償の行動にトルコ国民は感銘を受け、
日本とトルコは歴史的に友好関係が築かれてイランから決死の脱出をさせてくれたのでしょう。
火の山に裾の広がる花々
もう薄暗い時間で残念でした。
明るければ、眼の前を様々な花が美しく艶やかなはずです。
目の間にわずかにネモフィラを見ることができました。
イラン・イラク戦争は入社して間もなく起きて、会社の人も対象だった記憶がありました。
その時は、それが何だったのか深く理解もしなかったことがこういうことだったのかとわかり
感銘しました。
そして、トルコの国、イスタンブールの町がとても好きになりました。
火の山は3度目くらいですが、日も暮れての眺望は初めて見てうっとりとしました。
ただ、撮影場所から関門海峡と関門橋が見えず残念でした。
福岡県芦屋町にある岡湊(おかのみなと)神社は初夏に入ると
ナンジャモンジャの真白き花で雪が積もったようになります。
この神社の歴史はとても古く1800年の時を経て、
神社のある芦屋の町は「日本書紀」「古事記」には「崗之水門(おかのみなと)」として登場しています。
真白き雪のような「なんじゃもんじゃ」は、歴史とともに増えて今日のように神社に真白き雪を積もらせます。
ナンジャモンジャの主木は、親交の証として朝鮮李王家から贈られ、
親木は、現岡湊神社宮司が明治神宮を退職した記念に明治神宮から贈られたものだそうです。
それ以外にも、対馬や岐阜のものや、アメリカ種など、約120本のなんじゃもんじゃがあり、
初夏に神社を真白く変貌させてくれます。
********************************************
第一の鳥居から拝殿まで距離は短く、かつ平坦ですのでとても参内しやすい神社です。
第一の鳥居とナンジャモンジャ

阿形の狛犬
鳥居をくぐると、右手に迎えてくれます。
吽形の狛犬
左手に迎えてくれます。
第2の鳥居
第2鳥居の扁額
扁額の字は北白川内親王の書だそうです。
第2の鳥居をくぐり振り返ると、可愛い園児たちが黄色い声を上げていました。
参道を進むとナンジャモンジャの白い花に包まれた手水舎が
印象的でした。
手水舎から第2の鳥居の方を振り返ると、雪に包まれたみたいに見えました。
更に参道を進み、振り返ると右手に桃の石像を触っている人がいました。
幸桃(さちもも)
御婦人が触っている石像です、触ると厄除けできるようで筆者も触って厄除けをしました。
拝殿
拝殿近くの参道には、ナンジャモンジャの白い花はなくなり眼の前がパッと開けた感じがしました。
拝殿を左手に回り込むと本殿が見えます。
参道周りと打って変わって重厚な静寂な世界でした。
最後に、ナンジャモンジャだけ撮りました。
緑の中で涼しげに咲いていました。
ナンジャモンジャが咲くこの時期に岡湊神社に参拝すると、
別世界に入り込んだ錯覚に陥ります。
参拝を終え帰途に着くときは、清々しい気持ちになりました。
北九州市の吉祥寺は境内に広がる藤棚の花が素敵な寺院です。
藤の花の垂れ下がった下を腰をかがめて通り抜けることがこの時期の大きな楽しみです。
今回は、少し早かったのか垂れ下がり量が少し少なくてあまり腰を曲げずに楽に通り抜けすることができました。
吉祥寺は、1800年前の1217年に創建されました。
160年の歴史を持つ3本の野田藤が、境内の藤棚に広がり薄紫の天空の蓋を作り出しています。
吉祥寺は、北九州市八幡西区吉祥寺町にあり「きっしょうじ」と一般的に呼ばれることが多いのですが、
町の名前を「きちじょうじ」と呼ぶように、正式には寺の名前も「きちじょうじ」と呼ぶそうです。
筆者も「きっしょうじ」と呼んでいましたが、なんともややこしいですね。
******************************************
境内の藤棚
藤棚の藤の花の垂れ下がりはまだ少し早く、筆者の胸くらいですので、少し屈めば楽に通り抜けられます。
最も長く垂れ下がるときは腰辺りまで下がるので通り抜けは体の堪えるようになります。
藤の花
階段下から見上げたときの藤の花
梵鐘と藤
この藤の花は若いのかあまり下に垂れ下がりません。
梵鐘と藤
緑に薄紫色が溶け込んでいます。
下から見上げた藤棚
ツツジと藤の花のコラボが素敵でした。
山門と藤棚
階段の入口の藤棚
藤棚の西側の階段入り口の藤棚も素敵でした。
西側階段の上から見た藤棚
藤棚は、下から見ると薄紫ですが、上から見ると緑の海のようですね。
薄紫の藤棚の垂れ下がりも見事ですが、外側から見ると緑が藤の花を覆っており
落ち着いた雰囲気に浸ることができました。