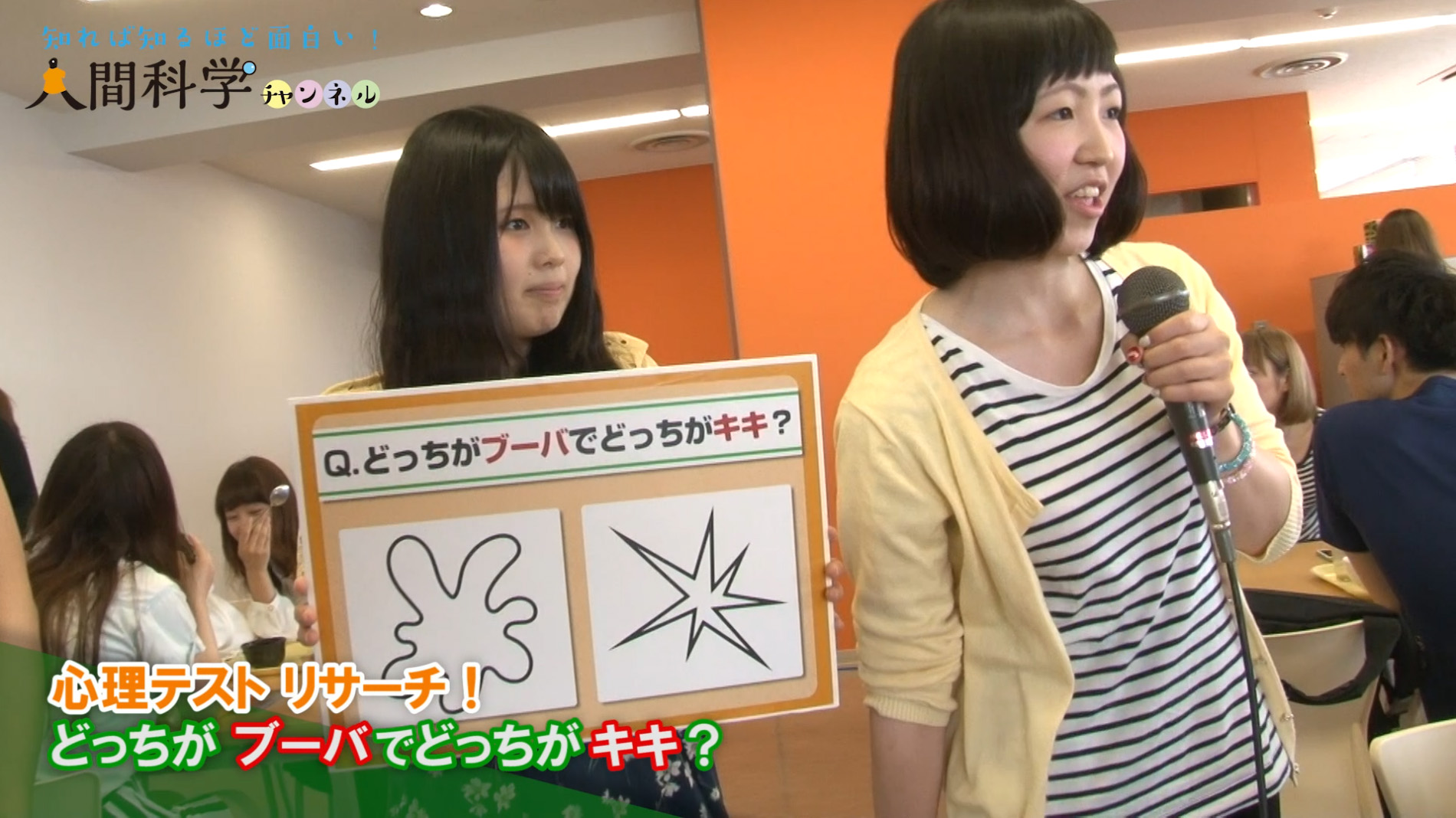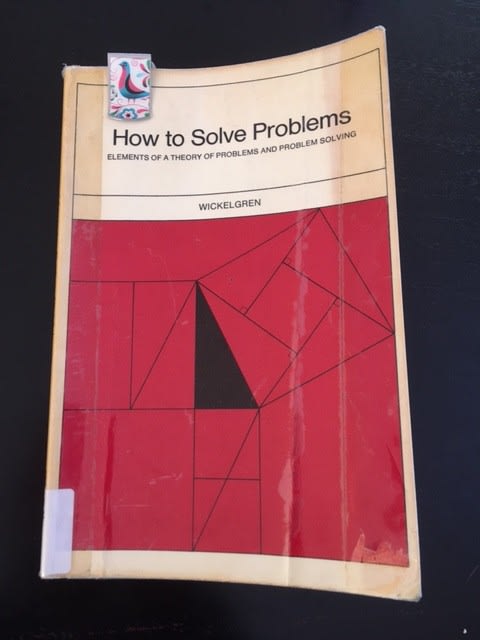“The egg is the world. Whoever wants to be born must first destroy a world.
The bird is flying to God. The name of the God is called Abraxas.”
(Demian: Hermann Hesse)
以前翻訳の勉強をしていたときのこと。
教授は聖書の翻訳の研究で有名なEugene A. Nidaさんの文献をよく活用していました。
聖書では限りなく原文に近い意味を伝える翻訳を目指すのですが
例えば象徴的な意味を含む「子羊」という言葉を
羊がいない国の人たちにどのように表現をしたら
同じように心を動かし共感の念を湧きあがらせることができるだろうか?
などなど、翻訳者の悩みは尽きないわけです。
OriginalTextにぴったりとはまるTarget languageがなかなか見当たらない中、
翻訳者は言葉の意味の枠を伸ばしてみたり縮めてみたり、あの手この手を使って
読み手の頭の中に同等なものをre-createしようとする。
でも失われるものはゼロじゃない・・・。
私は聖書で、「悔い改める(repent)」という言葉が出てくると、
なんだか完全に意味を消化しきれていないようなモヤモヤした気持ちになっていたのですが、
先日読んだ"The common sense of faith" (COLE, ARTHUR BASIL) という本に、
"Repent" means a great change round in the mind.
the word suggests a change of feeling of sentiment and a going forward in the new direction. "
とあって、そーゆーことかぁぁ!
っとモヤモヤが解消されました。
新約聖書の原典はギリシャ語で書かれているそうですが、
"Repent"、と翻訳されているギリシャ語の言葉には上記のような意味が含まれているのだそうです。
解釈の余地がある=翻訳は一通りではない、ということで
この解釈も上書きされる可能性は否めないけれど・・・。


今日はブレイクタイムにDatesをたっぷり入れたココアケーキを作ってみました



超簡単です

3 tbsp Plain flour
3 tbsp icing sugar (今日はCaster sugarを使用)
1/4 tsp baking powder
2 tbsp oil (or butter)
3 tbsp milk
2 tsp cocoa powder
(Option: Dates)
Mugcup cakeのレシピで、
これらをMugに入れてミックスし、電子レンジで3分加熱する、とあるのですが、
私はちょっと薄目の一口サイズにしたかったので、
長方形の耐熱容器に入れて電子レンジで2分強加熱してみました。
Datesたっぷりで美味しかったです。

宜しければポチっとお願い致します

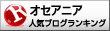 ご訪問ありがとうございます
ご訪問ありがとうございます
 .
.