
前回は自然物ということで
リンゴを描きましたが
レッスン10は人工物です。
カンナやペンチ、おおきな大工道具を
持参された方もいましたが、
私は身近な所で<はさみ>です。
形としては
使えるように見えることが大事!だそうで
支点からの長さや角度をよく観察するように・・という
先生のアドバイスでした。
苦労したのは、古いステンレスの色作りです。
鈍い光と所々錆っぽくてざらついた質感を表現
するのが大変^^
レッスン途中、こんな質問が生徒さんから・・・
「発色がいいというのは、どういうことをいうんですか?」
答える先生・・
「そうですね。。色に存在感がある。。ということでしょうか。。」
うーーん。。よけいにわからん。。ますますわからん。。
先生、続けて・・
「混ぜると濁って発色が悪くなりますが、イコール汚い色
ということではありません」
うーーん。。確かにソレは始めのほうの講義で聞いた気がする。。
隣合う色との兼ね合いで、どんな色でも美しく映えるという話だったような。。
先生、重ねて・・
「あまり頭で考えずドンドン描いていきましょう~絵に正解も間違いも
ないのですから」
と、こんなふうに
いつも煙にまくというか、背中を押してくれる楽しい先生~♪










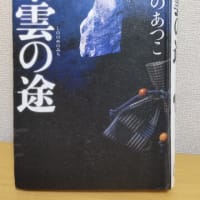


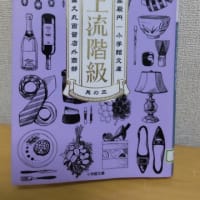

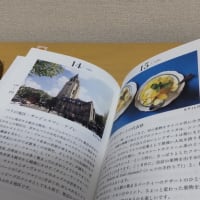
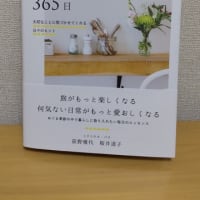
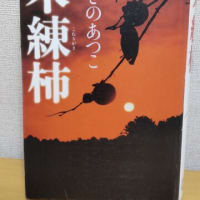

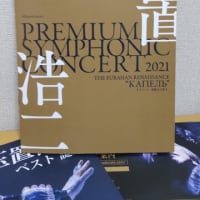
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます