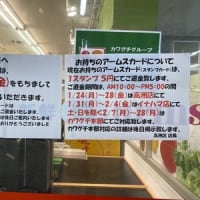先日お伝えしたとおり、「立地適正化計画」を考える学習会が午後1時半から開催されました。立地適正化計画の現状や問題点について、市原市からは日本共産党市原市議団の加藤和夫市議が報告を行い、千葉市からは私が報告を行いました。
市原市は、医療・福祉・商業等を集約化する「都市機能誘導区域」をJR駅と京成ちはら台駅に集約し、居住誘導区域に人口を誘導するのが主な内容です。千葉市についても千葉駅などの中心拠点への都市機能の誘導を図る点ではほぼ同様の内容です。
中山教授からは、そもそもの発端は「国土と地域、コミュニティの再編」を国が打ち出し、立地適正化計画はそれを進めるための政策だと指摘。立地適正化計画の問題点は、①市街地を縮める仕組みは存在せず、郊外でも無計画な縮小を招くこと。②中心部への集中。③ネットワークが存在しなければ居住地が衰退。④既存のコミュニティ計画と関係していない、の4点を挙げました。
そのもとで千葉市と市原市の計画について、人口減少に歯止めをかけるなどの施策を積極的に進めた場合の人口推移も含まれた人口ビジョンを使わずに、国立社会保障人口問題研究所の人口推計を使って、人口減少を前提に計画を策定している問題。「人口10%減少にふさわしい千葉市に変える計画=人口10%減少を実現するまち」だと指摘されました。
人口はあまり減らないのだから、すべての居住地で住み続けられる施策が必要との話がありました。居住誘導区域の設定は交通ネットワークは欠かせず、立地適正化だけやってネットワークをおろそかにしたら失敗するとの指摘は、千葉市に当てはまります。
こうした内容を受けて、千葉市と市原市のまちづくりをどう展望すべきか、いくつかの視点をいただきました。今回についてはブログでは触れませんが、議会活動に活かしていきたいと思います。結論は、現行の計画は撤回すべきであり、中心部の開発と郊外部の生活困難でさらなる人口減少を招くとのことです。
まちづくりの基本は市民と行政などが一緒になって考えることだと思います。