
権威主義&独裁主義になりがちな間接民主制は、もう沢山である。
日本人はモロ権威主義だが、権威主義に踊らされると、権威を持つ者の意見が正しいと勘違いしてしまい、自分の頭で物事を考える事なく、権威を持つ者の意見を鵜呑みにしてしまう。
例えば医療に置き換えてみると、医者がワクチンを推進しているから、ワクチン接種は当たり前だと勘違いしている。ここに集まる皆さんは、ワクチンの危険性を認知しているが、メディアの情報や、B層からの情報を鵜呑みにしている人達は、結局、権威主義に騙されてしまっている。抗癌剤にも同じ事が言える。
法曹界もデタラメで、法曹界は一般常識が通用する場所では無く、如何に屁理屈をこねられるかによって、勝敗が決まる様な所がある。不正選挙裁判の経験者なら理解出来るが、法曹界は権力者の味方であり、権力者を守る為の装置であると云う事が理解出来るであろう。
「政治家の先生」と呼ばれている輩などは、権威主義を振りかざし、国民をないがしろにした政治を行う、狂言役者である。
権威=絶対、みたいな構図を勝手に妄想する子羊達は、権威主義の恰好の餌である。権威主義から脱却しないと事実が見えてこず、何時までも権威に騙される事に成る。
権威とは、バカの壁であり、常識と言う危ない価値観を植え付ける物であり、国民をバカのまま洗脳する為の装置である。
間接民主制は国民の代表を選挙で選び、政治家に国の運営を任せる制度だが、不正選挙が当たり前の日本では、権力者の好きなように当選者を選出出来る、危ない制度である。
子羊達は、性善説が頭にこびり付いていて、先進国である日本の選挙に、不正など有る筈も無いと、洗脳されている為に、安保法案反対のデモを行い、デモで政権を引っくり返そうと必死だが、闘うポイントがズレている。安保法案反対のデモは日本中に広がりを見せているが、政権側は、選挙によって選ばれた国民の代表と言う建前で、無理やりにでも安保法案を通すだろう。安保法案反対のデモでは無く、本来は不正選挙のデモをぶちかますのが、本当の闘い方である。
闘い方も知らない子羊を量産するのが、権威主義であり、権威主義が蔓延っていては、国民が幸せになる事は難しい。
直接民主制は国民投票によって、物事が決まっていくので、国民が問題点を熟知する必要がある。問題点を熟知すると云う事は、自分の頭で物事を考える事なので、権威主義に騙される事は無くなる。自分の頭で考える事を覚えた国民は、何が善か悪かを瞬時に判断し、正しい選択が出来る。
子羊達には自分の頭で考えると云う事を、学んで欲しい。
直接民主制ちょくせつみんしゅせい
direct democracy
国民がみずから直接,国家意思の形成に参加する民主制。間接民主制に対立する概念。アテネにおける民主制がその典型とされるが,もとより古代ポリスにおける民主制は,きわめて狭い地域においてのものであった。
本文は出典元の記述の一部を掲載しています。
https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%88%B6-98310
間接民主制 カンセツミンシュセイ
かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】
国民が代表者を選挙し、その代表者を通じて間接に政治に参加する制度。
https://kotobank.jp/word/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%88%B6-470509
-------世界が注目、スイスの直接民主制-------
スイスの直接民主制は今、外国から熱い視線を浴びており、外国の視察団が続々とスイスを訪れている。特に大きな関心を示しているのは、ドイツ語圏諸国だ。近い将来、スイスの政治システムをまねて導入する国が出てくるかもしれない。
ドイツのバーデン・ヴュルテンベルク(Baden-Württemberg)州代表団は2012年3月11日、スイスを訪問し、この日行われた国民投票を視察。また、オーストリアのミヒャエル・シュピンデルエッガー副首相は5月6日、スイスのディディエ・ブルカルテール外相と共に、グラールス州で開かれたランツゲマインデ(Landsgemeinde・州の全有権者を町の広場に集め法案の可否を問う集会)を見学。6月には、アールガウ州はドイツのバーデン・ヴュルテンベルク州と共同で、直接民主主義について議論を行う民主主義会議(Demokratiekonferenz)をアールガウ州の首都アーラウ(Aarau)で開催した。
さらに、ドイツのラインラント・プファルツ(Rheinland-Pfalz)州のクルト・ベック州首相は来る9月23日、スイスで行われる国民投票の様子を現地視察し、民主主義の研究機関「アーラウ民主主義センター(ZDA)」を訪問する予定だ。
ヨーロッパの先駆国
「欧州連合(EU)だけではなく、南米のウルグアイなどもスイス式の直接民主制に興味を示している。(スイスの好イメージを外国にPRする政府機関である)『プレゼンツ・スイス(Präsenz Schweiz)』はウルグアイをスイスに招待しており、近日中にもウルグアイの代表団がこのセンターを訪問予定だ」とZDAの政治学者、ウヴェ・セルデュルト氏は語る。
直接民主制の特色として、有権者は一定数の署名を集めれば国レベルの国民投票を要求できる。近頃公表されたZDAの研究結果によれば、この制度を認めている国は、1920年以前はスイスだけだった。現在の西ヨーロッパではスイス以外に、リヒテンシュタイン公国、イタリア、サンマリノ共和国が導入している。
その他にアメリカ、カナダ、オーストラリア、1990年代以降は東ヨーロッパの14カ国(ラトビア、リトアニア、ハンガリーなど)、そして南米のウルグアイ、コロンビア、ベネズエラにも同様の制度がある。「ウルグアイが『南米のスイス』と呼ばれるゆえんだ」と、同研究に携わったセルデュルト氏は言う。
間接民主制への不満
「外国がスイスの直接民主制に興味を持つのは、間接民主制への不満が高まっているからだ。選挙で選出された議員に政治を任せるのではなく、自分で直接政治に参加したい人が増えている」とセルデュルト氏は続ける。
社会民主党(SP/PS)の全州議会(上院)議員で民主主義に詳しいアンドレアス・グロス氏は次のように語る。「すべての民主制度は危機に陥っている。民主制は永続的に発展していくプロセスなのだが、現在は発展というよりも衰退状態にある」
グロス氏はまた、「民主主義を弱体化する」動きがここ数年見受けられると話す。既存の民主主義国家はみんな権威主義に傾き、権力は徐々に施政者に移りつつあるという。さらにグローバル時代の今、国家が外国の影響を無視して独自に物事を決めるのは難しくなってきており、国際的な民主主義制度でも確立しない限り、国民の意見を政治に反映させるのは難しいと語る。そのため、選挙の投票に行くだけでは理想的な民主制を築けないという確信が世間に広まりつつあるという。
そうした中、EU危機も相まって、ヨーロッパ諸国はEU未加入国のスイスを羨望のまなざしで見つめているとの意見もある。それに対し、グロス氏は違う見解だ。「スイスは羨望などされていない。むしろ、エキゾチックでよくわからない国と見なされている。人権擁護と金融関連のテーマがスイスの特色としてよく挙げられる。しかし、直接民主制こそがスイスの素晴らしい特徴だともっと訴えていく必要がある」
憲法裁判所の不在
一方、直接民主制は危険だという意見もある。例えば、外国人国外強制退去などの国民発議は、少数派の権利を傷つけるかもしれないからだ。ただ、この国民発議は憲法上保障されている人権に抵触する恐れがあるため、実現はほぼ不可能だ。
スイスではここ数年、こうした人権にかかわるような国民発議が度々ある。直接民主制の弱点として、多数派が少数派を隅に追いやってしまうことが挙げられる。スイスの憲法では、「多数派による専制政治」から少数派を守ることはできない。だが、グロス氏は「(少数派が守られないのは)直接民主制のせいではない」と強調する。
イニシアチブやレファレンダムの憲法適合性を判断する憲法裁判所がスイスには必要なのだろうか。「民主制にはそのような裁判所が必要」と確信しているのは、スロべニアのチリル・リビチッチ憲法裁判官だ。スロべニアの有権者もスイスと同様、イニシアチブとレファレンダムの権利を有する。
グロス氏も同じ点を強調する。「憲法裁判所は、直接民主制を改善していくために欠かせない存在だ。直接民主制はこの100年間、婦人参政権などごく一部の例外を除いては全く進歩していないし、改善もされていない。スイスの直接民主制も改革の必要がある」
最も成功率が高いのは市民団体
前出のZDA研究では、直接民主制の権利であるイニシアチブとレファレンダムの成功率も分析された。その結果、最も成功率が高いのは、市民団体が行った場合と判明した。「(ほかの団体に比べ、)市民団体ほど直接民主制を利用する人たちはいない。これはスイスでも他国でも同様だ」とZDAのウヴェ・セルデュルト氏は語る。
「直接民主制は、初期の段階では野党の権力闘争の道具として使われることが多い。スイスでも長期間その傾向が見られた。しかし、時間がたつにつれて市民社会に浸透する」
そのままコピーはしない
「外国の視察団は我々から学ぶことはしても、スイス式の直接民主制をそっくりそのままコピーする気はない。視察団のメンバーは全員プロの政治家で、直接民主制の怖さも十分承知している。国民のもっと積極的な政治への参加を訴える反面、スイスのように国民からの要求でがんじがらめにされるのは避けたいというのが本音だ。スイスでは投票結果がものをいうが、ドイツの国民投票は単に『世論調査』で、法的拘束力はない」とセルデュルト氏。
ところで、スイスは、シリアの反体制派がアサド体制崩壊後を議論するベルリンでの会合を支援している。「その後のシリア」はスイス式の直接民主制からメリットを得ることができるのだろうか?セルデュルト氏はそれには答えられないと言う。「直接民主制や連邦主義を全くそのままの形で導入できるかどうかは難しい問題だ。シリアを例に挙げても、民主主義への政治体制の移行は世代を超えて続くプロセスになる」と答えた。
直接民主制
直接民主制とは、国民が直接、権力を行使し、政治決定に関わる政治制度。
それに対し間接民主制(代表民主制)では、国民は自分たちが選んだ代表者に権力を委ね、間接的に政治に参加する。
スイスの直接民主制で最も重要な制度は、イニシアチブと任意のレファレンダム。
スイスの政治制度には直接民主制のほかに、州と国民を代表する連邦議会(全州議会・国民議会)があるため、(スイスの政治システムは半直接民主制と呼ばれることもある。
イニシアチブとレファレンダム
スイスの有権者は、イニシアチブにより連邦憲法改正を提案する権利がある。連邦レベルのイニシアチブは、18ヶ月以内に有権者10万人分以上の有効署名を集め、連邦内閣事務局(Bundeskanzlei/ Chancellerie fédérale)に提出することで成立。
成立したイニシアチブは、連邦議会で協議される。連邦議会は、法案を承認、否決または対案を提出することができる。どの場合でも、国民投票に採決がかけられる。
イニシアチブが可決されるためには、投票者の過半数および州の過半数の賛成票が必要。
(随意の)レファレンダムは、連邦議会を通過した法律の可否を国民が最終的に判断する権利。連邦議会で新しく採決された法律に反対する有権者は、連邦議会が同法律の承認を公表した後100日以内に5万人分の有効署名を集め、連邦内閣事務局に提出すると、連邦レベルの国民投票に持ち込める。
連邦議会が憲法改正案を承認した場合は、強制的レファレンダムによりその憲法改正案が義務的に国民投票にかけられる。
随意のレファレンダムが成立するためには、投票者の過半数の賛成票が必要。強制レファレンダムでは投票者と州の過半数の賛成票が必要。
ヨーロッパの市民イニシアチブ
欧州連合(EU)では、リスボン条約(欧州連合条約および欧州共同体設立条約を修正する条約、2009年12月1日に発効)により欧州市民イニシアチブが制定された。この制度は2012年4月1日から施行された。
欧州市民イニシアチブはドイツのいくつかの州やオーストリアで行われる国民投票に類似している。EU加盟国の国籍を持つ市民は、欧州委員会に対してEUの法律改正を要求できる。しかし、国民投票はイニシアチブの権利に含まれていない。
http://www.swissinfo.ch/jpn/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%8C%E3%81%8A%E6%89%8B%E6%9C%AC-_%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E6%B3%A8%E7%9B%AE-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%88%B6/33539920
日本人はモロ権威主義だが、権威主義に踊らされると、権威を持つ者の意見が正しいと勘違いしてしまい、自分の頭で物事を考える事なく、権威を持つ者の意見を鵜呑みにしてしまう。
例えば医療に置き換えてみると、医者がワクチンを推進しているから、ワクチン接種は当たり前だと勘違いしている。ここに集まる皆さんは、ワクチンの危険性を認知しているが、メディアの情報や、B層からの情報を鵜呑みにしている人達は、結局、権威主義に騙されてしまっている。抗癌剤にも同じ事が言える。
法曹界もデタラメで、法曹界は一般常識が通用する場所では無く、如何に屁理屈をこねられるかによって、勝敗が決まる様な所がある。不正選挙裁判の経験者なら理解出来るが、法曹界は権力者の味方であり、権力者を守る為の装置であると云う事が理解出来るであろう。
「政治家の先生」と呼ばれている輩などは、権威主義を振りかざし、国民をないがしろにした政治を行う、狂言役者である。
権威=絶対、みたいな構図を勝手に妄想する子羊達は、権威主義の恰好の餌である。権威主義から脱却しないと事実が見えてこず、何時までも権威に騙される事に成る。
権威とは、バカの壁であり、常識と言う危ない価値観を植え付ける物であり、国民をバカのまま洗脳する為の装置である。
間接民主制は国民の代表を選挙で選び、政治家に国の運営を任せる制度だが、不正選挙が当たり前の日本では、権力者の好きなように当選者を選出出来る、危ない制度である。
子羊達は、性善説が頭にこびり付いていて、先進国である日本の選挙に、不正など有る筈も無いと、洗脳されている為に、安保法案反対のデモを行い、デモで政権を引っくり返そうと必死だが、闘うポイントがズレている。安保法案反対のデモは日本中に広がりを見せているが、政権側は、選挙によって選ばれた国民の代表と言う建前で、無理やりにでも安保法案を通すだろう。安保法案反対のデモでは無く、本来は不正選挙のデモをぶちかますのが、本当の闘い方である。
闘い方も知らない子羊を量産するのが、権威主義であり、権威主義が蔓延っていては、国民が幸せになる事は難しい。
直接民主制は国民投票によって、物事が決まっていくので、国民が問題点を熟知する必要がある。問題点を熟知すると云う事は、自分の頭で物事を考える事なので、権威主義に騙される事は無くなる。自分の頭で考える事を覚えた国民は、何が善か悪かを瞬時に判断し、正しい選択が出来る。
子羊達には自分の頭で考えると云う事を、学んで欲しい。
直接民主制ちょくせつみんしゅせい
direct democracy
国民がみずから直接,国家意思の形成に参加する民主制。間接民主制に対立する概念。アテネにおける民主制がその典型とされるが,もとより古代ポリスにおける民主制は,きわめて狭い地域においてのものであった。
本文は出典元の記述の一部を掲載しています。
https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%88%B6-98310
間接民主制 カンセツミンシュセイ
かんせつ‐みんしゅせい【間接民主制】
国民が代表者を選挙し、その代表者を通じて間接に政治に参加する制度。
https://kotobank.jp/word/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%88%B6-470509
-------世界が注目、スイスの直接民主制-------
スイスの直接民主制は今、外国から熱い視線を浴びており、外国の視察団が続々とスイスを訪れている。特に大きな関心を示しているのは、ドイツ語圏諸国だ。近い将来、スイスの政治システムをまねて導入する国が出てくるかもしれない。
ドイツのバーデン・ヴュルテンベルク(Baden-Württemberg)州代表団は2012年3月11日、スイスを訪問し、この日行われた国民投票を視察。また、オーストリアのミヒャエル・シュピンデルエッガー副首相は5月6日、スイスのディディエ・ブルカルテール外相と共に、グラールス州で開かれたランツゲマインデ(Landsgemeinde・州の全有権者を町の広場に集め法案の可否を問う集会)を見学。6月には、アールガウ州はドイツのバーデン・ヴュルテンベルク州と共同で、直接民主主義について議論を行う民主主義会議(Demokratiekonferenz)をアールガウ州の首都アーラウ(Aarau)で開催した。
さらに、ドイツのラインラント・プファルツ(Rheinland-Pfalz)州のクルト・ベック州首相は来る9月23日、スイスで行われる国民投票の様子を現地視察し、民主主義の研究機関「アーラウ民主主義センター(ZDA)」を訪問する予定だ。
ヨーロッパの先駆国
「欧州連合(EU)だけではなく、南米のウルグアイなどもスイス式の直接民主制に興味を示している。(スイスの好イメージを外国にPRする政府機関である)『プレゼンツ・スイス(Präsenz Schweiz)』はウルグアイをスイスに招待しており、近日中にもウルグアイの代表団がこのセンターを訪問予定だ」とZDAの政治学者、ウヴェ・セルデュルト氏は語る。
直接民主制の特色として、有権者は一定数の署名を集めれば国レベルの国民投票を要求できる。近頃公表されたZDAの研究結果によれば、この制度を認めている国は、1920年以前はスイスだけだった。現在の西ヨーロッパではスイス以外に、リヒテンシュタイン公国、イタリア、サンマリノ共和国が導入している。
その他にアメリカ、カナダ、オーストラリア、1990年代以降は東ヨーロッパの14カ国(ラトビア、リトアニア、ハンガリーなど)、そして南米のウルグアイ、コロンビア、ベネズエラにも同様の制度がある。「ウルグアイが『南米のスイス』と呼ばれるゆえんだ」と、同研究に携わったセルデュルト氏は言う。
間接民主制への不満
「外国がスイスの直接民主制に興味を持つのは、間接民主制への不満が高まっているからだ。選挙で選出された議員に政治を任せるのではなく、自分で直接政治に参加したい人が増えている」とセルデュルト氏は続ける。
社会民主党(SP/PS)の全州議会(上院)議員で民主主義に詳しいアンドレアス・グロス氏は次のように語る。「すべての民主制度は危機に陥っている。民主制は永続的に発展していくプロセスなのだが、現在は発展というよりも衰退状態にある」
グロス氏はまた、「民主主義を弱体化する」動きがここ数年見受けられると話す。既存の民主主義国家はみんな権威主義に傾き、権力は徐々に施政者に移りつつあるという。さらにグローバル時代の今、国家が外国の影響を無視して独自に物事を決めるのは難しくなってきており、国際的な民主主義制度でも確立しない限り、国民の意見を政治に反映させるのは難しいと語る。そのため、選挙の投票に行くだけでは理想的な民主制を築けないという確信が世間に広まりつつあるという。
そうした中、EU危機も相まって、ヨーロッパ諸国はEU未加入国のスイスを羨望のまなざしで見つめているとの意見もある。それに対し、グロス氏は違う見解だ。「スイスは羨望などされていない。むしろ、エキゾチックでよくわからない国と見なされている。人権擁護と金融関連のテーマがスイスの特色としてよく挙げられる。しかし、直接民主制こそがスイスの素晴らしい特徴だともっと訴えていく必要がある」
憲法裁判所の不在
一方、直接民主制は危険だという意見もある。例えば、外国人国外強制退去などの国民発議は、少数派の権利を傷つけるかもしれないからだ。ただ、この国民発議は憲法上保障されている人権に抵触する恐れがあるため、実現はほぼ不可能だ。
スイスではここ数年、こうした人権にかかわるような国民発議が度々ある。直接民主制の弱点として、多数派が少数派を隅に追いやってしまうことが挙げられる。スイスの憲法では、「多数派による専制政治」から少数派を守ることはできない。だが、グロス氏は「(少数派が守られないのは)直接民主制のせいではない」と強調する。
イニシアチブやレファレンダムの憲法適合性を判断する憲法裁判所がスイスには必要なのだろうか。「民主制にはそのような裁判所が必要」と確信しているのは、スロべニアのチリル・リビチッチ憲法裁判官だ。スロべニアの有権者もスイスと同様、イニシアチブとレファレンダムの権利を有する。
グロス氏も同じ点を強調する。「憲法裁判所は、直接民主制を改善していくために欠かせない存在だ。直接民主制はこの100年間、婦人参政権などごく一部の例外を除いては全く進歩していないし、改善もされていない。スイスの直接民主制も改革の必要がある」
最も成功率が高いのは市民団体
前出のZDA研究では、直接民主制の権利であるイニシアチブとレファレンダムの成功率も分析された。その結果、最も成功率が高いのは、市民団体が行った場合と判明した。「(ほかの団体に比べ、)市民団体ほど直接民主制を利用する人たちはいない。これはスイスでも他国でも同様だ」とZDAのウヴェ・セルデュルト氏は語る。
「直接民主制は、初期の段階では野党の権力闘争の道具として使われることが多い。スイスでも長期間その傾向が見られた。しかし、時間がたつにつれて市民社会に浸透する」
そのままコピーはしない
「外国の視察団は我々から学ぶことはしても、スイス式の直接民主制をそっくりそのままコピーする気はない。視察団のメンバーは全員プロの政治家で、直接民主制の怖さも十分承知している。国民のもっと積極的な政治への参加を訴える反面、スイスのように国民からの要求でがんじがらめにされるのは避けたいというのが本音だ。スイスでは投票結果がものをいうが、ドイツの国民投票は単に『世論調査』で、法的拘束力はない」とセルデュルト氏。
ところで、スイスは、シリアの反体制派がアサド体制崩壊後を議論するベルリンでの会合を支援している。「その後のシリア」はスイス式の直接民主制からメリットを得ることができるのだろうか?セルデュルト氏はそれには答えられないと言う。「直接民主制や連邦主義を全くそのままの形で導入できるかどうかは難しい問題だ。シリアを例に挙げても、民主主義への政治体制の移行は世代を超えて続くプロセスになる」と答えた。
直接民主制
直接民主制とは、国民が直接、権力を行使し、政治決定に関わる政治制度。
それに対し間接民主制(代表民主制)では、国民は自分たちが選んだ代表者に権力を委ね、間接的に政治に参加する。
スイスの直接民主制で最も重要な制度は、イニシアチブと任意のレファレンダム。
スイスの政治制度には直接民主制のほかに、州と国民を代表する連邦議会(全州議会・国民議会)があるため、(スイスの政治システムは半直接民主制と呼ばれることもある。
イニシアチブとレファレンダム
スイスの有権者は、イニシアチブにより連邦憲法改正を提案する権利がある。連邦レベルのイニシアチブは、18ヶ月以内に有権者10万人分以上の有効署名を集め、連邦内閣事務局(Bundeskanzlei/ Chancellerie fédérale)に提出することで成立。
成立したイニシアチブは、連邦議会で協議される。連邦議会は、法案を承認、否決または対案を提出することができる。どの場合でも、国民投票に採決がかけられる。
イニシアチブが可決されるためには、投票者の過半数および州の過半数の賛成票が必要。
(随意の)レファレンダムは、連邦議会を通過した法律の可否を国民が最終的に判断する権利。連邦議会で新しく採決された法律に反対する有権者は、連邦議会が同法律の承認を公表した後100日以内に5万人分の有効署名を集め、連邦内閣事務局に提出すると、連邦レベルの国民投票に持ち込める。
連邦議会が憲法改正案を承認した場合は、強制的レファレンダムによりその憲法改正案が義務的に国民投票にかけられる。
随意のレファレンダムが成立するためには、投票者の過半数の賛成票が必要。強制レファレンダムでは投票者と州の過半数の賛成票が必要。
ヨーロッパの市民イニシアチブ
欧州連合(EU)では、リスボン条約(欧州連合条約および欧州共同体設立条約を修正する条約、2009年12月1日に発効)により欧州市民イニシアチブが制定された。この制度は2012年4月1日から施行された。
欧州市民イニシアチブはドイツのいくつかの州やオーストリアで行われる国民投票に類似している。EU加盟国の国籍を持つ市民は、欧州委員会に対してEUの法律改正を要求できる。しかし、国民投票はイニシアチブの権利に含まれていない。
http://www.swissinfo.ch/jpn/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%8C%E3%81%8A%E6%89%8B%E6%9C%AC-_%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E6%B3%A8%E7%9B%AE-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%88%B6/33539920


















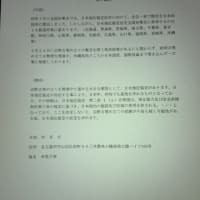
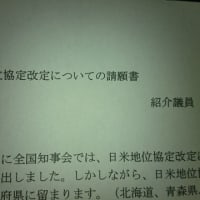

自分の頭で考えて行動しないと、やりたい放題やられちゃうんだよ~。|||(-_-;)||||
信じちゃいけない人間を信じちゃダメなんだよ~。
民間企業の新人を戦地に投入 防衛省が画策する「隠れ徴兵制」
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163195
民間企業に就職したと思ったら、配属先は「自衛隊」だった――。防衛省が密かに検討していた「徴兵プログラム」が国会で取り上げられ、大騒ぎになっている。
明らかになったのは26日の参院安保法制特別委。共産党の辰巳孝太郎議員は、防衛省が13年7月に作成した「長期 自衛隊インターンシップ・プログラム(企業と提携した人材確保育成プログラム)」と題した資料を掲げて質問。資料には「プログラムのイメージ」として、最初に「企業側で新規採用者等を2年間、自衛隊に『実習生』として派遣する」とハッキリ書いてあり、ほかに「自衛隊側で、当該実習生を『一任期限定』の任期制士として受け入れる」「自衛隊側は当該者を自衛官として勤務させ(略)」とあった。
安倍首相は25日の参院特別委で「徴兵制、徴兵制と、はやす人々は全く無知と言わざるを得ない」と言っていたが、防衛省自身が「インターンシップ」というゴマカシ言葉を使って実質的に「徴兵制」を検討していた事実をどう考えるのか。
「企業を通じて戦地に(若者を)送るようなシステムを一経営者に提案をする発想そのものが恐ろしい」
GPIFの運用実績チャラ…世界株安で「年金5兆円消失」の恐れ
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163188
このブログで度々問題になっていた投稿できないURLですが、どうやら’-’(ハイフン)がまざっているURLがダメなようです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5208971.html
まあ、こちらにあるように短縮URLにするか、
URLをコピペするときに自動でつけるhttp://を取ってしまうと書き込みできます。
http://がなくなるとスクリプトがurlと判定しなくなるのでリンクが貼られませんが、まあコピペすれば何とかなるので一応は大丈夫です。
うーん、やっぱgooブログのスクリプトのバグだと思うんだけど何とかならないもんでしょうかね~。