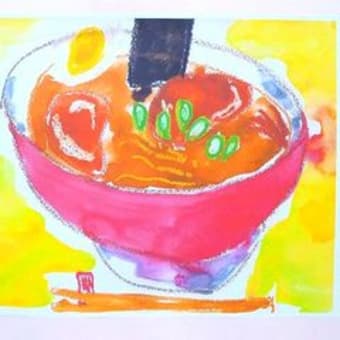「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック教育研究所
お子さんが間違った行動をしたときに、理由を説明して諭すのもひとつの方法ですが、有無もなくNOサインを出すのもひとつです。
指でバツ印を作って示す、腕で大きくバツ印を作って示す、手のひらを示して「NO!」と制止する、「ムッ!」と咎める表情をする・・・、教室の親御さんもそれぞれに工夫されています。
たとえば、他者が使っているものを衝動的に取ってしまった場合:
理由を説明して諭すことが有効であるためには、
・言葉の理解ができる
・状況の理解ができる
・自分と他者と物との関係を理解できる
という条件の揃うことが必要です。
条件が揃わないのに諭そうとすると、お子さんにとっては”訳のわからないことを長々と言われている”というだけになってしまいます。しかもそれを怒りながら言ったら、お子さんは自分の行動が否定された上に叱られて、イライラするばかりです。
小さいときから、NOサインを的確に出していきましょう。
1)はじめはサインの意味が分からずに、パニックになることもあるでしょう。NOサインの意味を理解させるのに多少の時間はかかります。行動を改めることができたら、その場ですぐに動作を伴ってほめましょう。
ほめることによって、お母さんが何を望んでいるのか、何が悪くてどうすれば良いのかをお子さんは理解します。その積み重ねによって、NOサインの意味が分かってきます。また、NOサインを受け入れる心理状況も発達に従って備わってきます。
2)マイナスの行動をしてしまうのには、悪いのはわかっているけれど衝動的に行ってしまう場合があります。その場合は、NOサインは衝動の抑止の意味があります。自分では制しきれないことを、他者の力で抑止してあげるのです。
3)もうひとつは、状況の正しい判断ができない、他者が見えていない、ということもあります。その場合は判断を、サインを出してくれる親御さんに委ねているのです。
発達障害の方の中には、長じたお子さんや成人であっても、「そんなことしたらいけないのは、当たり前でしょ」と思うことでも判断しきれないことがあります。そのことを自分でも知っていて、その判断部分を自分以外の信頼でいる人に委ねているのです。
ですからNOサインが出されると、意外とあっさりそれに従うことができるのです。そこには成長のプロセスで培われてきた大きな信頼があるからです。
クドクドと説明するのではなく、NOサインが的確に出せるように今日から試みてはいかがでしょう。最初はうまくいかないかもしれませんが、あきらめずに。でも、何より大切なのは、行動を調整することだけなく、そこに信頼関係を育てていくことだということをお忘れなく。
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp