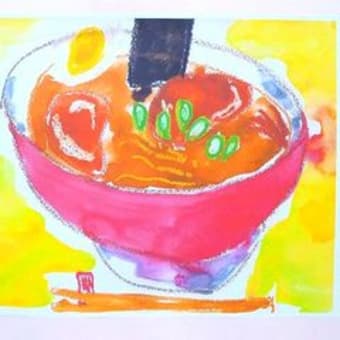「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック教育研究所
きょう8月6日は、64回目の広島原爆忌でした。広島平和記念公園での平和記念式典、テレビから流れる「平和の鐘」の音と共に8時15分の黙祷を奉げた方もたくさんいらっしゃることでしょう。お子さんと戦争について、原子力爆弾について、多くの犠牲について、命について、平和について、何か触れることはできたでしょうか。
小学校3年生の国語の教科書に、「ちいちゃんのかげおくり」(あまんきみこ作)というお話があります。空襲の夜、炎の渦の中をお母さんとお兄ちゃんと逃げ惑い、はぐれてしまった女の子ちいちゃんは、夏のはじめのある朝、空色の花畑の中(「きっと、ここ、空の上よ。」とちいちゃんは思いました)で、出征したお父さん、はぐれてしまったお母さんとお兄ちゃんと再会する、という悲しいお話です。
このお話を教室で生徒さんと読みました。
「出征する」という言葉をはじめ、
「お父さんは、白いたすきをかたからななめにかけ、日の丸のはたに送られて、列車に乗りました」と読んでも、生徒さんはイメージを持つことができません。
「体の弱いお父さんまで、いくさにいかなければならないなんて。」というお母さんのぽつんと漏らした言葉にも、生徒さんはその悲しみを読み取ることができないのです。
問題集には、「このお母さんの言葉からどんなことがわかりますか?」という問いがあります。
( )いくさが、かなりひどくなっていること。
( )いくさが、もうすぐ終わりそうだということ。
( )いくさが、勝ち進んでいるといること。
「体の弱い人まで必要になるほど、いくさがひどい状況で人が足りなくなったのだろう」ということを読み取らせようとしているのです。
今日お話したいのは、生徒さんの読解力の問題ではありません。あの戦争があまりに遠い昔のことのようになってしまって、子どもの生活とかけ離れてしまってるということです。
私が子どもの頃には、8月にはもっとたくさんの番組が特集されていて、昼間も夕食の時間にも家族一緒にテレビを見たような思いがします。「戦争を知らない子ども達」と歌われた世代ですが、夏休みのひと日にはそんな番組を見て両親から話を聞いたことが夏休みの思い出と重なります。
なんだかこわくて夜眠れなかったり、壁の染みまでがなんだか恐ろしいものに見えたりと、今でもその思いが蘇ってきます。心の深くに戦争の恐ろしさが根付きます。戦争に対する忌避観、嫌悪感、拒絶感を持つことは、平和の創造において肝要です。
8月9日の長崎原爆忌、8月15日の終戦記念日、年に1回は戦争について、命について、平和について親子で触れるときを持たれてはいかがでしょうか。お子さんの状況を考えて、受け容れられる範囲でどうぞそんな機会をお持ちになってみてください。
ただし、発達段階や心理状況によって、お子さんに受け容れられる範囲とその範囲を越えてしまうものとがありますから、不安を与えすぎないようにご配慮下さい。
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp