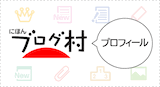全国の天気 今日の天気 明日の天気 週間天気予報 地震情報 台風情報
目薬をさした後に「まぶたパチパチ」が逆効果の訳 目薬の正しい点眼方法を知っていますか?

「熱が出たから風邪薬か解熱剤を飲もう」「便秘で苦しいときには下剤を飲まないと」と、体調が悪くなると手っ取り早く薬に頼る人がほとんどでしょう。ただ、薬は症状を緩和する効果がある一方で、副作用による悪影響を体に与えてしまうものです。そんな薬の飲み方や副作用にいたるまでをわかりやすく解説した薬剤師の鈴木素邦さんの著書『その一錠があなたの寿命を縮める 薬の裏側』より一部抜粋・再構成してお届けします。
目薬の点眼の仕方は、9割が間違っている?
目薬の使い方、皆さんは自信ありますか? 飲み薬と違って、使い方が間違っていると治療効果が期待できません。体感的に患者さんの90%は何かしら間違えている人が多いです。
目薬は、最もデリケートな粘膜である眼球表面に使うものですから、微生物が付かないように無菌な状態で作られ、錠剤以上に注意されて出荷されてきます。また、液体ですから細菌やウイルスなどの微生物が侵入すると、増殖する恐れがあるため、開封後の取り扱いには気を付けなければなりません。
そのため目薬を使用する前に、必ず手を洗い、先端は触らないようにしましょう。先端を触らないとしても、開封と同時に外気と液体は接触することになりますので、少なからず微生物は侵入することになります。そのため、明確な決まりは定められておりませんが、目薬は開封したら1カ月以内が使用期限と考えておきましょう。なお、目薬のボトルに使用期限が書かれていますが、これは開封しない時の使用期限となります。
目薬のキャップも置き方にルールがあります。キャップの内側は、目薬の先端と接触する場所になります。微生物がキャップ経由で入らないようにするために、目薬本体の先端部と触れる凹側を上にしておきます。キャップを置かずに持ち続けることも可能ですが、慣れるまでは置く方が良いと思います。
正しい点眼の仕方
目薬の点眼には、2つの原則があります。容器の先端が眼球や目尻に接触すると、無菌で製剤化されていた薬液に、微生物が混入してしまいます。雑菌が入らないように注意が必要で、眼球や目尻と目薬の先端が触れないようにすることが大切です。
点眼量は、1滴目に入る目薬は、1滴滴下で充分な効果がでるように設計されています。2滴、3滴と垂らすと効果が出そうと思われる方もいらっしゃる印象ですが、まぶたの中には、目薬1滴分しか留められないため、それより多く垂らしたものは、顔をつたって溢れ出てしまいます。

(画像:『その一錠があなたの寿命を縮める 薬の裏側』より)
溢れた目薬が勿体ないだけでなく、処方薬であれば、次回の通院日の前に薬が足らなくなる可能性もあります。点眼するときは、そのまま点眼でもよいですが、上手くできない時は、「げんこつ法」を試してみてください。
①右手で目薬の容器を持ちます。②左手でげんこつを作って目の下の頬に当て、下まぶたを引っ張るように、あっかんベーをするような感じ③上を向き、左手のげんこつの上に目薬を持った右手を乗せて手を安定させて点眼します。
次に点眼後ですが、「目頭を軽く1分間押さえる」ことが重要です。目頭には、鼻に抜ける穴があり、眼にある液体は目頭付近から鼻に移動することができます。目薬も眼にある液体になりますから、この管に目薬が入ってしまうことが度々あり、目薬が目以外の場所に流れ出てしまいます。そのため、点眼後は軽く目頭を1分以上押さえてください。押さえないと効果がどんどん下がってしまいます。
点眼後、まぶたを閉じたり、開いたりするのはNG
目薬を使用後、目の中にまんべんなく目薬が届くように、目を動かしたり、まぶたを閉じたり開けたりされる方がいらっしゃいますが、これは逆効果です。目を動かすと、目頭の穴から薬が逃げやすくなり、まぶたをパチパチすると薬が目の外に出てしまう可能性が高まります。目薬を点眼後は、まぶたを閉じて静かにしていることがポイントになります。
目薬使用後には、液体が流れてくるのでティッシュで拭いたり、使用後に洗顔してしまう方が多いと思いますが、注意事項があります。目薬使用後のティッシュ使用方法は、まぶたを閉じて流れ出てくる液体を拭くのはOKですが、目薬点眼後すぐに、目尻にティッシュをあてるのはNGです。
ティッシュは、かなり水分を吸収しますので、場合によっては、まぶた内に点眼した目薬のほとんどを吸い取ってしまうことがあります。ティッシュは、溢れ出てきた目薬を拭くときだけに使わないと、目薬の効果がでなくなってしまいます。
目の周りに落ちた点眼液を流し込んでいる場合は、顔についている汚れや細菌、花粉などが、目に入ってしまいます。目の粘膜はデリケートですから、目の周りに落ちた液体はふき取り、新たに1滴、まぶたに目薬を点眼しましょう。
目薬を複数種類使うときの話ですが、まず使用する順番です。目薬の透明度を確認していただいて、「透明か」「濁っているか」を見てください。透明ということは溶かされている薬の粒子が小さく吸収が早い、一方で、濁っている薬は溶かされている薬の粒子が大きいため吸収に時間がかかると判断します。そのため、透明な目薬を先に使いましょう。
吸収が比較的早いとはいえ5分程度はかかりますので、点眼後5分置いてから、濁っている目薬を使用するようにしましょう(薬によっては、10分の間隔をあける薬もありますので、医師や薬剤師から指示があるときはそちらを優先してください)。
ちなみに、眼軟膏(まぶたなどに塗れる軟膏)も使うときは、目薬の使用後に使うようにしてください。軟膏は少なからず油が入っているため、水性の目薬を弾いてしまいます。そのため、使用する順番は、①透明な目薬、②濁った目薬、③眼軟膏の順番で使用します。
子供が目薬を怖がる場合はどうするか?
子供は、目薬を怖がってしまうことが多いです。さらに飲み薬と違い、怖がっているときに力ずくで目薬点眼をする選択肢にはつかえません。泣いてしまい目薬が流れ出てしまい、効果がないのでやり直しになってしまいます。そんな時は、寝ているときにまぶたを広げて、点眼すると解決できます。
著者:鈴木 素邦
※ 2025/02/01 12:30 (東洋経済オンライン)
の掲載文章から引用しました。参考になれば幸いです。
ブログ村ランキングに参加しています
バナーをクリックして応援お願いします
おすすめのサイト