
「藤原頼長の群像」アマゾン電子書籍紹介。BOOK★WALKER電子書」
藤原頼長(1120年~1156年)平安後期の公卿。関白藤原盛実の次男。母は忠実の養子となる。異母兄忠通の養子となる。1130年(大字)元服にあたって正五位下に叙せられ、翌年従三位、以降中納言、権大納言と進み、1136年(保延2)にわずか17歳で内大臣となる。1147年(久安3)左大臣有仁の死後、一上の宣旨を賜わり、蔵人所別当となるや、外記日記・殿上日記の筆録を督励し、上月月奏官人の出勤日数を天皇に上奏する、励行・官政などの朝議の復興に尽力を尽くした。1149年に左大臣となり、翌年天皇の外戚の地位を目指して近衛天皇に養女の多子を入内させた。頼長の博覧と公事に精励する姿に、摂関家の将来を期待した父忠実は、多子立后を終えると、兄忠通に頼長へ摂政を譲るように説得した。しかし忠通はこれを拒否したため、忠実は忠通を義絶氏長者の地位を取り上げて頼長に与えた。1151年(仁平元)に鳥羽法皇に奏上して、頼長に内乱の宣旨を蒙らせた。このた、摂政から関白に転じた忠通と内覧・氏長者の頼長との対立は激しさを増した。頼長は「なにごともいみじくきびしい人」という異名を持っていたという。そのためか鳥羽上皇もしだいに彼を「ウトミ思い召し」になった。1156年(久寿2)に近衛天皇が没すると、これが忠実・頼長の呪詛によると噂が流れ、法王の信頼を失って失脚、宇治に籠居を余儀なくされた。1156年(保元元)に鳥羽法皇が没すると後白河天皇、忠実らの挑発によって、崇徳上皇とともに挙兵に追い詰められた。頼長は奇襲あるいは東国へ下向を主張する源為義の意見を退けて、大和の武士や興福寺の悪僧信実・玄実らの到着待つうちに拠点とした白河北殿を天の方に急襲されて敗北。頼長は乱戦の流れ矢で重症負い、奈良に引きこもる父を訪ね面会を求めたが拒絶されその地で絶命した。










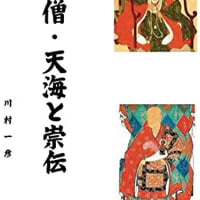

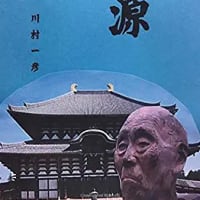
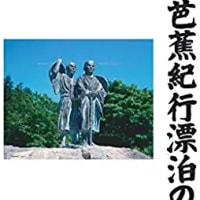
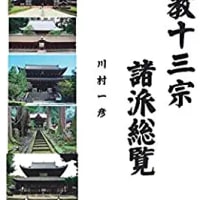
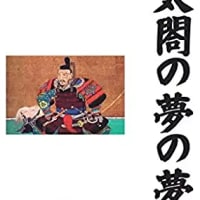
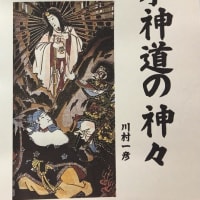
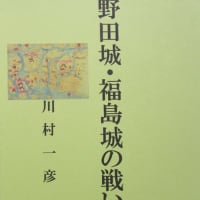
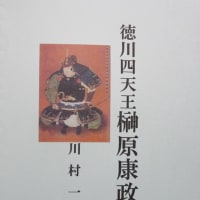
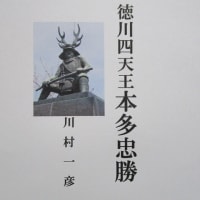
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます