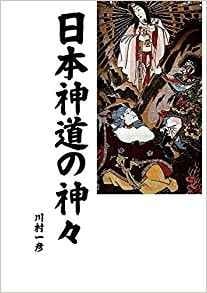 『日本神道の神々』1188円アマゾン書籍紹介。
『日本神道の神々』1188円アマゾン書籍紹介。日本の神道は仏教や儒教の伝来前には古神道が存在し、純神道、原始神道、神祇信仰は自然崇拝、物体、磐座や洞穴や奇岩、巨木に巨大岩石に峻険な峰々に精霊を感じ信仰されていった。また大自然の海や川、山岳に畏敬の念をもって祀られていた。それぞれの地域に集団で氏族が形成され、一族の崇敬する祭神が氏族の団結を高めていき、古神道が生まれていった。『記紀』が成立し、神話の世界から天地創造の神々が生まれ、いち早く地方へと神々の伝播されていった。仏教伝来と同時に、時代を経て融和、同化していった。それが「神仏習合であった。千年以上も神仏習合の歴史文化が明治維新の神仏分離令を持って、分別されていった。今や神社数、仏教寺院数はほぼ同じ勢力を持って棲み分け作って共存している。再び過去の日本神道は振り返って神道はどう進化と変化をしてきたか検証して見た。










 『大久保長安事件の陰謀』アマゾン電子書籍紹介。
『大久保長安事件の陰謀』アマゾン電子書籍紹介。 『幕藩一揆の攻防』アマゾン電子書籍紹介。
『幕藩一揆の攻防』アマゾン電子書籍紹介。 『幕閣列伝大老・老中』アマゾン電子書籍紹介
『幕閣列伝大老・老中』アマゾン電子書籍紹介 『戦国大名・敗将の有終』アマゾン電子書籍紹介。
『戦国大名・敗将の有終』アマゾン電子書籍紹介。