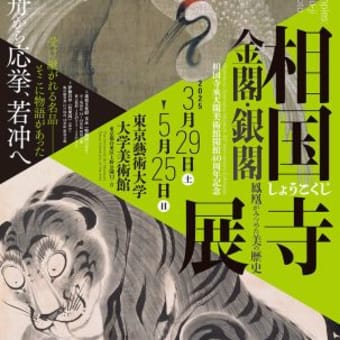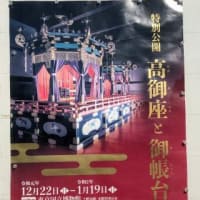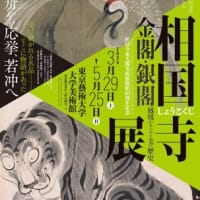丸ビルホールで行われた、
理化学研究所科学講演会に行って来ました。
実は、昨年も行ったのですが、
中々面白かったので、今回も行ったと言う次第。
今回の科学講演会は、生命系のお話がテーマの様でした。
- トップバッターは、
バイオリソース研究センター 微生物材料開発室 室長の
大熊 盛也 博士で、講演タイトルは
『生物研究に欠かせない材料、バイオリソース』
バイオリソースと言うのは、生物遺伝資源と言って、
生物・生命科学の研究を行う際の基礎材料。
つまりは、試料となる動植物と言う事ですね。
バイオリソースには、“実験動物”“実験植物”
“細胞材料”“遺伝子材料”“微生物材料”の
5分野があるそうなのですが、理研はその5つのすべての分野で、
世界でもトップレベルの機関なんだそうです。
本庶佑博士、大隅良典博士、山中伸弥博士、大村智博士など
日本人ノーベル賞受賞者が、研究につかった成果も、
収蔵されているそうです。
あと、そう言うアカデミアの分野だけではなく、
産業分野にもここのリソースは提供されていて、
Kirinのプラズマ乳酸菌は、ここのJCM5805株が
提供されて、開発されたものだそうです。
と、ここまで生物研究に関しての理研の貢献を聞いて思い出したのが、
理研関係者は思い出したくもないであろうO元博士の研究不正問題。
こんなに立派に、細胞などの供給体制があるのであれば、
あの実験試料もコンタミが起きることも無かっただろうと思うのだけどね?
- 二人目の講演者は、
開拓研究本部 坂井星・惑星形成研究室 主任研究員の
坂井 南美 博士で、講演のタイトルは
『次世代天文学 ~化学との融合~』
化学で宇宙に迫ると言うお話。
星間物質の研究だそうです。
星間物質の探索には、電波望遠鏡が非常に重要で、
これまでの電波望遠鏡の何倍もの解像度と感度を持つ
ALMA望遠鏡が出来て、かなり研究が進んだそう。
遠くにある星の回転の向きがわかったと言う事もあるようです。
最近、地球型?惑星の発見が相次ぎ、地球外生命体もいるのでは?
と言うニュースもありますが、坂井博士の意見では、
「そう簡単に、生命体は見つからんよ」と言う事らしい。
いまの人類が居るのも、数多ある進化環境の一つの産物で、
それ以外の進化経路をたどる事も当然ありうるので、
そう簡単に生物は生まれないと言うのが、坂井博士の立場でした。
- 最後の三人目の講演者は、
開拓研究本部 平野染色体ダイナミクス研究室 主任研究員の
平野 達也 博士で、講演タイトルは
『染色体のつくりかた:ゲノムDNAはどのように折りたたまれているのか?』
最初の大熊博士の話は、組織運営の話がメイン、
二人目の坂井博士は、ちょっと難しく、
この三人目の平野博士のお話が、
素人向けに優しく科学を語ったという感じが一番しました。
講演慣れもしているっぽかったし。
今回、はっきりと理解したこととして、
ゲノム=一つの静物が持っている遺伝情報のセット
DNA=遺伝情報を伝えるための糸状の分子
染色体=遺伝情報を伝えるための装置。DNAとタンパク質から形成
と言う事。
ゲノムとか、DNAとか、遺伝子とか、良く聞きますが、
正しく理解していたとは言い難かったので、今回知識が整理できました。
実は平野博士は、遺伝子が、たった3種類のたんぱく質から
作る事を実験的に確かめたと言う凄い人。
講演態度にも余裕があって、本当に講演慣れした感じでしたね。
と言う事で、科学的な知識を高めた、
今日、文化の日でした。