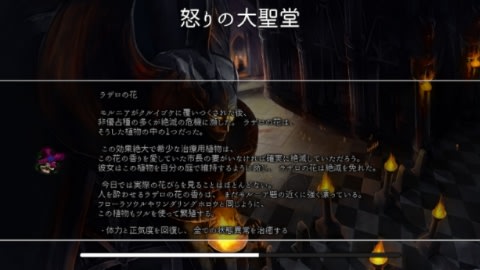落下の解剖学
監督 ジュスティーヌ・トリエ
綿密な芸術。
折り重なる違和感によって導かれるあっという間の2時間30分。一見するとヒューマンサスペンスなのですが、中身は芸術映画。カンヌのパルムドール受賞作。
私や旦那は傑作だと感じましたが、実際は年に1,2本ほど観る人にはオススメできません。なぜなら最初から最後まで全てのシーンに違和感が意図的に、緻密な計算の元に散りばめられているからです。
その違和感は「映画ならフツーは〇〇するよね」という常識を外しているからこそ生まれるもので、それは雑音になります。雑音は、「なにが言いたいのかわからない」だとか、「なにを観せられているのかわからない」といった不快なノイズになります。
この映画はその不快感を意図的に与えてきます。セリフ。音。家の家具の配置。母親と弁護士の関係性。目が不自由なはずの子どもが雪の中の橋を渡る。冒頭のインタビュー。噛み合わないちぐはぐな会話に行動。それどころか映画内のセリフで「真実がどうかは関係ない」と何度も口にするなど全てがバラバラです。終わりでさえも中国人か韓国人が経営してそうな日本料理店で不器用に箸を使って食事をします。
どれもこれもがスッキリしない。映画としてオカシイのです。この違和感が常につきまとうので、観客は不安を抱きながら映画を見続けます。見続けるしかないのです。
けれども映画という虚構とは違って現実はこの【落下の解剖学】の違和感のようにスッキリしないことだらけです。そうした視点で【落下の解剖学】を眺めると、「この映画はサスペンスはなく不合理な芸術映画」だと感じられます。
こうなるとこの映画の虜になります。違和感は印象深いシーンになり、観客の中に残り続けます。映画を否定する違和感が映画を作り、映画を虚構と否定する観客がいつまでも心に残る映画を完成させるのです。こんな素晴らしい映画はありません。
ゆえに傑作だと表現したのです。けれども同時に一般性は大きく下がってしまうので、あまり映画を観ない人にはオススメできないとも表現しました。
評価が割れそうな映画ではありますが、もしかしたらこの【落下の解剖学】が、2024年で最も好きな映画になるかもしれません。そんな素晴らしい映画でした。