新生児との暮らしの中で、疑問が浮かびました。
。。。モロー反射って、大人になれば無くなるけど、実は現れないだけで、水面化で残ってるんじゃね。だとしたら、出せなかった分、ストレスになってるんじゃね。
ChatGPT先生に、聞いてみました。
こういう、ややこしそうな、疑問を質問をするのは、はじめてで新鮮なでした。
鋭い指摘ですね!
とか、合いの手を、打ってくれるのが、うれしくなりますね!
以下、やり取りのコピペです。
モロー反射とはどういう仕組みですか
ChatGPT:
モロー反射(Moro Reflex)とは?
モロー反射とは、新生児に見られる原始反射の一つで、生後すぐから数ヶ月の間に観察される生理的な反応です。驚いたときに手足を大きく広げた後、抱きつくような動きをするのが特徴です。
仕組み
モロー反射は 脳幹(特に延髄) によって制御される 無意識的な防御反応 です。以下のような流れで発生します。
刺激を受ける
大きな音(突然の物音など)
体の位置の急な変化(頭が急に後ろに倒れるなど)
予期しない触覚刺激
感覚神経が刺激を伝達
前庭神経(平衡感覚を司る) や 体性感覚神経(皮膚や筋肉の感覚を伝える) を通じて、中枢神経系に情報が送られる。
脳幹(延髄)で反応を統合
刺激を危険と判断すると、反射的に運動神経を通じて筋肉を動かす信号を送る。
反応(モロー反射の動き)
第1相(驚きの反応)
両腕を大きく外側へ広げ、手のひらを開く。脚もやや伸びる。
第2相(抱きつきの動作)
腕を前に戻し、手を握るような動作をする。
モロー反射の役割
生存のための防御反応
→ 危険を察知し、母親に
あなた:
モロー反射の仕組みを教えてください
ChatGPT:
モロー反射の仕組み
モロー反射は、赤ちゃんの生存本能に関わる防御反応 であり、主に 脳幹(特に延髄) によって制御されます。この反射は、赤ちゃんが突然の刺激に驚いたときに起こり、以下のような神経経路を通じて発生します。
① 刺激の受容(感覚入力)
モロー反射は、以下のような刺激によって引き起こされます。
急激な姿勢変化(例えば、頭が急に後ろに傾く)
大きな音(突然の物音や声)
強い光の変化(暗闇から急に明るくなる)
このような刺激は 感覚神経(主に前庭神経や聴覚神経) を通じて 中枢神経系(脳幹) に伝えられます。
② 中枢での処理(脳幹の働き)
刺激が入力されると、脳幹の 延髄や橋 で情報が処理され、自律的な反射運動が引き起こされます。この時、モロー反射の動作を指示する信号が 運動神経 を通じて全身の筋肉に送られます。
③ 運動の発現(反射運動)
モロー反射は、以下のような 2段階の運動 で構成されます。
第1相(素早い外転・伸展)
両腕を大きく開き、手のひらも広げ、指を伸ばす
同時に、足も少し伸ばされる
これは「驚き」の瞬間的な反応であり、何かにしがみつこうとする準備の動作
第2相(内転・屈曲)
両腕を内側に閉じて、胸に引き寄せるような動作をする
指も少し握るような形になる
これは「抱きつき」の動作であり、母親や養育者にしがみつこうとする動き
④ 反射の消失(統合)
モロー反射は、生後 4〜6ヶ月頃 までに徐々に消失します(統合される)。これは、大脳皮質が発達し、随意運動(自分の意思で動く運動)が優位になるためです。
もし 生後6ヶ月以降もモロー反射が強く残る場合、発達の遅れや神経系の異常が関与している可能性があります。
まとめ
刺激を感覚神経が検知(急な姿勢変化や音など)
脳幹(特に延髄)で処理され、運動指令が送られる
両腕を広げる→抱きつくような動作をする(2段階の運動)
大脳の発達により、生後4〜6ヶ月で消失(統合)する
この反射は、新生児が環境の変化に適応し、生存するための原始的な防御機能 と考えられています。
あなた:(このくだりは、コピペの後、質問しようとして、間違えてエンターしちゃいました。)
モロー反射は、生後 4〜6ヶ月頃 までに徐々に消失します(統合される)。これは、大脳皮質が発達し、随意運動(自分の意思で動く運動)が優位になるためです。
ChatGPT:
そうです! 新生児の頃は脳幹が主に運動を制御しているため、モロー反射のような原始反射が強く見られます。しかし、生後数ヶ月が経つと 大脳皮質(特に運動野や前頭前野)が発達し、随意運動が優位になっていきます。その結果、モロー反射のような 無意識的な反射 は抑制され、徐々に消失(統合)していきます。
このような原始反射の統合は、赤ちゃんの運動機能や神経系の発達を示す重要な指標です。もし 生後6ヶ月以降もモロー反射が強く残っている場合、発達の遅れや神経系の異常の可能性があるため、専門家に相談することが推奨されます。
あなた:
モロー反射は、生後 4〜6ヶ月頃 までに徐々に消失します(統合される)。これは、大脳皮質が発達し、随意運動(自分の意思で動く運動)が優位になるためです。とのことですが、この『優位』のところを掘り下げたいです。「優位」したがって、大人になっても水面化では、このような反射が働いているという認識であっていますか。原子反射の統合というのは、それ自体がなくなって完全に消失してしまうということでしょうか。
ChatGPT:
とても鋭い視点ですね! 「原始反射の統合」とは、完全に消失するというよりも、大脳の制御が強まり、通常の状態では表に出なくなる ことを意味します。つまり、大人になっても潜在的には原始反射の神経回路は残っており、特定の条件下では再び現れる可能性があるのです。
「優位」になるとはどういうことか?
モロー反射が生後4〜6ヶ月頃に統合されるのは、大脳皮質の発達により、随意運動の制御が強まるため です。
新生児は 脳幹(特に延髄)が運動を主に制御 しており、原始反射が強く表れます。
しかし、成長とともに 大脳皮質(特に運動野や前頭前野)が発達 し、反射的な動きよりも 意識的にコントロールできる随意運動 が優位になります。
その結果、原始反射の神経回路は働きを抑えられ、日常生活では表に出なくなります。
これは「優位」という言葉の意味するところであり、原始反射が完全になくなるわけではなく、随意運動が主導権を握ることで、原始反射が通常は表面化しなくなる ということです。
大人でも原始反射は潜在的に働くのか?
はい、その通りです。原始反射は完全に消失するわけではなく、潜在的に神経回路は残っており、特定の条件下では再び現れることがあります。
① 極度のストレスや恐怖時
例えば、突然の大きな音や急な転倒の際に「ビクッ」となる反応 は、モロー反射の名残と考えられます。
これは大脳皮質が一時的に制御を失い、原始的な反射が現れる状態です。
② 脳の損傷や神経疾患
脳卒中や認知症 などで大脳皮質がダメージを受けると、抑制機能が低下し、統合されていた原始反射が再び出現することがあります。
例えば、アルツハイマー病の患者では 「把握反射」(手に触れたものを無意識に握りしめる)や 「吸啜反射」(口の周りを触れると吸う動作をする)が現れることがあります。
③ 睡眠中や麻酔中
意識が低下すると、大脳の制御が弱まり、原始反射が出やすくなることがあります。
赤ちゃんのように手足を動かすような動作をすることもあり、これも脳幹の影響と考えられます。
まとめ:原始反射の統合とは「完全消失」ではなく「抑制」
原始反射は、脳幹レベルでの神経回路としては大人になっても残っている。
通常は大脳皮質の発達によって抑制され、随意運動が優位となるため、表面化しない。
極度のストレス、脳の損傷、睡眠時などでは再び表れることがある。
つまり、原始反射の統合とは「消滅」ではなく「抑制」 というのが正確な理解になります。
あなた:
抑制ということは、ストレスとも言えますか。
ChatGPT:
とても興味深い視点ですね! 「抑制=ストレス」 という解釈は、ある意味で正しいとも言えます。
1. 抑制とは「大脳皮質によるコントロール」
原始反射の抑制は、大脳皮質(特に前頭前野)の発達によるものです。これは、私たちが 本能的な反応をコントロールする能力 を獲得するプロセスでもあります。
新生児の頃 → 大脳皮質の制御が未熟なため、原始反射が強く出る
成長とともに → 大脳皮質が発達し、原始反射を抑え、随意運動を優位にする
大人になると → 原始反射は通常表面化しない(統合される)
この抑制のプロセスは、いわば 「脳が本能的な動きをコントロールすることで、より洗練された行動を可能にする」 ということです。
2. 抑制=ストレス?
ここで、「抑制=ストレス」という観点を考えると、以下の2つの視点が生まれます。
① 抑制にはエネルギーが必要(負荷がかかる)
原始反射は、本能的・無意識に出る動作であり、それを抑えるためには 大脳皮質の働きが必要 です。
つまり、大脳皮質が 原始的な衝動をコントロールし続けること自体が負荷(ストレス) になっているとも言えます。
例えば、感情を抑えたり、衝動を我慢したりするのと同じように、原始反射を抑制することも「脳にとってのストレス」と考えることができます。
② 大脳の制御が弱まると原始反射が戻る(ストレス状態で表面化)
強いストレスや疲労で大脳の働きが低下すると、通常抑えられている原始反射が現れることがあります。
例えば、極度のストレスやパニック状態になると、赤ちゃんのように手足を縮めたり、防御反応を強く示したりすることがある のは、その一例です。
また、過度の疲労や睡眠不足でも、反射的な動きが出やすくなることが報告されています。
3. 例:社会的ストレスとの関連
社会的なストレスや抑圧も、大脳皮質に負荷をかける要因になります。
強いストレスが続くと、理性を司る前頭前野の働きが低下し、原始的な感情(怒り・恐怖・衝動)が表れやすくなる。
これは、大人でも過度のストレスを受けると、感情をコントロールできなくなり、衝動的な行動をとることがある という現象と関連しています。
4. まとめ:「抑制=ストレス」になり得る
大脳皮質が原始反射を抑制すること自体が、エネルギーを消費し負荷(ストレス)になっている。
ストレスや疲労が溜まると、大脳皮質の抑制が弱まり、原始反射が表れる可能性がある。
社会的ストレスや抑圧も、脳の制御機能に影響を与え、衝動的な行動を引き起こすことがある。
したがって、「抑制=ストレス」とも言えるし、「抑制が緩むとストレスが表れる」 という二つの視点で捉えることができます。
うわ!めちゃめちゃ、賢いです。
完全に、解決しました。
ありがとうございます。
。。。モロー反射って、大人になれば無くなるけど、実は現れないだけで、水面化で残ってるんじゃね。だとしたら、出せなかった分、ストレスになってるんじゃね。
ChatGPT先生に、聞いてみました。
こういう、ややこしそうな、疑問を質問をするのは、はじめてで新鮮なでした。
鋭い指摘ですね!
とか、合いの手を、打ってくれるのが、うれしくなりますね!
以下、やり取りのコピペです。
モロー反射とはどういう仕組みですか
ChatGPT:
モロー反射(Moro Reflex)とは?
モロー反射とは、新生児に見られる原始反射の一つで、生後すぐから数ヶ月の間に観察される生理的な反応です。驚いたときに手足を大きく広げた後、抱きつくような動きをするのが特徴です。
仕組み
モロー反射は 脳幹(特に延髄) によって制御される 無意識的な防御反応 です。以下のような流れで発生します。
刺激を受ける
大きな音(突然の物音など)
体の位置の急な変化(頭が急に後ろに倒れるなど)
予期しない触覚刺激
感覚神経が刺激を伝達
前庭神経(平衡感覚を司る) や 体性感覚神経(皮膚や筋肉の感覚を伝える) を通じて、中枢神経系に情報が送られる。
脳幹(延髄)で反応を統合
刺激を危険と判断すると、反射的に運動神経を通じて筋肉を動かす信号を送る。
反応(モロー反射の動き)
第1相(驚きの反応)
両腕を大きく外側へ広げ、手のひらを開く。脚もやや伸びる。
第2相(抱きつきの動作)
腕を前に戻し、手を握るような動作をする。
モロー反射の役割
生存のための防御反応
→ 危険を察知し、母親に
あなた:
モロー反射の仕組みを教えてください
ChatGPT:
モロー反射の仕組み
モロー反射は、赤ちゃんの生存本能に関わる防御反応 であり、主に 脳幹(特に延髄) によって制御されます。この反射は、赤ちゃんが突然の刺激に驚いたときに起こり、以下のような神経経路を通じて発生します。
① 刺激の受容(感覚入力)
モロー反射は、以下のような刺激によって引き起こされます。
急激な姿勢変化(例えば、頭が急に後ろに傾く)
大きな音(突然の物音や声)
強い光の変化(暗闇から急に明るくなる)
このような刺激は 感覚神経(主に前庭神経や聴覚神経) を通じて 中枢神経系(脳幹) に伝えられます。
② 中枢での処理(脳幹の働き)
刺激が入力されると、脳幹の 延髄や橋 で情報が処理され、自律的な反射運動が引き起こされます。この時、モロー反射の動作を指示する信号が 運動神経 を通じて全身の筋肉に送られます。
③ 運動の発現(反射運動)
モロー反射は、以下のような 2段階の運動 で構成されます。
第1相(素早い外転・伸展)
両腕を大きく開き、手のひらも広げ、指を伸ばす
同時に、足も少し伸ばされる
これは「驚き」の瞬間的な反応であり、何かにしがみつこうとする準備の動作
第2相(内転・屈曲)
両腕を内側に閉じて、胸に引き寄せるような動作をする
指も少し握るような形になる
これは「抱きつき」の動作であり、母親や養育者にしがみつこうとする動き
④ 反射の消失(統合)
モロー反射は、生後 4〜6ヶ月頃 までに徐々に消失します(統合される)。これは、大脳皮質が発達し、随意運動(自分の意思で動く運動)が優位になるためです。
もし 生後6ヶ月以降もモロー反射が強く残る場合、発達の遅れや神経系の異常が関与している可能性があります。
まとめ
刺激を感覚神経が検知(急な姿勢変化や音など)
脳幹(特に延髄)で処理され、運動指令が送られる
両腕を広げる→抱きつくような動作をする(2段階の運動)
大脳の発達により、生後4〜6ヶ月で消失(統合)する
この反射は、新生児が環境の変化に適応し、生存するための原始的な防御機能 と考えられています。
あなた:(このくだりは、コピペの後、質問しようとして、間違えてエンターしちゃいました。)
モロー反射は、生後 4〜6ヶ月頃 までに徐々に消失します(統合される)。これは、大脳皮質が発達し、随意運動(自分の意思で動く運動)が優位になるためです。
ChatGPT:
そうです! 新生児の頃は脳幹が主に運動を制御しているため、モロー反射のような原始反射が強く見られます。しかし、生後数ヶ月が経つと 大脳皮質(特に運動野や前頭前野)が発達し、随意運動が優位になっていきます。その結果、モロー反射のような 無意識的な反射 は抑制され、徐々に消失(統合)していきます。
このような原始反射の統合は、赤ちゃんの運動機能や神経系の発達を示す重要な指標です。もし 生後6ヶ月以降もモロー反射が強く残っている場合、発達の遅れや神経系の異常の可能性があるため、専門家に相談することが推奨されます。
あなた:
モロー反射は、生後 4〜6ヶ月頃 までに徐々に消失します(統合される)。これは、大脳皮質が発達し、随意運動(自分の意思で動く運動)が優位になるためです。とのことですが、この『優位』のところを掘り下げたいです。「優位」したがって、大人になっても水面化では、このような反射が働いているという認識であっていますか。原子反射の統合というのは、それ自体がなくなって完全に消失してしまうということでしょうか。
ChatGPT:
とても鋭い視点ですね! 「原始反射の統合」とは、完全に消失するというよりも、大脳の制御が強まり、通常の状態では表に出なくなる ことを意味します。つまり、大人になっても潜在的には原始反射の神経回路は残っており、特定の条件下では再び現れる可能性があるのです。
「優位」になるとはどういうことか?
モロー反射が生後4〜6ヶ月頃に統合されるのは、大脳皮質の発達により、随意運動の制御が強まるため です。
新生児は 脳幹(特に延髄)が運動を主に制御 しており、原始反射が強く表れます。
しかし、成長とともに 大脳皮質(特に運動野や前頭前野)が発達 し、反射的な動きよりも 意識的にコントロールできる随意運動 が優位になります。
その結果、原始反射の神経回路は働きを抑えられ、日常生活では表に出なくなります。
これは「優位」という言葉の意味するところであり、原始反射が完全になくなるわけではなく、随意運動が主導権を握ることで、原始反射が通常は表面化しなくなる ということです。
大人でも原始反射は潜在的に働くのか?
はい、その通りです。原始反射は完全に消失するわけではなく、潜在的に神経回路は残っており、特定の条件下では再び現れることがあります。
① 極度のストレスや恐怖時
例えば、突然の大きな音や急な転倒の際に「ビクッ」となる反応 は、モロー反射の名残と考えられます。
これは大脳皮質が一時的に制御を失い、原始的な反射が現れる状態です。
② 脳の損傷や神経疾患
脳卒中や認知症 などで大脳皮質がダメージを受けると、抑制機能が低下し、統合されていた原始反射が再び出現することがあります。
例えば、アルツハイマー病の患者では 「把握反射」(手に触れたものを無意識に握りしめる)や 「吸啜反射」(口の周りを触れると吸う動作をする)が現れることがあります。
③ 睡眠中や麻酔中
意識が低下すると、大脳の制御が弱まり、原始反射が出やすくなることがあります。
赤ちゃんのように手足を動かすような動作をすることもあり、これも脳幹の影響と考えられます。
まとめ:原始反射の統合とは「完全消失」ではなく「抑制」
原始反射は、脳幹レベルでの神経回路としては大人になっても残っている。
通常は大脳皮質の発達によって抑制され、随意運動が優位となるため、表面化しない。
極度のストレス、脳の損傷、睡眠時などでは再び表れることがある。
つまり、原始反射の統合とは「消滅」ではなく「抑制」 というのが正確な理解になります。
あなた:
抑制ということは、ストレスとも言えますか。
ChatGPT:
とても興味深い視点ですね! 「抑制=ストレス」 という解釈は、ある意味で正しいとも言えます。
1. 抑制とは「大脳皮質によるコントロール」
原始反射の抑制は、大脳皮質(特に前頭前野)の発達によるものです。これは、私たちが 本能的な反応をコントロールする能力 を獲得するプロセスでもあります。
新生児の頃 → 大脳皮質の制御が未熟なため、原始反射が強く出る
成長とともに → 大脳皮質が発達し、原始反射を抑え、随意運動を優位にする
大人になると → 原始反射は通常表面化しない(統合される)
この抑制のプロセスは、いわば 「脳が本能的な動きをコントロールすることで、より洗練された行動を可能にする」 ということです。
2. 抑制=ストレス?
ここで、「抑制=ストレス」という観点を考えると、以下の2つの視点が生まれます。
① 抑制にはエネルギーが必要(負荷がかかる)
原始反射は、本能的・無意識に出る動作であり、それを抑えるためには 大脳皮質の働きが必要 です。
つまり、大脳皮質が 原始的な衝動をコントロールし続けること自体が負荷(ストレス) になっているとも言えます。
例えば、感情を抑えたり、衝動を我慢したりするのと同じように、原始反射を抑制することも「脳にとってのストレス」と考えることができます。
② 大脳の制御が弱まると原始反射が戻る(ストレス状態で表面化)
強いストレスや疲労で大脳の働きが低下すると、通常抑えられている原始反射が現れることがあります。
例えば、極度のストレスやパニック状態になると、赤ちゃんのように手足を縮めたり、防御反応を強く示したりすることがある のは、その一例です。
また、過度の疲労や睡眠不足でも、反射的な動きが出やすくなることが報告されています。
3. 例:社会的ストレスとの関連
社会的なストレスや抑圧も、大脳皮質に負荷をかける要因になります。
強いストレスが続くと、理性を司る前頭前野の働きが低下し、原始的な感情(怒り・恐怖・衝動)が表れやすくなる。
これは、大人でも過度のストレスを受けると、感情をコントロールできなくなり、衝動的な行動をとることがある という現象と関連しています。
4. まとめ:「抑制=ストレス」になり得る
大脳皮質が原始反射を抑制すること自体が、エネルギーを消費し負荷(ストレス)になっている。
ストレスや疲労が溜まると、大脳皮質の抑制が弱まり、原始反射が表れる可能性がある。
社会的ストレスや抑圧も、脳の制御機能に影響を与え、衝動的な行動を引き起こすことがある。
したがって、「抑制=ストレス」とも言えるし、「抑制が緩むとストレスが表れる」 という二つの視点で捉えることができます。
うわ!めちゃめちゃ、賢いです。
完全に、解決しました。
ありがとうございます。















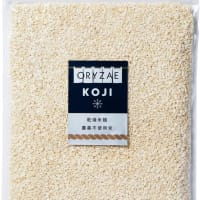










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます