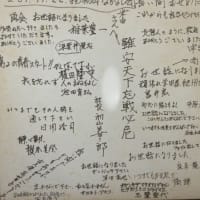これが秋晴れです。
久しぶりに心地よい朝を迎えました。
出社途中、
昨晩の満天に輝いていたお月さんは、快晴の西の空の下で薄く見えていました。
さて、合板の話しに戻ります。飛び飛びに成りました事お詫びを申し上げます。
例えば体力壁の面材にダイライトと言う建材が有ります。
これは火山灰が原材料で無機質です。
仮に湿気を帯びてもその物が大きく変化する訳でも有りませんし、
そして火山灰ですから水分は直ぐに放出される性質を持っています。
湿気を逃がす為、結露がし難いのですね。
このダイライト9mm厚さで透湿抵抗値が2.30【単位は省略します】
同じく壁震火【カベシンカ)と言う商品名の面材が有ります。
これの透湿抵抗値は2.34と成っています。
これも抵抗値の数値がダイライトと同じ程度ですから、結露が起し難い面材と成ります。
ところが合板は同じ厚さでも抵抗値が16.9も有ります。
16.9÷2.34=7.22 約7倍も抵抗値が高いのですね。
よって科学的にも合板は湿気が逃げない事が解ります。
だから、合板を壁の面材に使った場合は
壁内部で結露を引き起こし易く、又、雨水等が侵入し湿気ても外部に放出し難い、
水分が壁内部に滞留し、それが元に成って他の木材を腐らす一因となるのですね。
ちなみに杉の板9mm厚さでは抵抗値が4.7と成っています。
あさひホームが創業から屋根下地には合板を用いずに杉の板を用いている事が
解って頂けたのでは無いでしょうか。
【数値は財団法人建築環境・省エネルギー機構発行の省エネ基準解説書より】
科学的な面からも合板は
面材等に使わない方が良い事がお解り頂けたのでは無いでしょうか。
ただし、
新築時においては合板のその強度は認められます。
それで長期優良住宅等においても屋根下地や壁の面材に用いられています。
しかし、使うので有れば細心の注意が必要です。
私個人的は合板を多用した長期優良住宅は、
その施工現場を見てその耐久性に疑問を持っています。
今日まで建築されている合板に囲まれた住まいは
【プレハブ住宅や2×4工法等に代表されますが、合板を外周部に多用した住まい】
経年変化が激しく劣化が早いのをこれでご理解して頂けると思います。
【施工不良もからんでと推測しますが、合板の特性でしょう】
屋根裏、壁の中、軒の裏側を機会が有れば見て下さい。
更に、
合板を面材として用い、断熱材に「グラスウールやロックウール」での
充填工法【内断熱施工】は施工者にとっては楽でコストも下がりますが、
住まいの大敵の結露が問題として残っているのです。
この断熱・気密施工が正しく行われないと最悪の住まいが建築されます。
最後に
住まい造りは「一生で一度有るかの大事業」ですね。
そして大金をかけるのです。
「創り手に全てを任せる」のでは無くて、ご自身も勉強をする事が
大切とお解り頂けたのでは有りませんか?
あさひホームでは
住まい造りの勉強会や完成見学会を兼ねての住まい造りの勉強会を行っています。
本日も小松市上寺町で開催しています。
お気軽にご参加して下さい。
余談に成ります。
前日お引き渡しを致しましたお客様宅に妻が御礼の挨拶に出向いたところ、
「あんた所の職人さん、挨拶はきちんと出来て本当に気持ちよかった」との
お言葉を頂いたとスッタッフに伝えている所を小耳に挟んだのですが・・・・・
本当に嬉しい限りです。
自慢に成りましたが、
住まいは工場生産では有りません、人が現場で造りのですね。
9時から地鎮祭です。
地鎮祭には最高の日和に成りましたが、休日ですね。
行楽等にお出かけの方も多いと思いますが、
くれぐれも交通事故などに注意をしてお出かけ下さい。