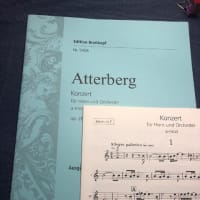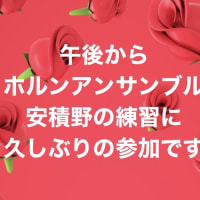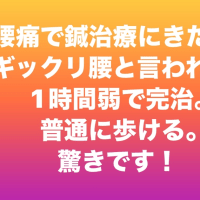興味ありませんか??
実はそれをご紹介しようと思います。
ホルンふきの方は、当たり前すぎて退屈かもね。
それでは変換器の説明です。
私が知る限り、多くのホルン吹きは、おそらくですが…こんな変換システムでしょう…。。
(まぁ、中には実音と指使いとを一対一に対応させて覚えている方もいるようですけど…。)
まず、前提として、かならず、譜面の出だし付近、もしくは冒頭には調の指定があります。
ホルンは、もともとヘ長調(F)が基本ですから、in F とあればそのまま吹きます。
(記譜上の「ド」は、そのまま「ド」の音で吹きます。(実音でF、つまりピアノの「ファ」ですけどね))
それでは、入門編
読み替えでいちばんやさしいのは、in Es です(変ホ長調)。
この場合の変換器内部はこうです。
機械的に「一つ音を下げて、譜面には♭を2つ追加」です。
たとえば、「レ」なら「ド」の音に読み替えます。
「ド」なら「シ♭」となります。
♭2つとは、一つ下げた時に「ミ」または「シ」だったら、♭をつけるという意味です。
次にin G の場合です。
これはinEs と、全くこの逆になります。
「一つ音を上げて、譜面には♯を2つ追加」です。
「シ」なら「ド♯」に変換します。
もちろん「ド」は「レ」です。
さて、ここまでは理解できたでしょうか。
次は中級です。。
その上のin A は…というと、
五線紙の中を棚に例えると…棚の中の音符(おだんご、でもいいですけど…)
「一つ上の棚へ移します。串なら、一串分上げます。」…そんな感じです。
もっと簡単に言うと、in A は、「一段上げて、譜面には♯5つ追加」となります。
つまり一段上げたときに、「ファ」「ソ」「ラ」「ド」「レ」の段、もしくは串には、すべて♯をつけるということを意味します。
このあたりは、ちょっと慣れないと厳しいですね。
どうも感覚的に下げる方がまだ楽なような気がします。
今度は一段下げるほうです。
in D は…「一段下げて、譜面には♯を3つ追加」です。
譜面上の「ド」は一段落として「ラ」と読み替えます。
「ラ」は、「ファ♯」となります。
まぁ。この辺りまでは、視覚的に上げ下げして対応しています。
ちょっと書き忘れたので補足しますが、今まで書き替え幅の範囲で、
私が最も吹きにくいのは、実はin F の半音下のin E です。
ぜ~んぶ、半音下げて吹くのです。
やさしいのか、難しいのか人によって意見は分かれるところです。(続きは次回)
最新の画像もっと見る
最近の「ホルンあれこれ」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2012年
人気記事