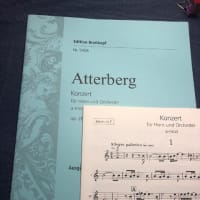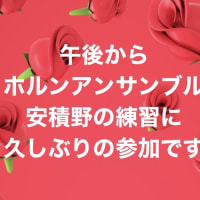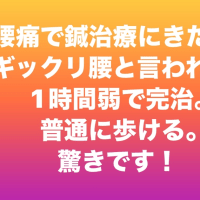これ以上になると、記譜上の「ド」が、実音で何の音になるかを確認して、
そこを起点にして読替えたほうが早くなります。
たとえば、冒頭でも触れましたが、inC なら記譜上の「ド」は「ソ」にあたります。
(つまり、ホルンはヘ長調なので、実音(inC)の「ド」が、Fホルンでは「ソ」になるということです)
そう考えて、あとは♭1つ追加ですね。
inB♭なら記譜上の「ド」が「ファ」という具合です。
今度は#1つ追加です。
ただし、おかしいのは、ダブルホルンを使っている方は、
ほとんど、B♭管(ベー管)で吹いていますので…
inB♭だったら、そのまま(なにも移調せずに)吹けばよいと思うかもしれませんが…
でも…これがなかなか出来ないのです。
混乱してしまうのです。
B♭管でも、F管の指使いで覚えているからなのです。
頭の中では、「B♭→ F → B♭」っという、まどろっこしいことをやらないと…
どうも…納得しないようです。
急ぎ足で説明しましたが、非常に大まかでしたが、何となく雰囲気はお分かりいただけたでしょうか?
まぁ、ここに補足するのであれば、もともと記譜に#や♭があった場合ですね。
#1つが+1。
♭1つが-1と数えて…
その合計で決まります。
たとえば、inCでもともと記譜に最初から#1ついていたら、(♭1つ追加するので)結局、+-ゼロというわけです。
#や♭が付かないということです。
これで、やっと変換器のお話は99%終わりました。
でも、なんで、こんなテーマを取り上げたかというと、
実は…ブラ2(ブラームス交響曲第2番)の2楽章の、「In H(はぁ~)」。
この…ほとんどお目にかかれない移調の話をしたかったからなのです。
上級編です。(次回に続く)
最新の画像もっと見る
最近の「ホルンあれこれ」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2012年
人気記事