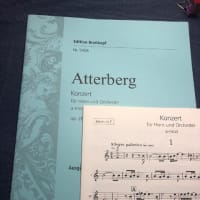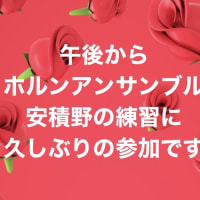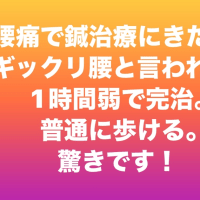最初は、理由など考える暇もなく、指使いを習いました。
わけもなく、教則本に書かれているままに…
ド 0
レ 1
ミ 0
ファ 1
ソ 0
そのうちに、1番を押すと1音分ほど管を長く(余分に)通るので全音低くなることを覚えました。
(-1.0音)
だから、例えば解放で(= 0 )「ソ」を吹いて、そのままで人指し指(1)を押すと1音分下がって、
「ファ」になるのでした。
なるほど納得でしたね。(「ミ」と「レ」も同様です)
ついでに言うと、2番を押すと、半音低く。(-0.5音)
3番なら、1.5音分長くなるので1音と半分下がります。。。(-1.5音)
ということは、1+2(人さし指と中指を同時に押した場合)と、薬指を単独で押した場合(3)は、同じ管の長さになりますから
ここで替え指が成立します。
ですから、「ミ」の音が 、1+2 (-1.0 + -0.5 = -1.5)もしくは 3(-1.5) のいずれかでも
管の長さが同じなのです…替え指が成立すると説明できます。
さて、せっかくですから、音階の「ソ」から上の指使いも、同様の考えで予測してみましょう。
一般的な指運表は…
ラ 1+2
シ 2
ド 0
…となります。
ここで上のドを起点にして、そこから2の指で半音下げたのが「シ」のはずです。
「シ」(2)から、1音低いのが「ラ」ですから、人指し指を加えて 1+2としたのが、当然「ラ」になるはずです。
そうです。その通りになります。(この考えを利用すれば、半音階の指使いも探し当てられます。)
蛇足になりますが、当然、薬指(3)でも(1+2と同様に)「ラ」になります。
(ただし、楽器構造(巻)の関係もありますが、一般には、1+2の方が、3より音程が高めになることを覚えておいたほうが良いでしょう。)
ここまでの説明で、ただ意味もなく指運表を丸暗記するよりも、
余分な管を足すことで(すなわち回り道して、管を長くして)音程を半音とか1音下げる…と考えた方が、
より論理的で指も覚えやすいことがお分かりいだけけると思います。
ですが、、初心者はいざ知らず、実はこれだけでは不十分なのです。
「ミ」の音が 1+2 もしくは 3 で出せることは説明できても、
「ミ」の音が…開放の0 でも 1+2 でも出ることの説明はつきませんしね。
そうなのです。。
ロータリーバルブを押さえることで、ホルンの管自体が、F管から変化していることを認識しないとダメなのです。
私がこれを意識したのは社会人になってからかもしれません。
調性を意識しだした頃です。例えば交響曲○短調とか、△長調とか、、
これを意識すると指使いが楽になります。
しかも、替え指の本質を知る上でも、ナチュラルな発想は有用と思いますよ。
次回はそのあたりの話です。
まずは替え指の謎解きからですね。
(^_^)☆
最新の画像もっと見る
最近の「ホルンあれこれ」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2012年
人気記事