=ウーリー・ステック(スイス)=

最強の能力は集中力
フランスのシャモニー ( Chamonix ) の近くにそびえる巨峰グランド・ジョラス( Grand Jorasses ) の北壁をシュテック氏は2時間21分という猛烈な速さで登り終えた。
現在33歳のシュテック氏は、ベルン州のなだらかに起伏するエメンタール村( Emmental ) の出身だ。あらゆる登山スタイルの中で最も危険といわれるフリー・ソロで世界トップレベルの1人に数えられている。 シュテック氏は、これまでロープや落下防止用のギアを使わずに危険なルートに度々アタックしてきた。 たった1回のミスは恐ろしい死を意味しかねない。
「彼が持っている最強の能力は集中力です。あの水準のクライミングをするには彼のような集中力が必要なのです」
とシュテック氏の友人で10年来のクライミング・パートナーでもあるシュテファン・ジグリスト氏は語っている。
人道主義的な標高
空高くそびえる崖の壁にしがみつきながら登山をしたことのない人にとって、シュテック氏の水準がどんなに高いか正確に理解するのは難しいだろう。 彼のレベルのクライミングでは、強靭さ、持久力そして精神力の鋭さが試される。 同様のことができるのは、世界最高レベルのクライマーのうちほんの一握りだけだというほどその難易度は高い。
シュテック氏のクライミングの才能は天性のものだが、彼はトレーニングを規則正しく行っている。オリンピック選手についているトレーナーのもとでのトレーニングを絶対に欠かさない。 その結果、彼は指先を使った片手懸垂やランニングを準備運動なしに3時間も行うことができる。 崖の上では、文字通り顔が白くなるまで、氷で覆われたむき出しで急勾配の道筋をかき分けながら進む。
4月にシュテック氏はシモン・アンターマッテン氏と共に、ネパールの6500メートルのテンカムポック峯 ( Tengkampoche ) の北壁登頂に成功した。 この山は「黄金のピッケル ( Piolets d’Or ) 」と呼ばれる登山家にとっての聖地の1つで、2人はその厳しい北壁を大胆にも新しいルートを開拓しながら登攀に成功した。
さらに2人は昨年、雪深いアンナプルナ連峰 ( Annapurna ) で、自分たちの登攀を途中で中止し、瀕死の遭難者を救出したことで有名になった。
「トップレベルのクライマーが自分のことだけに完全に没頭するのはよくあることです。彼らのようにトップレベルの先端にいる人間がほかの人を助ける心構えがあるということが分かってうれしく思います」
と過去に両足を電車事故で失ったものの、8000メートルのアンナプルナの登頂に成功したイギリス人登山家ノーマン・クロウチャー氏は4月に2人の勇気を称えているのです。

シュテック氏の登攀記録
・アイガー北壁、ヘックマイアー・ルート2時間47分 33秒 ( 2008年2月13日 )
・グランド・ジョラス北壁、マッキンタイア・ルート2時間21分 ( 2008年12月28日)
・マッターホルン北壁、シュミッド・ルート1時間56分 ( 2009年1月13日)

・・・・ アイガー悲劇の記憶(アイガー・バンド事故小史)
今から50年前、アイガー登山史上初めての救助活動が世界の注目を浴びた。北壁で遭難した4人のうち、生還したのはクラウディオ・コルティ隊員1人だけだった。
『コルティのドラマ ( Corti-Drama ) 』と題された本が、このほどスイスで発行された。当時の救助活動の詳細や、報道機関による生還者コルティの責任追及と彼の名誉回復までを追った。
事故が起こった1957年当時、グリンデルヴァルトからクライネシャイデック ( Kleine Scheidegg )まで の模様は双眼鏡で見ることができた。イタリア人のコルティとステファノ・ロンギ登山隊がアイガー北壁を登っている様子は、双眼鏡を通して観察されていたのである。イタリア隊が出発した2日後、ドイツ隊のギュンター・ノートドゥルフトとフランツ・マイヤーも同じルートを登り始めた。
≪救助後も注目が続く≫
2隊ともなかなか前進できない。そうこうしているうちに、北壁を登る途中でイタリア隊はにっちもさっちもいかなくなってしまったのである。1日後、6カ国からなる救助隊が、コルティ隊員を山頂から320メートルのザイルを垂らして救助することに成功した。しかしロンギ隊員は、寒さとひもじさで死亡した。
ロンギ隊員の遺体はザイルに釣り下がったまま、回収されたのは事故の2年後のことである。その2年間、野次馬の興味の対象となったことはいうまでもない。グリンデルヴァルトにとって不名誉なことだが、現地の人々は冷静に受け止めていた。遺体を回収するために山に登ることは不可能だと判断されていたからである。
ドイツ隊のロートドゥルフトとマイヤー両隊員の行方は分からず仕舞いで、憶測が飛んだ。中にはコルティの責任を問うものもあった。コルティは自分が助かりたいがため、2人のドイツ人を墜落させたのだというのだ。4年後、行方不明だった2人は遺体で発見された。その結果、2人は頂上に到着し、その後の下山で疲労のため死亡したということが分かった。コルティはやっと「無実」を認められ、名誉を回復したのだった。

苦い思い出
事故から50年目にあたる今年、スイス人のダニエル・アンカー氏とドイツ人のライナー・レットナー氏による本が出版された。イタリアに暮らすコルティを訪ねるなど、著者は当時の模様を知る証言者に聞き歩いた。救助活動の模様などを詳細にわたって記録したカメラマン、アルベルト・ヴィンクラーの写真も入手した。ヴィンクラーの報道写真は当時、マスコミにより世界中に流されたものである。
「当時子どもだった人も、登山隊員をどのように救助しようとしたか、詳しく覚えている」と著者のダニエル・アンカー氏。遭難事故は現地の人の脳裏にいまでも鮮明に残っているのだ。
さらにアンカー氏によると、グリンデルヴァルトの村にとって「コルティのドラマ」は苦い思い出だという。3人を救助できなかった上に、当初は救助活動を拒否したからである。「技術面でも機材面でも、その準備はなかった。スチールザイルによる救助方法は当時まだ知られていなかった。また、アイガー登山はグリンデルヴァルトの村人にとってタブーでもあった。事故を起こすのは登った人が悪いからだという考えだったのだ」
≪報道合戦≫
この救助活動は世界のマスコミの注目を浴びた。現地の人たち以外は、救助は可能だと考えていた。「登山家はどれだけ耐えられるのだろうかということに興味が集中した。しかも、夏でニュースがさほどなかったことも報道合戦に拍車をかけた」。もしテレビが当時あったなら、必ず中継されたはずだとアンカー氏は言う。
同時に、この遭難事故によりグリンデルヴァルトは観光面で大いに儲かったことも否めない。もちろん、彼の救助が失敗したことは現地の人々にとって辛いことだったろうとアンカー氏は言う。
2年後、ロンギ隊員の遺体回収は、オランダの出版社が出資して実現した。出資者は、ほかのリコプターなどを飛ばすことを禁止し、回収の模様を独占しようとしたが、それはかなわなかった。
≪ハイキングの気持ちで上るのは危険≫
その後、救助技術は大きく進歩した。特に現在のグリンデルヴァルトの救助活動は評価が高い。夜間に起こった遭難事故でも、厳しい状況下の救助活動もヘリコプターのおかげで可能だ。しかし、今日のハイテク技術で登山者の危険が無くなったかというと、それは間違いだ。携帯電話で救助を呼ぶことも考えられるが、バッテリーがなくなっていたり、天候によって電話が通じなかったりもする」とアンカー氏は警告する。
アイガー北壁はすでに何百もの登山隊が登ったとはいえ、その魅力は消えていない。グリンデルヴァルトを訪れる観光客にとっては、一種の舞台ともいえる。登山隊員の様子を、グリンデルヴァルトから見ることができるからだ。また、登山者にとっても魅力ある場所だ。牧草地から1800メートル上ったところにあるにもかかわらず、電車が通る音やカウベルが聞こえる、特別な場所なのだ。

北壁の登頂歴;
- 1934年、ドイツのW・ベックとG・レーヴィンガーが史上初のアイガー北壁挑戦を試みるも、標高2,900m付近から滑落して死亡。
- 1935年8月21日、マックス・ゼドゥルマイヤーとカール・メーリンガーが北壁に挑んだが、第3雪田の上の標高3,300m付近で凍死する。それ以降、この場所は「死のビバーク」と呼ばれるようになった。
- 1936年7月18日、ドイツのアンドレアス・ヒンターシュトイサーとトニー・クルツ、オーストリアのエディー・ライナーとヴィリー・アンゲラーの2隊が競いながら登頂を目指し、ヒンターシュトイサーが第1雪田の下の難しいトラバース(ヒンターシュトイサー・トラバース)に成功、さらに「死のビバーク」を越える位置まで登攀する。しかしアンゲラーが負傷したことから2隊は助け合いながら下山することを決定、天候の悪化からビバークを余儀なくされる。7月21日、ザイルを回収してしまったことが仇となって退却できず、何とか脱出を試みるも、クルツを除く3人が墜落などで相次いで死亡。クルツも救助隊の元にザイルで下りる際にカラビナにザイルの結び目が引っかかるという悲劇に見舞われ、体力を消耗し切っていたために結び目を外すことが出来ず、ザイルにぶら下がったまま、7月22日、「もうダメだ」の一言を残して力尽きる。救助隊のわずか数メートル上であった。この事件により、ベルン州の州議会は北壁の登攀を禁止する決議を採択する(翌年、条件付きで緩和)。
- 1938年7月24日、アンデレル・ヘックマイヤー、ルートヴィヒ・フェルク(ドイツ人隊) ハインリッヒ・ハラー 、フリッツ・カスパレク(オーストリア人隊)がアイガー北壁初登頂。両隊は登頂開始時は別々のパーティだったが、後から登頂に挑んだドイツ人隊がオーストリア隊に追いついた時点で同一パーティを組み、初登頂に成功した。
- 1963年、芳野満彦、渡部恒明らが、日本人として初めてアイガー北壁に挑む。渡部が100m付近から墜落したが、深雪の上に落ちたため九死に一生を得る。
- 1965年8月16日、高田光政が日本人初登頂。登頂まであと300mというところで、パートナーの渡部恒明が墜落・負傷したため救助を求めるために山頂を経由した際に達成。しかし渡部はその間に謎の墜死を遂げた。一説には骨折の痛みと孤独に耐えきれずに自らザイルを解いたとも言われている。これをもとに新田次郎は「アイガー北壁」という小説を書いている。
- 1969年7月、辰野勇が、日本人としては二人目となる北壁登頂に成功。当時の世界最年少記録(21歳)。
- 1969年8月15日、加藤滝男、今井通子、加藤保男、根岸知、天野博文、久保進の6人が、夏期世界初直登。冬期直登ルートが夏場は通れないため、「赤い壁」を経由。現在でも最短直登ルートとして名が残っている。加藤滝男が山頂直下でザイル無しで墜落したが、運良く固定ザイルに引っかかって九死に一生を得た。
- 1970年1月27日、森田勝、岡部勝、羽鳥祐治、小宮山哲夫の4人が、冬季日本人初登頂。
- 1970年3月21日、遠藤二郎、星野隆男、小川信之、三羽勝、嶋村幸男、高久幸雄、深田良一の7人が、冬季直登日本人初登頂。
- 1977年3月9日、長谷川恒男が冬季単独初登頂。ヨーロッパのみならず、世界中の登山家を驚愕させた。
- 2008年2月13日、ウーリー・ステックが2時間47分33秒で登頂し、自らが持つ冬期単独登頂の最短記録を更新。

【 We are the WORLD 】
https://www.youtube.com/tv?vq=medium#/watch?v=OoDY8ce_3zk&mode=transport
【 Sting Eenglishman in New_ York 】
http://www.youtube.com/watch?v=d27gTrPPAyk
【 DEATH VALLEY DREAMLAPSE 2 】
※上記をクリック賜れば動画・ミュージックが楽しめます
----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------
【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com
【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/
【壺公栴檀;ニュース・情報】http://blogs.yahoo.co.jp/bothukemon
【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/
・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・
森のなかえ
================================================













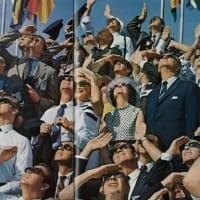



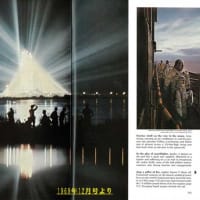
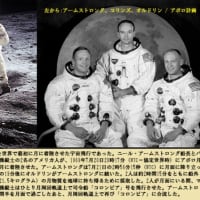
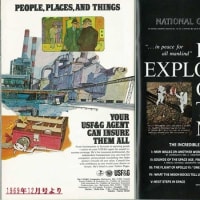
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます