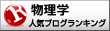例の有名な思考実験、地面に対して速度vで疾走する特急列車のヘッドライトから出る光の速さはcなのかc+vなのか?
1)答えはもちろん光速度一定原理によりcだが、それだけでなくドップラー効果の公式で考えたら観測者は地面に静止しているので、すなわち媒質にとって静止しており光速度はcのまま一定です。
2)話はそれだけではない、光が粒子だとすると光速度は列車の速度vが加算されてc+vであり、光が波動だとしたら列車は媒質に対して速度vで前方に動いているので光速度は列車の速度vが引き算されてc-vとなる。
3)2)から平均を考えると両者の相加平均がcであり、相乗平均がローレンツ係数だ。
ということは相対論こそ光の粒子性と波動性の中間によって成立している自然だと言えるのだろうか?
1)答えはもちろん光速度一定原理によりcだが、それだけでなくドップラー効果の公式で考えたら観測者は地面に静止しているので、すなわち媒質にとって静止しており光速度はcのまま一定です。
2)話はそれだけではない、光が粒子だとすると光速度は列車の速度vが加算されてc+vであり、光が波動だとしたら列車は媒質に対して速度vで前方に動いているので光速度は列車の速度vが引き算されてc-vとなる。
3)2)から平均を考えると両者の相加平均がcであり、相乗平均がローレンツ係数だ。
ということは相対論こそ光の粒子性と波動性の中間によって成立している自然だと言えるのだろうか?