 |
ヨーロッパ退屈日記 新潮社 このアイテムの詳細を見る |
伊丹十三さんの「ヨーロッパ退屈日記」(新潮社)に次のような記事が載っていた。
「(英国の)タクシーの運転手になるには、一年間の見習い期間があり、その間は無給で、自転車に乗り、指導員に従って、ロンドンのあらゆる地理と、二点間の最短距離を覚えるのに費やされる」
これは1960年代の話だから、現在も続いているかはわからない。だが、伝統を重んじる社会であるから、この慣わしが残っていても可笑しくないだろう。
イギリスのガイドブックを見れば、タクシーの乗り方として「住所を言えば、目的地までピタリと運んでくれる」といった説明が載っていたように思う。少なくとも「足りない経験をカーナビで解決!」というような安易な思考回路は相手にされないのではないだろうか?それがお金をいただくプロフェッショナルとしての心意気である。
彼らはプロフェッショナルであるから、素人が真似をしようと思ったところで、歴然とした品質の差が出るのは当然である。どちらを選ぶかは、利用する市民の気位の高さかと思うが、誰がやっても変わらないような薄っぺらい仕事というのは、社会的地位が低下するばかりか、雇用者にとっても、雇用主にとっても、そして利用者にとっても、長期的にはあまり幸福な結果にならないのではないだろうか?
これはタクシーに限った話ではなく、いかなる仕事も同じことが言えると思う。誰にもできそうな任務だからこそ、何を差別化してどのようにアプローチするのか、経営者も従業員もそれぞれが考え、経験を積まなければならない。人材育成への投資や蓄積があって初めて、市場で評価され、適切な料金を回収できるはずである。
ここまで読んで気付いた方もいると思うが、これすなわち日本人の得意とする「日本型経営」そのもので、なんら新しいことではない。多くの企業では忘れ去られたが、日本人のカイゼンの遺伝子は、多くの人に残っていると信じたい。
余談ながら同書には、次のような記載もある。
「ロンドン市内でUターンが許可されているのはタクシーだけで、そのため、タクシーに使う車は回転半径が非常に小さく設計されています」
当然ながら、ハード面の差別化ももちろん必要である。
また、韓国では高級タクシーと普通のタクシーと二種類あって、普通のタクシーはお客さんを運んでいる最中に、他の客まで拾ってしまうという、ホンマかいなと思う荒業が習慣らしい。ただ、これは支払い分担のトラブルさえ無くせば、環境には非常にいいと思う。
伊丹十三のエッセイ
http://www.shinchosha.co.jp/kangaeruhito/high/high08.html














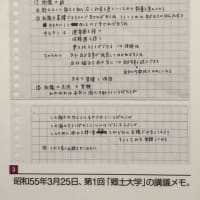

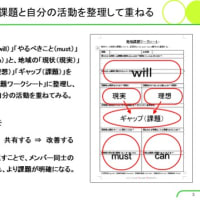
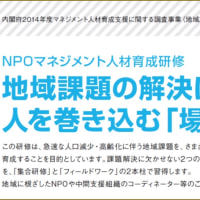
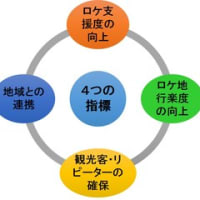








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます