
図はPLL(フェーズ ロックド ループ)による「FM復調」の原理を示しています。オペアンプを理解していれば一目瞭然ですね。
VCO(Voltage Controlled Oscillator)は「V/Fコンバータ」であり、入力電圧に比例して出力周波数が変化します。よってVCOの出力は入力信号の周波数と位相が一致し(同一波形であり)、VCOの入力(オペアンプの出力)が復調された信号波形になります。
すなわちこれもオペアンプの核心部。ネガティブフィードバックする限り必ずプラス入力端とマイナス入力端の値は一致するということです。もしVCOの代わりに抵抗を取り付けたら、プラス入力端、マイナス入力端、オペアンプの出力の3か所の波形がすべて同じになりますね。
関連記事:オペアンプとは何か? 2007-09-02
VCO(Voltage Controlled Oscillator)は「V/Fコンバータ」であり、入力電圧に比例して出力周波数が変化します。よってVCOの出力は入力信号の周波数と位相が一致し(同一波形であり)、VCOの入力(オペアンプの出力)が復調された信号波形になります。
すなわちこれもオペアンプの核心部。ネガティブフィードバックする限り必ずプラス入力端とマイナス入力端の値は一致するということです。もしVCOの代わりに抵抗を取り付けたら、プラス入力端、マイナス入力端、オペアンプの出力の3か所の波形がすべて同じになりますね。
関連記事:オペアンプとは何か? 2007-09-02
















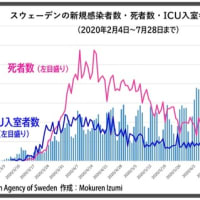









この分野はあまり興味を示す人がいないのかな?
身の回りはPLLだらけなのになぁ~?
ラジオだろうと地デジだろうと「チューナー部」のローカルOSCはみんなPLL制御してるし・・・。
とてもメンドくさかったのは、昔の仕事でスーパーインポーズのクロスカラーを解決するのにPLLでGenLockをかけてやろうと、東芝のTC5018でやっきになって実験してたっけ!
結局はPLLにしないで、緻密な4FSC(14.31818MHz)の調整にしたのです。トリマコンデンサだけで済むので、コストがとても安くつきました・・・。でも、不満でしたけどねぇ~!
まぁ、昔のことなんで、フィルタはもろアナログ!CとRでラグリードでした。今じゃ通用しない話ですけどねぇ~!
今や当たり前となっているPLL、つきつめてみませんか?
でも、誰も興味もたんかなぁ~?
PLLについては、私はいままでほとんど接する機会がなく、FM変調を復調するときに使うものだろうと、漠然と思ってきた次第です。そもそも高周波の経験が今までほとんどありませんでした。
ところが最近、XR2211というFSKデモジュレタICを使用している機器に接する機会があり、見事にFM復調している様子を見て感心してしまいました。
で、いったいどうやって復調してるんだろうと布団の中で考えながら、ふと思いついたのが添付のブロック図です。「なんだ、簡単じゃないか」てな感じでね。
(^^)
何か変ですかねえ...?
いや、そういうモンなんです。
デジタルだろうとアナログだろうと「変調」の定義が意味するところは同じなのです。ただ、それに気づいてしまった・・・それだけのことなんですよ!
アナログ信号を三角波で変調・・・いやいや間違い!三角歯・・・じゃなくて三角波をキャリアにしてアナログ信号を載せるとどうなるか?
PWMになぁ~るじゃあ~りませんか!
ってな感じですかね?
実際には「変調」っていうほど大袈裟な話ではなく、コンパレータの入力が三角波と入力信号というただそれだけの話です。
でも、これはPLLとは直接関係ない話・・・でした。
「三角波をキャリアにしてアナログ信号を載せるとどうなるか?PWMになぁ~るじゃあ~りませんか!」
なるほどお、そうですよね。こういうシンプルな話ほど奥が深くておもしろいですね。分かっているようで実は分かっていないことも多いです。
kaoaruさんのサイトにも何度かお邪魔して、その膨大な情報量に圧倒されてしまいました。興味深い話がてんこ盛りですね。コメントを残そうとも思ったのですが、要領が分からず諦めました。
ともあれ、今後ともよろしくお願いします。m(_ _)m
見てましたかぁ~、いやいや・・・これはどうも・・・。逆に恐縮してしまいます。
私のところはブログでもないし、そういう仕掛けを作っていません。ただのメモです。
でも、いろんなことに「興味を示せる」のはいいですよね!
しかし広大なネット上の情報はむしろ毒リンゴの方が多いかも知れませんね。その中からキラリと光る宝物を見分けるのは、かなりのスキルが必要ですね。
私のブログのすべての記事もただのメモですよ。備忘録のようなものです。と言っても、昔の記事は自分で書いておきながら、いま読み返すとすぐには理解できないものや、大嘘を書いてたりするものもありますね。だから突っ込んでくださる方は大歓迎です。
(^^)
歳と共に「興味」や「感受性」が薄れていくのは仕方がありませんが、願わくば大切にし続けたいですね。
kaoaruさん含め,議論を深めませんか?
比較対象を分周するかどうかでも違ってきますし、弁別にアナログ・ラグリードフィルタ方式とかデジタルか?ってことでも違うし・・・。
まぁ、もっとも、今はDSPで処理しちゃうのが最先端ですけどね!
廉価版のPLL方式ラジオなら分周方式です。AMの9kHzステップというのはそこから決めたものですし・・・。
そして、そういう専用のマイコンが存在するところもその意味合いですが、そういうことにとらわれてしまうと自由な発想ができなくなる、そういうモノですしね・・・。
PLLについては私はほんとに無知なのですが、そもそもFM変調が周波数変調(FSK)であることは一般によく知られていますよね。で、周波数変調された信号をどうやれば復調できるのかと考え始めたのがきっかけです。そしてkaoaruさんにもお話しましたが、ふと思いついたのかこの記事に添付している図です。「なんだ簡単じゃないか」とね。VCOがキーワードであることも知ってはいました。
しかし実際には簡単ではなくオペアンプを組み合わせて作れと言われてもたぶん私にはできないでしょう。ん?ホントにできないかな?一度やってみようかな。(^^)
しかしWebの質問サイトなどで「どうしても位相をロックできなくて困っている」という質問などもたくさんありますね。かなり難しいのは確かなようですね。
kaoaruさん,ホロンといい,リアルタイムのコメントだな。LINEみたいですね。(私は使っていませんが ^^;)
実は周波数シンセサイザの設計で,VCOだけ担当したことがあります。決まった回路があって,それほど設計に苦労は無かったけど,評価で温特の苦しめられた記憶があります。低温側です。
PLL全体の勉強が不足しています。オールディジタルが主流(?)ですよね。何か良い書物でもありますか?