
「 FOSTEX フルレンジユニット FE83En 」の紹介がてら、スピーカーのインピーダンスについてもう少し考えてみます。周波数特性の図を見ると、150Hz辺りに急峻な山の頂点があります。これはコーン紙とボイスコイルが一体になった物体の質量(M)とエッジのダイヤフラムのバネ定数(k)によって構成される共振現象であり、この時の周波数を一般に共振周波数:f0と表します。[ω0=√(k/M) f0= 1/2π × √(k/M)]
このf0においてインピーダンスが急増しています。何故でしょう。実は共振による振動は理屈上、外部からのエネルギーを必要としないのです。実際にはメカロスや空気抵抗などによって永久に振動し続けることはありませんが、ごく僅かなエネルギーを供給するだけで振動を継続させることができます。つまりf0においては、ボイスコイルが発生させた磁気エネルギーは、磁石の静磁界によってほとんど相殺されない(力に変換されない)ということです。よってボイスコイルは、ほぼ単独のインダクタンスとして働きインピーダンス(誘導性リアクタンス)を増加させているわけです。もし、ボイスコイルを機械的に固着させてインピーダンス特性を測れば、20Hz~1kHzまで直線となり、ぴったり8Ωを示すでしょう。
次に、1kHz以上において、じわじわとインピーダンスが増加しています。これはボイスコイルではなく、ボイスコイルを作っている電線(ポリウレタン線)のインダクタンス成分が効いてきているのです。ボイスコイルを解いて一本の電線に延ばしたと考えてください。電線のインダクタンスは長さに比例して大きくなります。そして、この電線のインダクタンスによって生じる磁束は、磁石の静磁界の方向と直交しているためにまったく打ち消されないのです。逆に言えば、電線が生じる磁束により力を発生することはありません。
関連記事:スピーカーのインピーダンスを考える① 2011-07-28
このf0においてインピーダンスが急増しています。何故でしょう。実は共振による振動は理屈上、外部からのエネルギーを必要としないのです。実際にはメカロスや空気抵抗などによって永久に振動し続けることはありませんが、ごく僅かなエネルギーを供給するだけで振動を継続させることができます。つまりf0においては、ボイスコイルが発生させた磁気エネルギーは、磁石の静磁界によってほとんど相殺されない(力に変換されない)ということです。よってボイスコイルは、ほぼ単独のインダクタンスとして働きインピーダンス(誘導性リアクタンス)を増加させているわけです。もし、ボイスコイルを機械的に固着させてインピーダンス特性を測れば、20Hz~1kHzまで直線となり、ぴったり8Ωを示すでしょう。
次に、1kHz以上において、じわじわとインピーダンスが増加しています。これはボイスコイルではなく、ボイスコイルを作っている電線(ポリウレタン線)のインダクタンス成分が効いてきているのです。ボイスコイルを解いて一本の電線に延ばしたと考えてください。電線のインダクタンスは長さに比例して大きくなります。そして、この電線のインダクタンスによって生じる磁束は、磁石の静磁界の方向と直交しているためにまったく打ち消されないのです。逆に言えば、電線が生じる磁束により力を発生することはありません。
関連記事:スピーカーのインピーダンスを考える① 2011-07-28
















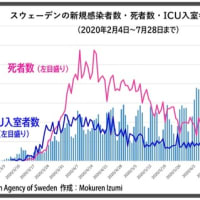









FE83シグマっていう磁気回路強化版を使ったことがありますが、なかなかハギレのいい音でした。
ブックシェルフ型にして本棚に埋め込む使い方が最高です。場所もとらないし。
FOSTEXに電話して喧嘩腰で聞きましたよ。「つまり8Ω」というのはボイスコイルの電線抵抗のことでしょ!」ってね。「再生周波数帯域でもっとも小さくなるインピーダンスです」などと回りくどい説明をされたもので。対応した人は「はい、電線の直流抵抗のことです」と白状してました。
(^^)
FE83でブックシェルフ。いいですねえ。
スピーカユニットの組み立てキットまで出ていました。ボンドまでセットされて・・・。
その頃は通称「ロクハン」と呼ばれていたFE163(だったか?)を愛用してました。学生の身分にはゼイタクなユニットだったと思います。
ロクハン・・・つまり6.5インチの口径ということです。
この他には「コーラル」のホワイトコーンのロクハンユニットだとかも試していました。
なるほどロクハンですか。フォステクスもコーラルもスピーカーユニットとして高級品でしたから、たしかに学生のお財布にはチト厳しかったですよね。
フルレンジでのバランスがいいことが主な要因だったのでしょう?MFBという方式が採用されたのもこのクラスでした。
ソリッドステートという言葉が出てきた頃にはすたれてしまったモノってたくさんあるのですが、当時の私には興味深いものばっかりで、書籍から情報を得たりしていました。
今で言うところの「提灯ネットワーカ」みたいなモンですかね?
子供の頃から「放浪癖」みたいなモノがありまして・・・。
なにをもってしてフツーと判断するかは難しいのですが、人とは違うことをやってました。世間に背を向ける・・・というスタンスだったのかな?
ヨソの人から見たら「変わった子」だったんでしょうねぇ~、GFもできないような子でしたから・・・。そういう反動力を自分の源としていたような気がします^^;
ドロンコーン側で発生させた起電力を負饋還に加えるわけです。
現在使われている「負帰還」という語は、昔は「負饋還」という字面だったのです。
「出力の1部をもどす」のではなく「出力の1部を入力に喰わす」という解釈です。私はそれが正解だと、高校生の身でありながら、そう感じました。ほんとにナマイキでしたねぇ~!
その当時は「トールボーイ型のバスレフボックス」にフォステクスのユニットを組み込んで使っていました。
もちろん、プリもパワーアンプも自作でした。
最初はバイポーラトランジスタのプリ+ハイブリットパワーIC(SANYOのSTKシリーズで25W+25Wのやつ)からスタートしました。
その後、アンプはすべてタマになりましたし、テープデッキはAurexの4トラックオープンリール(19cm/s)がメインでした。
プレーヤはテクニクスのローコストなSL-20でしたが、FGサーボ、よかったですねぇ~!
カセットデッキ入手が一番最初でテクニクスのRS-265Uという一番安いものでしたが、気に入ってました。
オーディオ三昧してた高校生でした・・・。
2SC1000BLが2段で最終段が2SC458のエミホロバッファという、今考えても「欲しいな!」と思える仕様でした。
電源電圧も12V~だったので使いやすかったのです。
プリはRIAAイコライザのみで、フラットアンプも省略というシンプルな(手抜きな^^;)構成としたのです。
一番最後にサンスイのFMチューナを入手するのですが、それまでは三菱ジーガムにFMマルチプレックスアダプタのキットを入手してそれでやってました。
いやぁ~、当時の高校生ってそんなモンだったのですねぇ~!
今はiPhoneやiPodなんでしょうけどねぇ~!
MFBとはメカニズムが違うのかも知れませんが、スピーカーユニットの前にマイクを置いて、そのマイクで拾った信号を負帰還するってのがありましたね。フォステクスだったか、コーラルだったか。
昔は「負饋還」だったのですか。それは知りませんでした。出力の一部を入力に食わすわけですか。う~む、なるほど。フォステクスのユニットを付けたバスレフ、プリもパワーも自作、その後アンプはすべて球、オーレックスのオープンデッキにプレーヤーとカセットデッキはテクにクス、なんて高校生ですか。(^^;
サンスイのFMチューナなんて渋いですね。三菱ジーガムってのがありましたっけねえ?
そう!今はiPhoneやiPodなんですよねえ。(; ;)
どうりで、友達もほとんどいなかったワケだ^^;
今は~「カセットデッキが友達さっ!」
昔に戻りましたね^^;
こういうのは、「退化の改心」というんです(笑)。