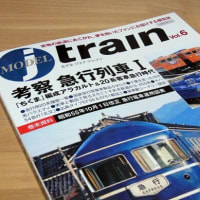ホビージャパンさんの
『Train Modeling Manual vol.3』に掲載して頂いている
「TORO-Q」の記事でワタシ、
スケールエフェクトという言葉をしれっと使ってますが、
奇しくも同誌で保土ヶ谷一夫氏も触れているんですね。
厳密に言うと、
スケールエフェクトという言葉自体は
『月刊ホビージャパン』3月号の
関連記事で使われているわけですが、
そこに掲載されている保土ヶ谷氏のD51作例と
ワタシのTORO-Q、
ベクトルの向きが全然違うのが面白い。
同じ「スケールエフェクト」を
意識しているにもかかわらず、なのに。
ワタシの考えているスケールエフェクトってのは、
どちらかと言うと
色彩学の面積効果を考慮した「補正」に近い。
同じ色でも面積が小さいと、
面積が大きい時よりも暗く見えてしまう。
ワタシの作例の場合は連載記事の性質上、
デザイン再現にウェイトを置いているので
1/150に縮小することでドーンデザインの魅力の一つである
色彩の鮮やかさを殺してしまうわけにはいかない。
だから今回は実物よりも明度を上げているわけです
(と同時に彩度を落とすわけにもいかないので
純色グリーンも加えています)。
記事でも書いた通り
元々そういう方向に振った配色が好みってのもあるし、
空気遠近法なども全く意識してないわけではないですが。
まぁ、どっちが正しいとか良いという話ではないです。
模型ってのは立体の絵みたいなもんですから、
いわば「タッチの違い」なのでしょう。
それに優劣をつけようとするのは
「油絵調」と「アニメ塗り」を比べるぐらいナンセンスです。
むしろ、ワタシ的には他のジャンル出身の方が
表現の選択肢を広げてくれるのは大歓迎。
うん、もっとグイグイとこじ開けて!
鉄道の魅力はもっと色んな描き方があるハズだし、
ワタシも沢山見てみたいッス。
『Train Modeling Manual vol.3』に掲載して頂いている
「TORO-Q」の記事でワタシ、
スケールエフェクトという言葉をしれっと使ってますが、
奇しくも同誌で保土ヶ谷一夫氏も触れているんですね。
厳密に言うと、
スケールエフェクトという言葉自体は
『月刊ホビージャパン』3月号の
関連記事で使われているわけですが、
そこに掲載されている保土ヶ谷氏のD51作例と
ワタシのTORO-Q、
ベクトルの向きが全然違うのが面白い。
同じ「スケールエフェクト」を
意識しているにもかかわらず、なのに。
ワタシの考えているスケールエフェクトってのは、
どちらかと言うと
色彩学の面積効果を考慮した「補正」に近い。
同じ色でも面積が小さいと、
面積が大きい時よりも暗く見えてしまう。
ワタシの作例の場合は連載記事の性質上、
デザイン再現にウェイトを置いているので
1/150に縮小することでドーンデザインの魅力の一つである
色彩の鮮やかさを殺してしまうわけにはいかない。
だから今回は実物よりも明度を上げているわけです
(と同時に彩度を落とすわけにもいかないので
純色グリーンも加えています)。
記事でも書いた通り
元々そういう方向に振った配色が好みってのもあるし、
空気遠近法なども全く意識してないわけではないですが。
まぁ、どっちが正しいとか良いという話ではないです。
模型ってのは立体の絵みたいなもんですから、
いわば「タッチの違い」なのでしょう。
それに優劣をつけようとするのは
「油絵調」と「アニメ塗り」を比べるぐらいナンセンスです。
むしろ、ワタシ的には他のジャンル出身の方が
表現の選択肢を広げてくれるのは大歓迎。
うん、もっとグイグイとこじ開けて!
鉄道の魅力はもっと色んな描き方があるハズだし、
ワタシも沢山見てみたいッス。