山田太一さんへの取材から(読売新聞より)
尊敬するあいどんさん(山田さんのお友だち)のカキコをそのままペーストさせてもらいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドラマの脚本や小説を通じて、家族や現代社会のありようを描いている山田太一さんに、介護や孤独死、子育てなどについて聞いた。(聞き手・猪熊律子)
◇
――最新の小説「空也上人がいた」は、介護現場が舞台となっている。介護の現状をどう見るか。
「取材や、老人ホームに入った知人の話などを通じて、介護の話を書きたいと思った。小説では、20代の男性ヘルパーと40代の女性ケアマネジャーが出てくる。この年代のケアマネは魅力的な人が多い。介護の仕事は、時にキレても仕方ないくらい大変な割に、給料が低すぎる。もっとお金を払うべきだと思う」
――小説に出てくる80代の男性は自ら死を選ぶ。自殺についてはどうか。
「今回の東日本大震災で、一時期、死者、行方不明者あわせて3万人弱という数字が出てみんな驚いた。だが、日本では毎年3万人を超える自殺がある。それだけ生きていても仕方ないと思う人がいる社会というのは、やはり異常だ。人間は何日も絶望したままでは生きられず、ある瞬間を乗り越えられれば生きていけるのに、そうなっていない。また、絶望の根底には、自分は生きる価値がないとか、あいつは駄目な奴(やつ)といったマイナスの思考が見られるが、今の社会は、マイナスをなくそう、なくそうとし過ぎるのでは。人生はプラス、マイナス両面から成り立っている。人間はマイナスによっても育まれるということに、みんながもっと気づけば生きやすくなる」
――孤独死については。
「戦後、日本人は、家制度や親の束縛を受けずに自由に生きる個人主義を目指してきた。その究極の姿と言えなくもない。行政が何かするというより、一人ひとりが考える問題だ。ただ、自殺もそうだが、助けを求められたら手を差し伸べられるような社会でありたい」
――今回の震災で、34年前の作品「岸辺のアルバム」が再び注目されている。震災で感じることは。
「規模が違うので同じように言うのは失礼だが、自然災害で今まで築いたものを一瞬にして失ったという点では似ている。小説では、全てを失うことは決してマイナスなだけでなく、改めて生き直す機会にもなると描いた。できれば、そうあってほしい。災害にしろ、病気にしろ、経験した人としない人とではものすごい差がある。一生懸命想像はするけれど、届かないものがあるということを忘れてはいけないと思う」
――子育てや家族について。
「子育てを大変なもの、マイナスととらえるのはもったいない気がする。家族、特に親と子は、自分で選べないという点で宿命的。それが人を育て、鍛えもする」
◇
1934年生まれ。早稲田大卒。松竹の助監督を経て、65年に独立。代表作に「ふぞろいの林檎たち」「異人たちとの夏」など。
(2011年7月5日 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全く同感です。
特に赤い部分は、悩んでいる全ての人に伝えたいし、これを読んでホッとして欲しいですね(^.^)
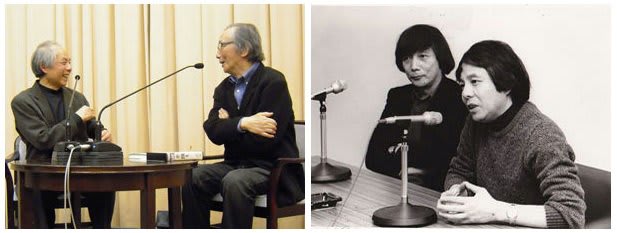
右は、ちょっと昔の天野祐吉さんと山田太一さん(山田さん、なかなかイケメンでしょう?)
尊敬するあいどんさん(山田さんのお友だち)のカキコをそのままペーストさせてもらいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドラマの脚本や小説を通じて、家族や現代社会のありようを描いている山田太一さんに、介護や孤独死、子育てなどについて聞いた。(聞き手・猪熊律子)
◇
――最新の小説「空也上人がいた」は、介護現場が舞台となっている。介護の現状をどう見るか。
「取材や、老人ホームに入った知人の話などを通じて、介護の話を書きたいと思った。小説では、20代の男性ヘルパーと40代の女性ケアマネジャーが出てくる。この年代のケアマネは魅力的な人が多い。介護の仕事は、時にキレても仕方ないくらい大変な割に、給料が低すぎる。もっとお金を払うべきだと思う」
――小説に出てくる80代の男性は自ら死を選ぶ。自殺についてはどうか。
「今回の東日本大震災で、一時期、死者、行方不明者あわせて3万人弱という数字が出てみんな驚いた。だが、日本では毎年3万人を超える自殺がある。それだけ生きていても仕方ないと思う人がいる社会というのは、やはり異常だ。人間は何日も絶望したままでは生きられず、ある瞬間を乗り越えられれば生きていけるのに、そうなっていない。また、絶望の根底には、自分は生きる価値がないとか、あいつは駄目な奴(やつ)といったマイナスの思考が見られるが、今の社会は、マイナスをなくそう、なくそうとし過ぎるのでは。人生はプラス、マイナス両面から成り立っている。人間はマイナスによっても育まれるということに、みんながもっと気づけば生きやすくなる」
――孤独死については。
「戦後、日本人は、家制度や親の束縛を受けずに自由に生きる個人主義を目指してきた。その究極の姿と言えなくもない。行政が何かするというより、一人ひとりが考える問題だ。ただ、自殺もそうだが、助けを求められたら手を差し伸べられるような社会でありたい」
――今回の震災で、34年前の作品「岸辺のアルバム」が再び注目されている。震災で感じることは。
「規模が違うので同じように言うのは失礼だが、自然災害で今まで築いたものを一瞬にして失ったという点では似ている。小説では、全てを失うことは決してマイナスなだけでなく、改めて生き直す機会にもなると描いた。できれば、そうあってほしい。災害にしろ、病気にしろ、経験した人としない人とではものすごい差がある。一生懸命想像はするけれど、届かないものがあるということを忘れてはいけないと思う」
――子育てや家族について。
「子育てを大変なもの、マイナスととらえるのはもったいない気がする。家族、特に親と子は、自分で選べないという点で宿命的。それが人を育て、鍛えもする」
◇
1934年生まれ。早稲田大卒。松竹の助監督を経て、65年に独立。代表作に「ふぞろいの林檎たち」「異人たちとの夏」など。
(2011年7月5日 読売新聞)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全く同感です。
特に赤い部分は、悩んでいる全ての人に伝えたいし、これを読んでホッとして欲しいですね(^.^)
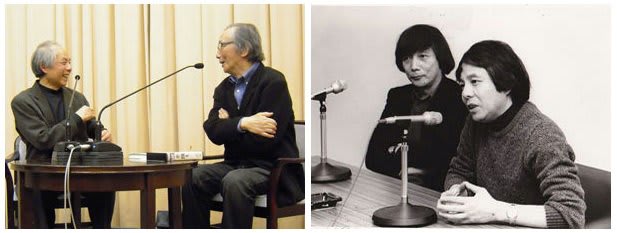
右は、ちょっと昔の天野祐吉さんと山田太一さん(山田さん、なかなかイケメンでしょう?)










