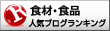・義須Gissu ぎす
ソトイワシ科Albulidae(ソトイワシ目Albuliformes)、ギス科(ニシン目)、ギス属Pterothrissus と、北日本の深海に生息する。体長60cm、重さ500gで200~500mのやや深海性、海産魚で体型は細長くキスに似るが背側が灰褐色で腹部にいくに従い白色を帯びている。
3~5月に産卵の為海面下に移動してきた時に捕らえ旬とするが市場に流通することは少ない。小骨が多く身が柔らかく、団子、から揚げ、さつま揚げ、主にカマボコの原料としている。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
現在、日本では様々な野菜を栽培していますが、農林水産省の統計で生産量等を把握しているものだけで約90品目にのぼります。 ですが、日本原産のものは、それほど多くはなく、私たちが普段食べている野菜のほとんどは、欧米や中国大陸から日本に持ち込まれたと言われています。日本原産の食用植物として、日本原産の植物は、日本列島の湿地帯に自然に生えていた雑草としての始まりました。日本原産としている野菜は20種類ほどという説が、日本では近年では主に約150種類の野菜を栽培、利用しているのですが、そのうちの日本原産の野菜は
1)独活(うど)、2)陸鹿尾菜(おかひじき)、3)牛蒡薊(ごぼうあざみ)、4)山椒、5)自然薯(じねんしょ)、6)ジュンサイ、7)芹(せり)、8)蓼(たで)、9)蔓菜(つるな)、10)白藍(はくらん)、11)浜防風、12)蕗(ふき)、13)菱(ひし)、14)松菜(まつな)、15)三つ葉、16)茗荷(みょうが)、17)百合、18)山葵(わさび)、19)ヤマゴボウ(有毒植物)などとしていますが、一方で日本原産の野菜は独活(うど)や、芹(せり)、三つ葉、蕗(ふき)、山葵、自然薯などほんの数えるほどとも言われます。
ヤマゴボウは、有毒植物として知られているのですが、葉・茎にはアルカロイドやサポニン、根には硝酸カリが含まれます。
そもそも原産とは、最初に産出した土地であり特に、動植物のもともとの産地といい最初に産出ということです。
大根や蕪、茗荷や葱などは古くから食べられていますが、海外から伝わったものとも考えられています。 牛蒡も古くに中国大陸から伝来としていますが、食用は主に日本で、他の国ではほとんど食用ではないようです。
◇大根は、春の七草に有り地中海沿岸または中央アジア原産で日本には、弥生時代までに中国から伝来で、江戸時代には各地で栽培するようになりました。
◇かぶも春の七草に原産地は、アフガニスタン周辺や地中海沿岸の南ヨーロッパ付近と考えられています。ヨーロッパでは紀元前からの栽培とのこと16世紀以降には食用と飼料用が広く栽培です。日本には中国を経由で弥生時代に渡来し、各地に多くの品種が存在し栽培が成立しています。記録的には「日本書紀(720年)」に記録としてあります。
◇和梨は日本原産と思われているのですが原産地は中国大陸で、古墳時代に大陸からの渡来人とともに日本に渡来したと考えられています。日本の野生種と交配し誕生した果実で、日本固有の栽培環境に適応して独自の進化を遂げているようです。奈良時代(710年~794年)以前に日本に伝来としています。
◇茗荷の原産地は東アジアで、日本を含むアジア東部の温暖地帯です。日本以外では台湾や韓国の一部にも生息を確認です。食用として栽培は日本だけで、香りの野菜として知られます。
◇葱の原産地は中国西部や中央アジア、シベリア、バイカル地方などと言われ紀元前200年ごろには中国で栽培を確認、土寄せの根深ネギの栽培方法も紀元前の中国で始まったといいます。日本には日本書紀(720年成立)の仁賢天皇6年(493年)9月に「秋葱」の名で登場するのが日本最古の記録があり奈良時代(710年~794年)以前から伝来し、江戸時代には全国で栽培としています。
◇ハクラン(白蘭)は、昭和34年、当時平塚市にあった農業技術研究所でハクサイとキャベツの種間雑種で、バイオテクノロジーによって開発の日本初のバイオ野菜です。昭和34年に平塚市の農業技術研究所で両者は染色体数が異なり、自然状態では交雑できない交雑植物の誕生でした。
◇浜防風は東アジアの台湾、中国、朝鮮及びロシアの海岸からカムチャッカに広く分布し、日本も原産国のひとつとしています。
◇蕗(ふき)は、北海道から沖縄まで野生種が分布しているほか、日本以外にも中国や韓国でも自生しているようです。
◇菱(ひし)は、日本全国の平地にある池や沼、湖などに多く群生し、朝鮮半島や中国、台湾、ロシアのウスリー川沿岸地域などにも分布しています。
14)松菜(まつな)は、ヒユ科の一年草で、海岸の砂地に生える植物です。若芽は食用にでき、野菜として栽培することもあります。
◇茗荷(みょうが)は、日本を含むアジア東部を原産として 3世紀末に書かれた「魏志倭人伝(ぎしわじんでん)」にもその名が見られるなど、古くから全国に自生しています。
◇百合は、日本原産の植物として、日本には15種類ほどが自生し7種類は日本特産種で、ユリを食用に品種改良の「ゆり根」という野菜は、江戸時代ごろから食用としていたようです。オニユリやヤマユリの球根で収穫までに約3年といいます。北半球で発見の植物で野生種では、アジア、ヨーロッパやアメリカに南は赤道付近やインドでも発見しています。
◇山葵(わさび)は、日本原産。中国大陸の近縁種とは、約500万年前に分化したと推定しています。
◇マルミノヤマゴボウは、本種は有毒です。「山ごぼう」の名で漬物として売られているは、モリアザミの根です。
◇大豆の原産地は中国東北部、黒龍江沿岸と一般的に考えられています。紀元前2838年に中国を支配した神農皇帝の医薬の書物『神農本草経』に大豆に関する記録が見られ、古くは4000年前から栽培と推定です。大豆の原産地は中国東北部、黒龍江沿岸と一般的に考えられています。大豆の原種はツルマメ(ノマメ)として、日本には中国から朝鮮半島を経て伝来としており、縄文時代中期に痕跡が見られ栽培が始まったようです。
全国的に流通し、特に消費量が多い国内生産量が多い野菜を例として見てみますと、だいこん、さといも、ねぎ、きゅうり、なすの5品目は縄文から平安時代にかけて渡来と見られ、ばれいしょ、キャベツ、ほうれんそう、トマトの4品目は江戸時代に、にんじん(西洋種)、はくさい、レタス(結球種)、たまねぎ、ピーマンの5品目は明治時代以降に日本に伝わったと言われています。
外国人が苦手な日本の食材としているのは、生卵 、刺身、板海苔は、海外ではもともと食べる習慣がないようです。
農林水産省の統計によると、家計消費用の野菜は国産割合がほぼ100%であるのに対し、加工・業務用の野菜は国産割合が約7割となっています。
輸入量が多い野菜は、生鮮品では、たまねぎ、🥕にんじん、かぼちゃが多く、たまねぎが全体の3割強を占めます。🧅玉葱、🥕人参は、加工原料用や業務用で多く使われています。その他、加工品として、🍅トマト(ピューレ、ジュース等)、🌽スイートコーン(冷凍、缶詰)、🥕人参(ジュース)類を輸入しています。野菜の自給率向上に向けて、令和2年(2020年)3月に定めた食料・農業・農村基本計画では、需要が拡大する加工・業務用野菜について輸入品から国産品への置き換えを目指すこととしています。
日本原産の野菜といわれているものの多くは、有史・文字の伝来以前、縄文時代の貝塚からの痕跡のある物、海外で自生の環境が同程度であるなどで、原産地が決められているように思えました。そして、その後に、日本には導入以前には、見られていなかった野菜類に、多く見られる地域が原産地表示として見られているのではないのかと私の考えているところです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
・鎌柄 かまつか
コイ科、青森、北海道を除いて、秋田、岩手以南日本各地の川、湖の砂底地に生息する淡水魚で体長15~25cmになる。目が小さいがぱっちりして頭がとがりぎみ、一対のひげをもちウグイをスマートにした細長い筒型をした体型で背が青黒くはん点模様がある。川底でじっとしていると、まるで「棒」の様で、それが鎌の柄に見えるという。おとなしい性格で目だけ出して砂に潜っていることが多く、スナホリ、スナモグリとも呼ばれる。綺麗な砂底を好み、砂底の砂を口から吸い込み、水生昆虫などの底性の小動物を食べ、砂だけをエラから吐き出す。愛くるしいしぐさから観賞用として飼われることもある。産卵期を5~6月として3~4月を旬とするが、白身の魚で味が淡白で塩焼き、天ぷら、甘露煮にしている。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
鎌柄 かまつか |
・フェオホルバイドPheophorbide ふぇおほるばいど
植物の緑色の色素で葉緑素(クロロフィル)を分解することによりでき、クロロフィルからマグネシウムを離脱させフェオフィチンとなって、さらにフィチル基を脱離するとフェオホルバイドになる。 光線過敏症の皮膚障害を起こす物質としている。
摂取すると光線の当たる部分の皮膚の浮腫や潰瘍、表皮の壊死の例がある。脂溶性で茶の浸出液では溶出しにくいが近年、食べる茶あるいは食材としての茶の需要が増大、クロレラ、スピルリナ、ドクダミ、大麦若葉類の健康食品類の過剰摂取、加工、保存の過程などでみられる。
厚生労働省が含有制限を設けてフェオホルバイドPheophorbide量の基準がクロレラで100mg/100g以下、総フェオホルバイド量160mg%と定めている。対象商品の粉末・顆粒・錠剤で概(おおむ)ね総フェオホルバイド量5.0mg%~93.9mg%の含有量であった。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
・微量栄養素Micronutrient びりょうえいようそ
無機質、ビタミン類をさしており1日に必要とする量は、mgからμg単位で少なく、微量で人体機能に不可欠な栄養素としている。
無機質のうち炭素(18%)、酸素(65%)、水素(10%)が主な成分で全体の93%を占める。これらは窒素(3%)と共に炭水化物、蛋白質、脂質の有機化合物の構成元素として利用している。
無機質(ミネラル)では、これ以下のCa(カルシウム)、Fe(テツ)、P(リン)等現在16種(不足しがちなミネラル10種Ca.Fe.I.Mg.Mn.Cu.Zn.Se.Cr.Mo)ほどが必要不可欠な成分として見出している。
ビタミンの分類は最近必ずしも明確ではないが不可欠な栄養素としている。それぞれに特有の代謝、生理作用、欠乏、過剰症状を有する。生活習慣病は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、高尿酸血症などが代表的な疾患であり 不足したりバランスが崩れると免疫力が低下し健康を害する。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
ベンゾールBenzol(ドイツ語)ともいい、融点5.4℃、沸点80.5℃で最も簡単な芳香族炭化水素で、有機塩素化合物であり、石炭ガス、コールタール、原油、軽油、ガソリン中に存在、現在では9割以上石油から生産する。
サンフィッシュ科、北アメリカ原産の淡水魚の一種。雑食性で全長25cm。生後約1年目までの幼魚では体形がやや細く、体側には7~10本の暗色横帯がある。
日本への移入は、1960年に当時の皇太子明仁親王(今上天皇)が外遊の際、15尾をシカゴ市長が寄贈し、日本に持ち帰った15匹が最初で日本各地の湖沼やため池、堀などに侵入・定着している。繁殖期は春~夏で雄は巣に残り卵を狙う他の動物を追い払ったりして卵を守る。食味は淡泊だが軟らかく美味しいというが成長が遅く養殖にはコスト高で適さず日本ではあまり食用としていない。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
言葉の意味は「健全な、新鮮な、元気のある」というラテン語 vegetusに由来するとしているがイギリスで生まれた語でVegetable(野菜、植物)の意味も込められていると思われる。「イギリスベジタリアン協会」発足式(1847年)で発表している。
単に植物、菜食という食生活の節制ということだけではなく、動物を殺傷して生産する絹、皮製品などに対する人生観・世界観をより深め、命の大切さを、教えている。
ベジタリアンにも、完全な菜食主義者ばかりでなく、動物性食品も適度に取り入れていることもある。植物性食品だけの生活では、栄養バランス上、植物性食品に殆ど含まれないか少ない、動物性食品に多く含むビタミンB12、アミノ酸のリジン、メチオニンの不足に陥りやすい。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
3月22日は、「世界水の日World Water Day」です。
3月22日は国連が定めた「世界水の日」 気候変動や紛争で悪化の一途をたどる水の危機 46年ぶりに国連水会議も開催 (unicef.or.jp)
淡水の保全と持続可能な水の大切、きれいで安全な水を使えるようにすることの重要性について世界中の人々と一緒に考えることを目的としています。
淡水資源管理の促進への人々の意識を啓発し、各国の行動につなげるため、1992年12月の国連総会で制定し1993年から毎年3月22日を「世界水の日」とすることを決議しました。この日は、水資源の開発・保全や1992年にリオデジャネイロ(ブラジル)で開催の国連環境開発会議(地球サミット)で採択の持続可能な開発を実現するための行動計画、アジェンダAgenda(課題項目)21の勧告の実施に則(そく)し普及啓発を行う日とし以降、世界中で毎年3月22日やその前後に、さまざまな催しやキャンペーンなどが行われます。
2021年の世界の水使用量ランキングは、1位 インド(761.00km3/年、2位 中国(581.29km3/年、 3位 アメリカ(444.29km3/年)、・・・・・10位日本(78.30km3/年) で世界的に水使用量が多いのは農業としています。
世界の人口1人当たりの水資源量ランキングは、1位 アイスランド(459,044m3/年・人)、2位 ガイアナ(336,827m3/年・人)、3位スリナム(161,505m3/年・人)でした。
日本は世界平均8372m3を下回り、98位でした。島国のため国外から入る水が少なく、人口が多いことが響いているようです。
水道水が飲める国は、諸説ありますが、「国土全体において水道水を安全に飲める国」は世界に15ヵ国程度といわれています。1. フィンランド、2.スウェーデン、3.アイスランド、4.アイルランド、5.ドイツ、6.オーストリア、7.スイス、8.クロアチア、9.スロベニア、10.アラブ首長国連邦、11.南アフリカ共和国、12.モザンビーク、13.オーストラリア、14.ニュージーランド、そして15.日本です。
2022年時点で世界では、地域や収入などによって格差があり約22億人が世界人口の4分の1に相当の人々では安全に管理の飲み水を利用できずにいます。
世界の水問題の現状は
◇不衛生な水を使用している人々が湖や河川、用水路などの未処理の地表水を使用している人は約1億1,500万人といわれます。安全な水が無いため長く生きられない子が大勢います。
◇水汲みに多くの時間を費やし主に女児・女性が自宅での給水のない家庭では、水汲み輸送の役割を担っています。
◇トイレや手洗いの下水管設備が身近にない人々は、手洗いができず不衛生な環境の中で、病気や下痢などによって亡くなる人もいます。
◇気候変動の影響で水不足が深刻化しています。干ばつや洪水の頻度が高まり、被害規模も大きくなる傾向で、衛生的な水は不足し、供給は止まることもあり、地域社会の復旧は困難を極めています。
国連環境開発会議(地球サミット)では、2030年までにすべての人が安全で安価な飲み水を入手できることを目標としています。
制定の背景には、地球上のすべての経済活動や社会活動は、質の良い淡水とその供給に大きく依存しているにもかかわらず、人口と経済活動の増加により、多くの国が急速に水不足に陥ったり、経済成長に行き詰まったりしている現状への危機感がありました。
今日、「世界水の日」は、2015年9月に採択の「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標6「安全な水とトイレを世界中に」で、2030年までに誰もが平等・安全に管理してある「水と衛生」を手に入れることの達成に向けてアクションを取るための日でもあります。
しかし、最新のデータによると、世界人口の半数の家には安全に管理の行き届いた衛生設備がなく、4分の1が安全な飲料水を利用できず、3分の1近くは水とせっけんを備えた手洗い場が自宅にありません。これらは、SDGs目標達成にはほど遠い現状を示しています。
安全な水と適切な衛生が、子どもの権利を守ることを重要視しています。
日本における水の使い方ランキングは、1位 風呂 2位水洗 トイレ 3位台所 4位洗濯水の順となります。
世界平均と比べると、日本の年間平均降雨量は約1.6倍にもなるのですが、日本の河川の多くが山からの急勾配で、短い時間で海に流れ出てしまい水を確保する量は少ない現状のようです。生活で実際に使用できる水の量は、人口一人あたり世界平均のおよそ45%程度といわれています。
国土交通省では水需要は2000年から2050年の間に、主に製造業の工業用水(+400%)、発電(+140%)、生活用水(+30%)の増加により、全体で55%の増加を見込んでいます。 2050年には、深刻な水不足に見舞われる河川流域の人口は、39 億人(世界人口の40%以上)となる可能性もあると予想しています。干ばつ、洪水や地滑りなど水に関わる災害も増えており、気候変動対策や治水の改善が急務な状況です。
水に関する記念日が続々登場してありました。
6月6日は「飲み水の日」で 1990年(平成2年)の制定です。東京都薬剤師会公衆衛生委員会により 世界環境デー(6月5日)の翌日です。 身近な存在である水に改めて目を向け、日本では当たり前のように水道水を飲むことができますが、水道水をそのまま飲める国は珍しく、その大切さを再認識する機会を提供することを目的としています。
8月1日は、「水の日」および1日から1週間は「水の週間」です。1977年(昭和52年)に、国土交通省で制定の水循環基本法(平成26年法律第16号)により、毎年8月1日は、国民の間に広く健全な水循環の重要性について理解や関心を深める日として定めていました。「水の日」および「水の週間」は、水の大切さや水資源開発の重要性、水の有限性や貴重さについて理解を深め、無駄遣いを防止することが「水の日」の主な目的です。水に対する国民の関心を高めるために閣議で定めています。水の使用量が多く、水についての関心が高まる8月の初日を「水の日」(8月1日)とし、この日を初日とする一週間(8月1日~7日)を「水の週間」とし、水に関する様々な啓発行事を実施しています。
毎年8月下旬に毎年8月下旬には世界水週間(World Water Week)として、毎年8月下旬にスウェーデンのストックホルムで開催です。水問題に関する世界最大級の国際会議です。スウェーデン国際水研究所(SIWI:Stockholm International Water Institute)の主催により、水資源の持続可能な管理や保護の重要性を訴え、解決策を見出すための場を提供しています。世界190以上の国から研究者や政策決定者、企業、NGOなどが参加しています。
10月17日の上水道の日は、日本で初めて近代的な上水道が造られた1887年(明治20年)に現在の神奈川県横浜市で、イギリス人技師ヘンリー・スペンサー・パーマー氏の指導のもとに、川などから取り入れた水を濾過 して、鉄管などを用い有圧で給水の近代的な水道のことで10月17日のこの日に給水を開始したことからの制定です。
ちなみに、9月10日は下水道の日で、台風シーズンの210日を過ぎた220日(立春から数えて)が適当とのことによります。1961年(昭和36年)に、日本下水道協会(1964年設立)の前身団体(当時の建設省・厚生省)が協議して制定です。
12月1日を東京都水道局は、「東京水道の日」に、給水を開始した1898年(明治31年)12月1日であることより制定しました。東京の近代水道の始まりとして、淀橋浄水場から神田・日本橋地区に給水を開始したことに由来し、2019年(令和元年)記念日協会に登録しています。
人間3の法則がありました。3の法則は、人間が呼吸ができない状態で生きられる時間が3分、体温保持ができない状態で3時間、水分補給ができない状態では3日、食料補給ができない状態では3週間というのです。 個人の体調や体形、代謝によって多少の時間のずれはありますが、健康体であった人で単純に表しています。
人は、水と睡眠が充分に行えていれば、たとえ固形食物の摂取ができなかったとしても2〜3週間は生き永らえていられると言われいます。 しかし、水を一滴も取らなければ、せいぜい4〜5日で絶命に陥る可能性が高くなります。日本は、実際には水ストレスが高い国として発表しています。これは日本の地形、さらに食料自給率に起因しているのです。 約60%を輸入に頼っていることより食料の輸入はその農業で食料を生産した場合に必要な水も含まれ形を変えて水を輸入していると考えるられるからなのです。食料自給率率40%を上げることも、水不足解消に重要なことのようです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
・有機農産物及び有機農産物加工食品Organic plant and livestock processed foods ゆうきのうさんぶつおよびゆうきのうさんぶつかこうしょくひん
わたしたちは、健康を維持するため、より良い生活環境を守り、美味しい食材を求めて有機食品をもてはやすようになりました。
有機食品と言うと無農薬で化学肥料を使っていない農地で栽培、収穫された農産物のイメージがあります。しかし、以前は、その食品の基準があいまいで一部に消費者を惑わす不適切な表示が目立っていたのです。これまでにも農林水産省は、1992年「有機農産物及び特別栽培農産物に係る青果物等特別ガイドライン」制定、1996年「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」、国際的にはコーデックス委員会1における有機食品の表示基準の検討が進展し、平成11年(1999年) 7月に「コーデックス有機食品ガイドライン」が国際基準として採択しています。認定を受けたもののみが、製品に「有機」の表示を付して流通する仕組みが作られ、平成 12年(2000年) 6 月に施行です。2006年(平成18年)には「有機農業推進法」などを改定してきました。
有機農業の推進に、10周年を記念して2016年に制定の「有機農業の日(オーガニックデイ)」12月8日を記念日として一般社団法人次代の農と食をつくる会が制定しています。
2020年の国際食料安全保障指数が示され最も高かった国は前年に続きフィンランドで、前年から0.2ポイント上昇の85.3でした。日本は9位の77.9です。
以前から有機農業についての表示に対する適正化を図ってきたのですが、これらは、法的な強制力はありませんでした。消費者に分かりにくい、紛らわしい表示もみうけられるようにもなりました。「有機低農薬栽培」「有機減農薬栽培」との表示で、どの程度までが低農薬、減農薬といわれているのでしょう。表示規制の要望の高まりもあり2001年4月1日より栽培方法の基準、第三者の認定期間の検査、認定を受けてJASマークのついた農産物に「有機農産物」「オーガニック○○」の表示が認められるように規制するまでに至っています。
平成18年(2006年)度に策定された「有機農業推進法」において、
有機農業を「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。」と定義しています。
有機JAS規格
有機農産物
第1条有機農産物の生産方法の基準等を定めることを目的とする。第2条有機農産物の原則として
(1)農業の自然循環機能の維持増進を図る。化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として環境への負荷を低減した栽培管理方法を採用したほ場生産されること。
(2)採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取されること。第3条定義有機農産物とは、第4条の基準を満たす方法により生産された農産物をいう。
第4条生産方法についての基準は、「ほ場等の条件」「ほ場等における肥培管理」「ほ場に播種又は植え付ける種苗」「ほ場等における有害動植物の防除」「輸送、選別、調整、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る基準を設ける第5条有機農産物の名称の表示が有機、オーガニックとの表示が認められる。認証を受けていない農産物に「有機○〇」等の表示を行うことはできません
有機農産物加工食品
有機農産物加工食品の日本農林規格は、平成12年(2000年)に制定する
第1条規格の目的有機農産物加工食品の生産の方法についての基準等を定める。
第2条有機農産物加工食品の生産原則で使用する原材料の有機農産物は、有機農産物のJAS規格に規定されている特性が保持され、化学的に合成の食品添加物、薬剤等を使用しないことを基本とする。
第3条有機農産物加工食品の定義第4条生産の方法の基準を満たす方法で生産されること。
第4条生産の方法についての基準「原材料(加工助剤を含む)」「原材料の割合」「製造、加工、包装その他の工程に係る管理について基準を定める」
第5条有機農産物加工食品の名称の表示及び原材料名の表示は「有機農産物加工食品」「オーガニック○○」等の表示方法を定める。転換期間原材料を使用した場合「転換期間中有機農産物加工食品」等と記載する。
原材料名表示は、「有機○○」「有機○○転換期間中」等と記載し加工食品品質表示基準に基づく表示をする。
化学的に合成された肥料の使用を禁止し、農薬に付いては使用目的に合った農薬を定め、その使い方についても使用方法に沿うよう定めています。「転換期間中」「原産地表示」「遺伝子組換え食品」等についてもJAS規格に盛り込まれています。 しかし、農作物を作る側から見ると有機の表示をするのに大変な労力、無用な労力を要することもあります。化学肥料の多用によって自然環境を破壊することも事実です。例えば特に窒素(根を強くし茎、葉を育てる。葉ものに良い。柔らかさ、鮮度を保つ)の多用によって野菜を水っぽくして苦味、えぐみを残し甘味が薄く食感が悪くなる、ビタミンの含有量をも少なくして、土壌を弱くし病虫害に感染しやすい土壌と化してしまいます。それが農薬散布の多用につながり、そして土壌の悪化へと悪循環を起こす結果となりかねません。
2004年(平成16年)4月1日に施行された「特別栽培農産物新表示ガイドライン」により、化学合成農薬と化学肥料を一定量慣行の5割以上減らして栽培された農産物について特別栽培農産物と表示することとなりました。今までは減農薬・減化学肥料・無農薬・無化学肥料などという名称が使われていました。消費者にとってあいまいで分かりにくいため、現在は表示禁止され特別栽培農産物と統一のようです。平成19年(2007年)3月23日に標記ガイドラインを一部改正し、平成19年4月以降に出荷される農産物から適用しています。
有機肥料の魚かす、油かすは他の微量栄養素も含み緩行性ですが地力を衰えさせません。しかし、人が健康を害し体調がすぐれない時に服薬します。同じことが土壌にも言えるのではないでしょうか。処方を間違わないようにすることだと思うのです。そのために連作を避けるなどのいろいろの方法がとられるわけですね。JAS規格のみに有機、オーガニック名称の表示を認められるとのことです。有機、オーガニックの名称にとらわれず消費者は確かな目を持って農産物をみています。有機食品にすることの意義が高い食品としてあげるとすれば、中国の冷凍ほうれん草で問題になったようにそのまま食べられるもの葉物、お茶などになります。皮をむいて調理のされるもの芋類、フルーツ類は中まで農薬が入り込みにくいので有機食品でなくても比較的安全性が高いといえます。
農家の心意気としてその農産物が消費者に安心して食べてもらえるような栽培方法の表示をしてください。作付け時のドキメント、思いを消費者に伝えて頂ければと思います。ハウス栽培で有機JAS規格が認められているようです。減、無農薬、減、無化学肥料栽培農作物でも消費者に届けられる作物があるような気がしてならないのです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。