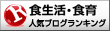・五畜 ごちく 鶏、羊、牛、馬、豚の5種類の主要な家畜、ないし馬(ウマ)、牛(ウシ)、駱駝(ラクダ)、山羊(ヤギ)、羊(ヒツジ)の 中央ユーラシアの草原地域に居る5種の主要な家畜たちのことです。
陰陽五行という中国古代の哲学思想があります。自然界に存在するあらゆるものを五つに分類し、その5種類の間はお互いに関連していると考えに基づいています。 その五つは木、火、土、金、水となります。
陰陽五行思想との結びつきは、食・薬・医の歴史の中で、紀元前200年頃(前漢)から220年(後漢)の頃に編幕と推定です。中国最古の医学書と呼ばれ『黄帝内経素問素問こうていだいけいそもん』は、主に生理、 病理、 衛生等の基礎医学的事項を論述して臓気法時論篇第二十二に、五穀為養(ごくういよう)、五果為助(ごかひじょ)、五畜為益(ごちくひやく)、五菜為充(ごさいふじょう)、気味合而服之以補益精気(きみあいじょふくしぜほせいえきき)との記載があり、食材についての解説は、
五穀:麦、黍、稗、稲、豆
穀類は主な食材として五臓を養う。
五果:スモモ、杏、大棗、桃、栗
果物は五臓の働きを助ける。
五畜:鶏、羊、牛、犬(馬)、豚[五畜=鶏・羊・牛・馬・豚)]
肉類は五臓を補う。
五菜:葵、藿、薤、葱、韭
野菜により五臓を充実させる。
多くの食材をバランスよく組合せることで身体の精気を補うことが出来ると解釈できます。食材によりそれぞれ対応の臓腑に特定の生理作用があることを経験的に認めてきました。
陰陽五行説は、中国の紀元前770年に周が都を洛邑(成周)へ移してから、紀元前221年に秦が中国を統一するまでの時代で春秋戦国時代ごろに発生した陰陽思想と五行思想が結びついて生まれた思想です。のちに五味五性、陰陽五行説とが結びつき発展を遂げてきたのです。
その代表的な思想として陰陽説と五行説として陰陽五行説が生まれています。食材が「五味」とし、木=春=酸味=肝、火=夏=苦味=心、土=梅雨=甘味=脾、金=秋=辛味=肺、水=冬=塩辛味(鹹味:かんみ)=腎となります。五行は、五味五性ほか方向(東南中西北)、時季(春・夏長・夏・秋・冬)、五気(風暑湿燥寒)、五臓(肝・腎・心・肺・脾)、五腑(胆胃小腸大腸膀胱)、五官(目舌口鼻耳)などがあります。
五味五性、陰陽五行説を考え合わせて体調のバランスを整えていくこと、それぞれにあった食事を処方することになります。
東洋医学では自然界の全てを木・火・土・金・水の5つの要素に分類します。
それらの相互作用によって生じる健康維持の働きを説いた理論が五行説です。
食養生のなかに、食材を五つに分類し、それぞれ味の性質を生かして調理するという方法があります。
さまざまの食材をバランスよく組合せることで身体の精気を補うことが出来るとの解釈のもとに発展してきたようです。
その中の今回は、五畜としての鶏、羊、牛、犬(馬)、豚についての解説となります。遊牧民のモンゴルでは、ウマ、ウシ(ヤク)、ラクダ、ヒツジ、ヤギを家畜とし厳しい気象条件下ので遊牧が適していました。ブタ、ニワトリは入れていません。
5畜は、頑強で運動能力が高く、粗食に耐えるということから食肉、乳製品の食用に、毛皮など、複数の用途に利用し用いてきました。遊牧民は、これらの家畜を肉、乳製品、毛や皮から衣類や道具を作ったりして自家消費ほか、商用としても肉用の家畜やカシミヤ、羊毛、ラクダ・馬の毛、皮革などで売買により収入を得てることもあります。
日本人になじみのある五畜としての鶏、羊、牛、馬、豚について、中医学的考えに基づいて、
鶏肉・羊肉・(鹿肉)は体を温め、馬肉は体を冷やし、豚肉・牛肉は体温に影響を与えないといわれます。これらの肉の特徴について触れると、
◇
鶏:韓国料理のサムゲタンは、1羽丸ごと使い中に香味野菜、もち米などを詰めよく煮こんだもので薬膳として知られます。
中国料理では、内臓はもちろん、とさか、足まで料理に利用しています。“鶏を割(さ)くに牛刀(ぎゅうとう)を用う”のたとえが、小さいことを処理するのに大仕掛けの手段を使うことということです。
他の豚、牛肉に比べ消化がよく、脂肪は、筋肉中に少なく皮下におおく融点が23~40℃で淡黄色をしてビタミン類に富みます。
◇
羊:成吉思汗料理となった由来は、蒙古の野戦料理であり鉄兜を鍋にして羊の肉を料理していたのがが定かではありませんがす中国に伝わり鉄の網焼きの拷羊肉(カオヤンロー)になって日本に伝わったといわれています。
明治時代に北海道で羊(ウシ科)の飼育が始まり料理も定着していき現在に至っています。現在では、衣服としての羊毛が合成繊維に押され激減傾向です。鶏肉と共に体を温めるといわれる羊肉、寒さから身体を温めてくれそうです。
◇
牛:肉質は常温では、腐敗しやすくそのため氷結点ー1.7℃前後で1~2週間、冷却、凍結冷蔵の方法が取られます。屠殺後、死後硬直を起こしてのち軟化熟成(エージング)して味に特有の旨みが増してきます。
牛脂の融点は、40~50℃、筋の多い基質部分には、コラーゲンを多く含み、部位に合った調理法を選ぶのがよいでしょう。軟らかいヒレ、ロースは、すき焼き、ステーキ、ローストビーフに、肩もも肉は、バーベキュー、炒め物、揚げ物、味噌漬け、粕漬け、佃煮に、堅いすね肉は、挽肉にしハンバーグ、そぼろ煮、スープ、煮込み料理に、冷製料理には、脂肪の少ないもも、ひれ肉を利用しています。
◇
馬:食用には、生後3~5年飼育したものでグリコーゲン、リノレン酸が多く脂肪の融点が30℃前後で溶け、牛脂より溶けやすく鑑別に利用し、脂肪は霜降りとはなりません。すじが多く臭みがあり、熱を加えるとより臭気を強く感じ、煮沸によって泡立ちがみられ硬いがアミノ酸組成は牛肉に似ています。脂肪がやわらかく甘味があり新鮮なものは寄生虫が少ないとして馬刺し、桜鍋、もも肉の燻製として賞味しています。
馬刺しとしても食べられている馬肉は身体を冷やすとか、この寒い季節には加減して摂食した方がよいかもしれません。
◇
豚:屠殺後、死後硬直を起こしてのち軟化熟成(エージングAging)して味に特有の旨みが増すが常温では、腐敗しやすくそのため1~3℃前後で3日~1週間、冷却、凍結冷蔵の方法が取られます。
中国では、肉以外にも足、舌、耳、内臓(肝臓〈レバー〉:鉄分13.0mg/100g中)とすべて余すところなく食用としています。牛肉に比べ寄生虫の心配があるので必ず加熱調理し、。焼き肉(肩ロース)、炒め(バラ肉)、煮込み(肩肉)、揚げ物(ロース・ヒレ)、しゃぶしゃぶ(ヒレ)、蒸しもの(肩ロース)、汁物(バラ肉)にします。
一般に飼育日数が増えると味は濃厚になって旨味を増すが肉質が硬くなります。牛肉と共に豚肉は、特に体温に大きな影響を及ぼさないということで、年間を通して食べられます。
多くの食材をバランスよく組合せることで健康を維持につながります。穀類は体を養い(五穀為養)、果物は体の働きを助け(五果為助)、肉類は体を補い(五畜為益)、野菜は体を充実させ(五菜為充)、バランスよくあわせ精気を補い強められる(気味合而服之・以補益精気)のです。
「陰陽五行」、五味と五性を知ることで、その食材の特徴を季節ごとに料理の味付けに生かします。
多くの食材 をバランスよく組合せることで身体の精気を補うことが出来ると解釈できます。陰陽は、宇宙に存在するあらゆる事象を 「陰」と「陽」に当てはめた中国古来の哲学で、 全ての事象は、単独ではなく、相反する形で存在し、1年で春分の日をゼロとした場合、夏至には「陽」が極まるが、秋分には戻り、冬至には「陰」が極まって、やがて春分を迎えるをくりかえすという考え方になります。
陰陽説と五行説を組み合わせて、「陰陽五行説(論)」、 基本は、木、火、土、金、水、(もく、か、ど、ごん、すい)の五行にそれぞれ陰陽を配します。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸(こう、おつ、へい、てい、ぼ、き、こう、しん、じん、き)、訓読みでは(きのえ、きのと、ひのえ、ひのと、つちのえ、つちのと、かのえ、かのと、みずのえ、みずのと※かのえ、かのと、は金を指す)となります。
陰陽は語尾の「え」が陽、「と」が陰。語源は「え」は兄、「と」は弟。「えと」の呼び名はここに由来するもので、「きのえ」、は「木の陽」という意味です。
旧暦では、これを十二支と組合わせており、季節に対応する五行(五時または五季で)は、春が木、夏が火、秋が金、冬は水としました。土は、四季それぞれの最後の約18日(土用)を指します。
また、西洋的な考え方が取り入れられる以前の方角、時間の表し方の概念なども、これを元にして作られたものと言われ、わが国でも、長らく使用してきました。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。