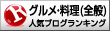・被子植物Angiosperms ひししょくぶつ
APG体系 (エーピジーたいけい)は、1998年に公表のあった被子植物の新しい分類です。
APGすなわち被子植物系統グループAngiosperm Phylogeny Group とは、この分類を実行する植物学者の団体名でした。この分類は特に命名がなく、単にAPG体系やAPG分類体系などと呼ばれます。特に葉緑体DNAの解析から、被子植物の分岐を調査する研究は近年飛躍的に進み、学術先端分野ではAPGの体系に移行しています。
APG体系以前の分類法の新エングラー体系modified Engler system又はupdated Engler system(1953年及び1964年)やクロンキスト体系Arthur Cronquist(1981年)がマクロ形態的な仮説を根拠に1つまたはそれ以上の命題から論理法則に基づいて結論を導き出す思考の手続で演繹的(えんえきてき)に分類体系を作り上げました。
クロンキスト体系Arthur Cronquist(1981年)は、表現型を基にした学術分野における中心的地位を占めるようになりました。
1990年代以降は、進化系統を直接的に反映するとしたミクロなゲノム解析による分類の研究が進みAPG植物分類体系が将来的に一般化する分類法とし整備がおこなわれています。実証的に分類体系を構築するものであり、以前の体系の表し方とは根本的に異なる分類手法です。
APG I:APG分類体系の初版は1998年に公表、固有の名称はなく当初は APG system などと呼ばれ、現在では区別のためにAPG Iとしています。
被子植物の下位分類は1990年代以降、被子植物の進化の初期に、原始的双子葉植物群が分岐し、次いで単子葉植物が分岐したとしています。残りが単系統群の真性(真正)双子葉植物Eudicotsを形成します。
双子葉植物はまとまった一群ではなく側系統群、単子葉植物はまとまった一群と見なせると思われます。
APG II:第2版で2003年に公表しています。主要な変更点は2点あり初版で分類未確定としていた多くの分類群タクソンTaxonを大きな科にまとめ、あるいはより細かい科に分類してもよいとしました。
APG III:2009年に第3版とし公表がありました。変更点は単子葉類の位置を修正、モクレン類に近縁ではなく真正双子葉類の側に近縁です。ナデシコ目などのコア真正双子葉類基部の多分岐を大きく修正したものです。ナデシコ目はキク類の姉妹群になっています。第2版では、一部の科で広義狭義どちらでも良いとしていましたが、この範囲を確定しました。
アンボレラ目、スイレン目、センリョウ目、サクライソウ目、マツモ目、ツゲ目、ヤマグルマ目、ハマビシ目、フエルテア目、ピクラムニア目、ブドウ目、ベルベリドプシス目、エスカロニア目、パラクリフィア目、ブルニア目を新設しました。
APG IV:2016年、第4版APG IVを公表しました。体系の大まかな概略はAPG IIIを踏襲(とうしゅう)していますが、いくつかの点で変更があります。ムラサキ目、ビワモドキ目、クロタキカズラ目、ペラ科など9科の新設がありました。
ウマノスズクサ科に旧カンアオイ科・旧ヒドノラ科・旧ラクトリス科を包括させ、サンアソウ科に旧アナルスリア科・旧カツマダソウ科を包括させ、ツゲ科に(旧ハプタントゥス科を包括しています。
学名に関しては、旧ススキノキ科の代わりに「ツルボラン科」、旧メリアントゥス科・旧ウィウィアニアス科の代わりに「フランコア科」を使用することになっています。
この結果、目の総計は64に、科の総計は416にそれぞれ変更しています。
二つの主な(非公式の)クレードとして、バラ上群Superrosids とキク上群Superasteridsの追加があり、それぞれ バラ類(rosids) と キク類(asterids)の上位クレードを構成することになりました。
被子植物Angiospermsの分類では植物界Plantaeのうち被子植物Angiospermsと裸子植物Gymnospermに分けられ裸子植物と対をなす分類群です。
植物の分類の主要な1グループ名であり種子植物の顕花植物のうち、一般に花と呼ばれる生殖器官の特殊化が進み胚珠が心皮にくるまれ子房の中に収まったものです。このことから被子植物と呼ばれ心皮が発育し果実となります。
被子植物の分類法は近年DNAの解析が飛躍的に進化し修正を重ねてきています。
最初の被子植物は、1億4000万年前のジュラ紀に裸子植物から又は、もっと以前の三畳紀に分化したともいわれます。
現在確認している最も古い被子植物の化石は、ジュラ紀から白亜紀に入る頃のアルカエフルクトゥスArchaefructus(古果)といい、これは水中生活に適応して特殊化し、花がよくまとまらず1つの枝のように見えるといいます。
被子植物は、白亜紀以降に繁栄しています。
各枝に現存種が残っているような被子植物の系統樹における最初の分岐は、主系列からのアンボレラ目Amborellalesの分岐がみられています。
順次にスイレン目Nymphaeales、コショウ目Piperales、モクレン目Magnoliales、クスノキ目Lauralesなどの分岐を示しています。この後における主系列は、単子葉植物群の派生がみられます。
1980年代以前の標準的な分類法は、新エングラー体系であり、この分類体系は直感的で分かりやすいため、市販の図鑑等に現在でも広く使われてきました。
その後にクロンキスト体系(Arthur Cronquist:1981年)が登場し、表現型を基にした学術分野におけるデファクトスタンダードの地位を占めるようになりました。
1990年代以降は、進化系統を直接的に反映するとしたゲノム解析による分類の研究が進みAPG植物分類体系が将来的に一般化する分類法とし整備しています。従来の分類法と異なる点が多く、従来の目・科が廃止ないし統合した例が多くに見られます。
代表的な被子植物を種が多い順に代表的な科を挙げるとキク科 25,000種(キク目Asterales・キク類・キク目)、マメ科 17,000種(マメ目Fabales)、ラン科15,000種(単子葉植物綱 Liliopsida・ラン目 Orchidales)、イネ科9,000種(単子葉類Monocots・ツユクサ類Commelinids・イネ目Poales)、トウダイグサ科7,500種(バラ類Rosids・キントラノオ目Malpighiales)、アカネ科6,000種(リンドウ目Gentianales)
などです。 近年では、表現型による上記各体系に代わりAPG体系が標準となりつつあるようです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。