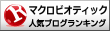・食事前のお口の体操 Mouth exercises before meals しょくじまえのおくちのたいそう
高齢になってくると足腰に不調が感じられてくると同様に、体全体にさまざまの異変が感じられてくるようになります。今回は、食べることで口腔のケアOral care、口の中のお手入れの中でも、お口の体操に着目しました。口腔機能を維持していくためには、口とその周りの筋肉のトレーニングが必要です。嚥下体操、唾液腺マッサージ、口腔周囲筋ストレッチ、パタカラ(口中体操)などがあります。
嚥下体操は、飲み込みをよくするための一連の動作を行うことです。食べ物、飲み物が、スムーズに食道へ送り込むための筋肉の体操です。頬(ほほ)、舌、喉(のど)の筋肉が使われることは、すぐに想像できます。食べるための動作は食べるための筋肉をトレーニングする体操です。実際には体全体の筋肉も大きく関係しています。目で食べ物を認識し、箸やスプーンを持ち次に手を伸ばして食器を持ち、食べ物を取り、口まで運びます。この時、手だけではなく、頭を支える首や肩の筋肉、腕や肩の筋肉がスムーズに連動して動くことで一連の動作を行っています。姿勢も大事な要素、「むせる」という動作には、背筋や腹筋、そしてしっかりと足を地面につけてふんばる足の筋肉なども必要になるのです。嚥下体操には、からだの筋肉を動かす要素も含みます。
嚥下体操を続けていくことは、食べるための筋肉のトレーニングだけではなく、笑顔をつくることや、楽しくおしゃべりをすることにもつながります。 これは、使っている筋肉がほとんど同じといえます。筋肉は、動かすほどリハビリになり、バランスよく協力し合う動きへと改善します。
嚥下体操は次の9つの項目で構成します。
- 姿勢を整えて座り、全身の筋肉バランスを整えます。
- 深呼吸は鼻から吸って、口から吐きます。長く息を吐くようにしましょう。
- 首の体操筋肉をゆっくり動かして筋肉をほぐすことで、食べる準備を始めます。嚥下に関係する筋肉は、首に多く集中しています。
- 肩は息を吸いながら肩を引き上げて、スッと力を抜くように息を吐きながら肩を下げます。
- 口の周りの筋肉をほぐし、動かすためのトレーニングです。口を大げさに動かします。
- 頬は口の中に空気をいっぱいにして、頬を内側から膨らませます。噛むこと、食べこぼし防止や、鼻へ食べ物が流れ込むのを防ぎます。
- 舌は、手で引っ張るぐらいに口の外に伸ばします。咀嚼時、飲み込みの時に舌の動きを保つことができます。そして発音にも欠かせない舌です。
- 発音練習によって「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音することで、唇や舌を動かします。唇、舌の動きを目的別にトレーニングできます。
- 咳ばらいも有効です。むせるのを防ぐためのトレーニングです。無理をしないで2~3回程度します。
唾液腺マッサージは、高齢になると、だ液は出にくくなります。おしゃべりの機会が少なくなったりすると、ますます口腔乾燥は進んでしまいます。食事前のブクブクうがいや、保湿剤の塗布などいくつかありますが、だ液腺マッサージも、その方法のうちの一つです。. 食べること、飲み込むことや、会話がしやすくなります。だ液腺は口腔内に3ヶ所あります。
耳下線(じかせん)は上あごからサラサラしただ液の分泌を、すっぱいものを想像しながら行うとよいでしょう。
顎下線(がっかせん)と舌下線(ぜっかせん)は下あごから少し粘り気のある食べ物をまとめるためのだ液の分泌を促します。おのおの5回程度は行うとよいでしょう。
口腔周囲筋ストレッチには唇やほほ、舌、あごなどが含まれます。高齢になるにつれて、口の働きは低下します。加齢および疾患による障害やまひなどで身体が動かしづらくなり、人との交流の機会が減り、笑うことやおしゃべりすることが少なくなって行く傾向です。むし歯や歯周病により歯を失ってしまい、柔らかいものばかり好んで食べるようになると、口のまわりの筋肉はますます動きにくくなってしまいます。食べたり、飲んだりすることが難しくなってきてしまうのです。口腔周囲筋ストレッチは口の働きの改善や誤嚥性肺炎の予防にもつながります。
舌の訓練は顎(あご)の下を親指で押すことにを舌下腺も刺激できます。舌には口に入った食べ物をまとめる、食べ物を左右の奥歯に運ぶ、そして飲み込むための重要な役割をしています。
唇(くちびる)のマッサージは唇に力をつけ、食べ物を口に入れる瞬間の食べこぼしを防ぐ目的があります。上下を6箇所に分割してそれぞれ指でつまんで縮めたり伸ばしたりを繰り返します。舌や唇って意識しないと動かしたりさわったりしないところですので、マッサージの習慣づけるようにしましょう。
顔全体のフェイスマッサージは口の周りや顔全体の筋肉を両手を使い動かしマッサージします。
パタカラ(口中体操)は発声しながら口を動かす、「口の体操」のことです。「パ」「タ」「カ」「ラ」の4文字を発声するため、「パタカラ体操」と呼ばれます。
「パ」の音は、口をしっかり閉じて発音することがポイントです。口をしっかり閉じる筋肉が鍛えられることで、口の中の食べ物をこぼさないようにすることができます。
「タ」は、舌を上あごにくっつくように発音する「タ」の音は、舌を上あごにくっつくように発音しましょう。下の筋肉が鍛えられると、食べ物をしっかり押しつぶしたり、飲み込んだりすることができます。
「カ」は、のどの奥を意識して発音します。のどの奥を意識して発音し喉の奥に力を入れ、一瞬呼吸を止めることで、食べ物を飲む込む動作ができます。のどを閉じることで、誤嚥を防ぎ、食べ物を食道に送ることができるようになります。
「ラ」は、舌をまるめるように発音します。舌をまるめて発音することを意識し、食べ物を喉の奥に運び、飲み込みやすくなります。
「一文字一文字」「はっきりと」意識して声に出すようにすることが重要です。食前が効果的です。
「パタカラ体操」は、お食事の前に行うことをオススメします。運動前の準備体操と同じで、実際に食べる前に体操しておくことで、口や舌の動きが慣れて食事しやすくなります。
「パタカラ体操」には、誤嚥以外にも、1.咀嚼(噛む)、嚥下(飲み込む)機能が維持、向上する。2.唾液の分泌が促進される(ドライマウスの防止)。3.いびきや歯ぎしりの改善。4.発音がはっきりし、口が動きやすくなる。5.入れ歯が安定する。6.口呼吸から鼻呼吸になり、口臭が改善。7.表情が豊かになり顔のたるみなどのアンチエイジングにもよい。
トレーニングにより、食べる機能を高めます。「パ」は食べ物の取り込み、「タ」は送り込み、「カ」は飲み込み、「ラ」は食塊形成の機能を高めます。高齢者だけでなく実際に食べる前に体操しておくことで、口や舌の動きが慣れて食事しやすくなります。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。