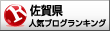★【卑弥呼】のルーツ(籠名神社祝部氏系図/『先代旧事本紀』系図)は日本の歴史、つまり日本の「古代史」(推古天皇時代頃から奈良時代=AD710年頃迄・それ以前は文字無し時代とする)の範疇では捉え切れません。従って、当研究は世界史に於ける「地理歴史」(後漢書時代は地理志・表記/古代ギリシア時代は・地理誌と訳されている)と位置付けています。その「地理歴史」への切口となるのが『三国志』の「西域伝」(裴松之・著)であります…
…
既に連絡済みの知人(ホツマ研究グループ/教師・高槻名誉市民を語り継ぐ会会員)が、昨日(2024/11/08・金曜)の昼過ぎに来られました。それは私の研究(日本語の始まりとヤマト国家創建思想ルーツ解明)を引き継ぐ事に関連し、その全ての資料を受け取る為でした。つまり、私の研究の必須的目標であった歴史上の人物(卑弥呼)をホツマツタヱ文書記載の世襲足姫(ヨソタリヒメ)として、それを三国志「倭人伝」の注解【魏略】の中に見つけた内容(天竺 ⇒ 復立卑弥呼)を、本として出版する為でした。
…
因みに、卑弥呼が何故ヤマトの国では「世襲足」と表記されたのかと言えば、「初代・卑弥呼」(老齢/後漢の桓帝と霊帝の治世AD147~189年頃の女性)の世襲だったから【ヨソタリ=世襲足】と表記し、その人物は我が国最古の系図として国宝に指定された元伊勢「籠神社」所有【籠名神社祝部氏系図】と、【籠名神官祝部丹波国造海部直等氏之本記・系図】に記載されています。そしてその元典は日本人の聖書として書かれた『ホツマツタヱ』(神武天皇条/系図は先代旧事本紀に因る尾張氏の系図)でした。
その研究の始点と成ったのは私が3歳時(昭和25年=1950年)の事。つまり、我が一家は夜逃して辿り着いた伊万里の塩浜海岸際の叔父(焼塩製造兼瓦製造者)の家で、初めて迎えた夏の或る朝の出来事(昭和25年夏/『ハマボウの花の花の下で』より~ https://erusaremu4654.jugem.jp/?eid=2 ・ ⇒ クリック検索)に起因します。因みにその海岸とは、下段の 白黒写真(伊万里湾・川南造船所の南側に位置す川南造船・塩浜住宅と追﨑の高尾ノ鼻との間に位置す小さな港的な塩浜海岸)の右端に位置す小さな港です。
…
然し、戦後(大東亜戦争)の昭和25年頃は、県道拡張工事(現在の国道204号線)で叔父の家は立ち退きを宣告されていました。そんな或る日(小学3年/昭和31年・夏)、学校の家庭訪問で早く授業を終え、先生を道案内し家に帰ると県道拡張工事関係者の人が我が家に来て、叔父が家の際に植えていた3本の木(毎年、夏には美しい黄色い花を咲かせてた木/現在は佐賀県指定の絶滅危惧種)が切り刻まれ捨てられていたのを見て悲しくなりました。つまり、3歳時に初めて見た黄色い花の美しさに感動し、花の呼称を母に訊くと、唯「木の花」言言い、誰も知りませんでした。それで、では誰が「キ=木と名付けたか」を執拗く訊くと、挙句の果てには「名付けた昔の人に訊いてこい」との母の返事であった。そんな母との言葉のやり取りの中でわたしは「言葉の不思議さ」を感じていました。それで日常的に話している言葉は誰が考えてつくったのかを、私は死ぬ迄には必ず見付けだしてみせると我が胸に刻み込みました。
…
そして、仕事の合間の休みを利用し資料を集め、ヤット、その研究内容を本に纏め出版する準備の処(77歳)へ行着いた次第です~(画像をクリックすれば戦時中の川南造船所の画像は少し大きく見れます)。
★浜辺の画像(ハマボウの木と花)は、叔父が植えた3本の木の花の種が「川南造船所・事務所跡地」の東海岸に流れ着いて咲いていた花を、帰郷した時に撮った写真です。現在は佐賀県指定【絶滅危惧種・塩生植物】の立て看板が、事務所跡(玄関前)に設置されています!
…
「復立・卑弥呼」(世襲・卑弥呼=【世襲足)の祖先「伊存」(後の神武に当たる)一行と、別働隊(クムラン秘儀教義宗団)の移動ルートは陸路と海路に分れ、徐福が出港したとされる会稽(カイケイ)で合流し、有明海北西部に上陸しました。

…
…【ランキング】 → ↓ ↓ ← (クリック)お願いします~
…
…