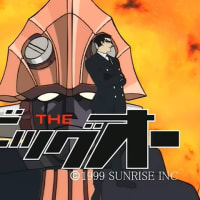京都を代表する和菓子の方です。池などの上に設置される木製の橋のことではありません。なお、鳥取にあるのは八頭です。
京都のお土産物として現地での一押しとも言えるくらい、店頭に並んでいる観光土産であり、統計調査では京都観光の土産として菓子類を購入する人は96%、そのうち八ツ橋の売上は全体の45.6%(生八ツ橋24.5%、八ツ橋21.1%)を占め、京都を代表する土産物になっています。
なお、京都には「京都八ツ橋商工業組合」と呼ばれる組合があり、製造業者として14社が登録されています。さらに、それぞれが「本家」「元祖」「総本店」「總本舗」などを名乗っているため、京都経験値の低い私にとっては、混乱を来すばかりです。
さて、すでにニュースになっていますが、老舗大手・井筒八ッ橋本舗(井筒)が、ライバル社の聖護院八ッ橋総本店(聖護院)に、創業を1689年(元禄2年)とする表示の使用禁止と、600万円の損害賠償を求める裁判を京都地裁に起こしました。井筒は「創業年が事実と違い、そのころに八ッ橋は存在しなかったはず」と主張。聖護院は「提訴は驚くばかり。対応を検討する」としています。
井筒は、「創業年がでたらめだ。業界全体への影響が大きく、やめてもらいたい」と言っています。聖護院はのれんや看板などに、「創業元禄二年」「since1689」と記していますが、当時、八ッ橋が作られていたとする文献はなく、八ッ橋を320年以上作っているように客や取引先を誤認させていると主張しています。聖護院が1969年、創業の由来を同業者に説明した文書では「正確な創業年は『不詳』」とされていたとも指摘しています。ちなみに、井筒は1805年(文化2年)創業とのことです。
そもそも、八ッ橋は、江戸初期に活躍した近世箏曲の祖・八橋検校(やつはしけんぎょう)さんをしのび「琴の形状を模した干菓子」とする説、愛知県の寺の「伊勢物語」第九段「かきつばた」の舞台「三河国八橋」にちなむとする説などがあり、いつ誕生し、いつ八ッ橋と名づけられたかは確定していないとされています。
聖護院では、江戸中期1689年(元禄2年)に、聖護院の森の黒谷(金戒光明寺)参道の茶店にて供されたのが八ッ橋の起源とする説を唱え宣伝にも用いているそうですが、八ッ橋がこの時代に作られていたとする文献はないそうです。
井筒によると、聖護院は10年ほど前から創業年を強調した表示を開始。井筒も加盟する業界団体「京名菓八ッ橋工業協同組合」が昨年5月、聖護院に根拠のない表示の中止を求め、京都簡裁に調停を申し立てた。聖護院は「民事紛争に該当しない」と訴え、調停は不成立に終わっており、今回の裁判につながっていると思います。
ちなみに、「生八ッ橋」は戦後に考案されたものです。
なお、私は八ッ橋はちょっと苦手でして、生八ッ橋を1つ戴いてお終いです。
本家西尾八ッ橋:元禄年間に聖護院の森の黒谷参道に八ッ橋屋梅林茶店として創業し、1689年(元禄2年)に八ツ橋の原型が誕生。文政七年に熊野神社に奉納された絵馬には「八ッ橋屋為治郎」の名が残る。
聖護院八ツ橋総本店:1689年(元禄2年)に聖護院の森の茶店として創業し、八ツ橋の製造販売を開始。
聖光堂八ツ橋總本舗:1850年(嘉永3年)の創業と同時に八ツ橋の製造販売を開始。
おたべ(株式会社美十):1957年(昭和32年)から八ツ橋製造を始めた。餡入り八ツ橋「おたべ」は1966年(昭和44年)から製造を開始し、新顔ながら一大勢力となる。
八ツ橋屋西尾為忠商店:本家西尾八ツ橋と分かれてできた銘柄。完全手作業製造・梱包、添加物無添加で、3軒の直営店だけでの販売を行う。餡入り八ツ橋が4角形で、通年販売は一般的な餡入りと抹茶餡入りだけであることも特徴。
井筒八ッ橋本舗:1805年(文化2年)創業。井筒八ツ橋や、水上勉の小説『五番町夕霧楼』の主人公から名を採った餡入り八ツ橋「夕子」で知られる。