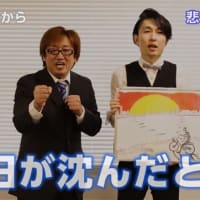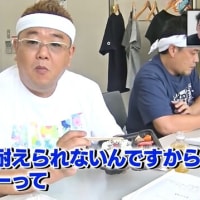そもそも、「年金」とは一体どういうものなのでしょうか。歳取って、おじいちゃん、おばあちゃんになったら国からもらえるお金、くらいのイメージを持っているかもしれません。
早い話が、年金とは「年金保険」ともいい、保険の一種です。現役時代の保険料を支払い、その保険料を原資として将来の一定期間受け取るというものが基本です。代表的なものが「公的年金」と言われる「国民年金」やサラリーマンが加入する「厚生年金」などに当たりますが、これ以外にも様々な年金があります。国が運営するもの以外でも民間の保険会社が提供している年金(私的年金保険)という金融商品も存在します。
年金は基本的に支払った保険料を保険会社(国)に預けてそれを運用してもらいながら、最終的に年金が必要な時期(老後)にこれまで預けてきた保険料+運用益を原資として年金として受け取る形になっています。
年金に関しては年金制度は大きく「積立方式」と「賦課方式(ふかほうしき)」の2種類があります。
積立方式:自分が支払ってきた保険料+運用益を受け取る方式です。民間の保険会社における私的年金などはこの方式が取られます。自分が払った保険料で自分の年金がつくられるので、世代間の不公平感がでない一方で、インフレに弱いという問題点があります。
賦課方式:今支払われた保険料は別の誰かの年金に充てられる方式です。公的年金はこの方式が取られています。インフレに強いというメリットがあるものの、その一方で少子化には弱い制度となっています。現在は少子高齢化が賦課方式となっている公的年金制度に暗い影を落としているといえます。
年金は現役時代に「保険料(年金保険料)」を支払います。そして、一定の年齢になることで満期を迎え、以後は「年金」を受け取ることになります。たとえば、国民年金の場合、20歳から60歳までの40年間保険料を支払います。そして、年金は65歳以降は死亡するまで毎月受け取ることができるようになります。ただ、この支払期間と受け取り期間については保険によって異なります。
さて、5月のことですが、シアトル・マリナーズのイチローさんが、チームとスペシャルアシスタントアドバイザーとして契約を結び、今季の残り試合に出場しないことを発表しました。これは現役引退を意味するものではないものの、選手としてのキャリアにひと区切りがついたことは事実です。
日本のプロ野球の場合ですと、大物選手のセカンドキャリアは監督やコーチへの就任、解説者などメディア関連の仕事に就くのがよくあるパターンです。一方、MLBでは、ほとんどの選手は悠々自適のセカンドライフを送っています。それが可能なのは、現役時代のとてつもない額の年俸ですが、充実した年金制度もあります。
現在のMLB年金制度では、43日以上のメジャー登録があれば受給資格が発生します。シーズンを重ねるごとに受給額も上がっていき、10シーズンで満額支給です。支給年齢は一般的に62歳から(前倒しも可能)で、もちろん生涯年金であり、死去するまで支給されます。そのうえ、一般的な年金のように積立金は必要ではありません。
支給額はメジャー歴10年以上の選手ならば最高で年間21万ドル(約2300万円)です。ちなみに、日本人で10年以上の満額支給の資格を得た選手となると、イチローさん、松井秀喜さん、野茂英雄さん、大家友和さんの4人しかいません。
メジャー歴9年であと一歩で満額に届かなかったのは、上原浩治選手(現;読売ジャイアンツ)と、マリナーズなどで活躍した長谷川滋利さん(現;オリックスバファローズのシニアアドバイザー)です。なお、5月にマイアミ・マーリンズを自由契約となってしまった田澤純一選手が今季でメジャー9年目を迎えています。
日本人選手の場合、大谷選手らのように若いうちにMLBへポスティングシステムで移籍でもしない限り、海外FAで移籍している限り、年齢的なこともあり、20代後半から30歳にかけてのメジャーデビューから10年間に渡って現役を続けるのは難しいでしょう。
松井さんも10年目のシーズンはマイナー契約からスタートしてメジャー昇格を果たしたものの、途中でリリースされましたが、この10年目は年金受給額の上では重要なシーズンだったでしょうし、上原選手が、今年、これだけこだわった理由の一つにもあるように思えます。
ちなみに日本のプロ野球でも年金制度がありましたが、選手たちから一定の積立金を集めて運用益から支給するという仕組みでした。しかも、約束の運用益を実現できず、事実上の破綻状態となってしまい、現在は制度自体がありません。