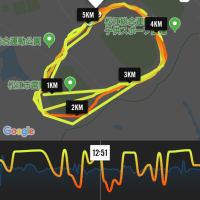生保8グループ 8年ぶり増収 医療、年金が押し上げ (産経新聞) - goo ニュース
国内生保と外資系生保の決算発表から、保険料収入は前年同期に比べ0.8%と増加し、保険料が前年を上回るのは8年ぶりらしいです。
テレビ等での大量のCMも影響してか、医療保険やがん保険が顕著に推移したことと、銀行での窓口販売による個人年金の販売が順調な事が貢献しています。大半の方が長生きのリスクに備えて来た事と、保険各社の戦略が近づいた事の表れかも知れません。
自分が貰える(リスクが起きたとき)医療保険等は延びていますが、反対に死亡保障は前年に比べ5%減少しています。また、保有契約の減少は9年連続らしいです。それに伴い個人が契約している死亡保険の平均保障額が、15年ぶりに1000万円を下回りました。従来の生計主体者中心の保険設計から、入院したり手術したりすれば給付金が支払われる医療保険にシフトしています。
死亡リスクより長生きのリスクへ変わりつつある背景には、晩婚化や少子化の進行なども影響しているようです。当然、未婚であれば死亡リスクを余り考慮する事もないですし、子供が少なければ、死亡時の必要保障額も少なくて済みます。従って自分個人の長生きのリスクへの備えを重視する人が増えるのも頷けます。
今まで、FPが死亡保障額を考えるときに、いつも第一に考える制度が有ります。それは、民間での生命保険に未加入でも生計主体者が万が一の時に、残された家族には支払われる遺族厚生年金が有ります。この遺族厚生年金をベースに、幾ら万が一の時に入るお金と出るお金を計算するのですが、来年(平成19年4月以降)より少し事情が変わります。
簡単に説明しますと、子供がいるかいないかで大きく異なります。平成16年度の年金改正で、子供がいない場合大きく変更になりました。①夫死亡時30歳未満の配偶者は、遺族厚生年金は5年間しか貰えません。そして妻が65歳になって老齢基礎年金が支給されます。②夫死亡時、30歳~40歳未満の配偶者の場合は、妻が65歳まで遺族厚生年金、65歳時から+老齢基礎年金の支給となります。③夫死亡時、40歳以上の配偶者は従来通りに65歳までは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算、65歳から遺族厚生年金+老齢基礎年金と経過的寡婦加算が支給されます。以上、夫死亡時の妻の年齢で大きく公的遺族年金が変わります。
先月(4月)のサラリーマンの消費支出は実質4.3%減少しています。此は、減少した支出のお金が貯蓄に廻ったのではなく、税金や社会保険料の支払いなど非消費支出を実収入からさし引いた可処分所得(自由に使えるお金)が減少したからです。以上のことを考え合わせ、生命保険と医療保険等は各家庭又は個人でしっかりした、お金の優先順位を明確にして、長生きのリスクと一定期間の万が一のリスクをバランス良く、ライフプラン(人生設計・生涯設計)を基に考慮する必要が有ると思います。

 | サラリーマンの家計簿「生命保険」「住宅ローン」「教育費」「投資」ここまで見直せる!実業之日本社このアイテムの詳細を見る |
国内生保と外資系生保の決算発表から、保険料収入は前年同期に比べ0.8%と増加し、保険料が前年を上回るのは8年ぶりらしいです。
テレビ等での大量のCMも影響してか、医療保険やがん保険が顕著に推移したことと、銀行での窓口販売による個人年金の販売が順調な事が貢献しています。大半の方が長生きのリスクに備えて来た事と、保険各社の戦略が近づいた事の表れかも知れません。
自分が貰える(リスクが起きたとき)医療保険等は延びていますが、反対に死亡保障は前年に比べ5%減少しています。また、保有契約の減少は9年連続らしいです。それに伴い個人が契約している死亡保険の平均保障額が、15年ぶりに1000万円を下回りました。従来の生計主体者中心の保険設計から、入院したり手術したりすれば給付金が支払われる医療保険にシフトしています。
死亡リスクより長生きのリスクへ変わりつつある背景には、晩婚化や少子化の進行なども影響しているようです。当然、未婚であれば死亡リスクを余り考慮する事もないですし、子供が少なければ、死亡時の必要保障額も少なくて済みます。従って自分個人の長生きのリスクへの備えを重視する人が増えるのも頷けます。
今まで、FPが死亡保障額を考えるときに、いつも第一に考える制度が有ります。それは、民間での生命保険に未加入でも生計主体者が万が一の時に、残された家族には支払われる遺族厚生年金が有ります。この遺族厚生年金をベースに、幾ら万が一の時に入るお金と出るお金を計算するのですが、来年(平成19年4月以降)より少し事情が変わります。
簡単に説明しますと、子供がいるかいないかで大きく異なります。平成16年度の年金改正で、子供がいない場合大きく変更になりました。①夫死亡時30歳未満の配偶者は、遺族厚生年金は5年間しか貰えません。そして妻が65歳になって老齢基礎年金が支給されます。②夫死亡時、30歳~40歳未満の配偶者の場合は、妻が65歳まで遺族厚生年金、65歳時から+老齢基礎年金の支給となります。③夫死亡時、40歳以上の配偶者は従来通りに65歳までは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算、65歳から遺族厚生年金+老齢基礎年金と経過的寡婦加算が支給されます。以上、夫死亡時の妻の年齢で大きく公的遺族年金が変わります。
先月(4月)のサラリーマンの消費支出は実質4.3%減少しています。此は、減少した支出のお金が貯蓄に廻ったのではなく、税金や社会保険料の支払いなど非消費支出を実収入からさし引いた可処分所得(自由に使えるお金)が減少したからです。以上のことを考え合わせ、生命保険と医療保険等は各家庭又は個人でしっかりした、お金の優先順位を明確にして、長生きのリスクと一定期間の万が一のリスクをバランス良く、ライフプラン(人生設計・生涯設計)を基に考慮する必要が有ると思います。