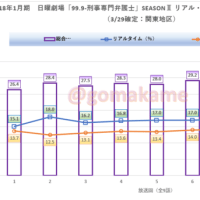編集委員 内田洋一 2016/5/16
多くの演劇人に愛された演出家、蜷川幸雄は意外なことに「理解されない」とうめきつづけた人だった。好意的にみえる劇評にも激しく怒って、周囲を戸惑わせた。自身が思う演劇の世界像はそれだけ侵しがたいものだったからだろう。30年余り前から取材を重ねてきたが、蜷川幸雄の内面はようとして知れなかった。その謎に迫ることで、演劇の闘士80歳の死を悼みたい。
【謎1】なぜアイドルを多用したか?
蜷川幸雄ほどアイドルタレントを重用した演出家はいない。芸術性を損なうと批判する批評家は少なくなかったが、高名になってからも「オレは芸術家じゃない、芸能人だ」とかたくなにその姿勢を貫き通した。
切符が売れる。コンサートで万単位の観客をひきつける華がある。厳しい選抜を勝ち抜いているから身体能力も根性もあり、短期間の稽古で伸びる。そうした興行上の実利はむろんあった。「小難しい芝居と思われると切符が売れないんだ」と役者の話題を前面に出すよう努めてもいた。が、真の理由はほかにあったのではないか。
偏愛したのは、スターの影だった。青春時代のアイドルはアメリカ映画のジェームス・ディーンであり、アンジェイ・ワイダ監督の名画「灰とダイヤモンド」のツィブルスキ。光り輝く寵児(ちょうじ)が転落する。光と影の振幅を極大化させる神秘的な力を演劇に持ちこみ、彫像を刻むように「時代」の像をとらえようとしたかに見えた。
1985年夏、私は蜷川幸雄にエッセーの連載を頼んだ。49歳、革ジャンでハーレーに乗り、稽古場で灰皿を投げまくっていたころだ。打ち合わせで「オレ、スターが好きなんだよ」と明かした蜷川は、ジュリー(沢田研二)について書いてきた。
「おそらく、彼らはほかのどの職業の人たちよりも短期間のうちにスターになり、人々の憧憬の眼差しをあびる。しかし失墜もまた急激にやってくるのだ。一夜にして彼らは売れない歌手になり、ときには侮蔑の対象とすらなる。人々にとって、スターというのはいつでも憧憬と侮蔑の対象なのだ。歌手たちはこの両義性のなかで、やがて世界の構造と人間の構造について知らされてゆくのだ。彼らが優れた表現者にならぬはずはない」(「ジュリー」)
- 藤原竜也が演じた8度目の「ハムレット」=写真 渡部 孝弘
この蜷川的スター主義は一般にいうスター主義とは似て非なるものだった。失墜の予感をはらみ、危うい綱渡りを自覚しているスター。物語をかきまわし、秩序をゆるがすトリックスター。その系譜には小栗旬、松本潤、藤原竜也らがいる。翼を太陽に溶かされ失墜するギリシャ神話のイカロスのようなはかなさ。そこに演劇の本質をみていたのではないか。
蜷川演出は劇の終盤に群衆の歓声、街頭の絶叫をよく響かせた。その中で処断されるスターの孤影。蜷川劇の名場面だ。歌謡曲や激烈な視覚効果の導入もスター同様、大衆の欲望の視線を喚起させるための仕掛けだっただろう。
が、この蜷川的スター主義は劇薬であった。東宝、次いでホリプロと提携して成功した興行モデルをビジネスチャンスと受けとめ、形だけまねる例が相次いだからだ。売れればいいとばかり、ゆるいタレントが大手を振って素人芸をみせる現状がある。美学なき安易な追随は蜷川演出の精神から最も遠いといえるだろう。
【謎2】なぜシェークスピアを日本化したのか?
桜吹雪、仏壇、声明、賽(さい)の河原、佐渡の能舞台……。シェークスピアやギリシャ悲劇に蜷川演出は日本の意匠をもちこんだ。映画界には、私淑していた黒沢明が「マクベス」を戦国時代に移す「蜘蛛巣城(くものすじょう)」というお手本があったが、演劇で試みたのは蜷川からである。
かつて新劇と呼ばれた近代演劇では、西洋人に似せるため鼻や金髪のカツラをつけて演じることが珍しくなかった。それを「恥ずかしい」と受けとめたのが原点。少年時代に親しんだ歌舞伎や人形浄瑠璃の演出を取り入れ、日本人の意識の古層にある記憶と結びつけることでドラマを普遍化しようとしたのである。
たとえば、仏壇を舞台にした「NINAGAWAマクベス」は、こんな偶然から生まれた。打ち合わせのあと埼玉県川口市の実家に寄った蜷川は仏壇にある父親の位牌(いはい)に手を合わせた。「親父、久しぶりに帰ってきたよ」。ろうそくをともし、チーンとならすうちにも考えが激流のように駆けめぐる。ああ、日本人はこうやって先祖としゃべるんだなあ。もし、仏壇の中に物語がそっくり入っていたら。観客は先祖の物語としてシェークスピアを見てくれるのでは……。日比谷の東宝演劇部にとって返し「仏壇、仏壇」とつぶやきながら階段を駆けのぼった。
「NINAGAWAマクベス」(1980年初演)の仏壇を舞台にしたセットの模型を喜ぶ
鋳物の町、川口で生まれ育った蜷川は「バカヤロー」をあいさつ代わりにする汗まみれの労働者を生涯忘れなかった。彼らを寝させてしまう芝居はやらないと誓い「開幕3分間が勝負」とばかり異次元に連れ去る冒頭シーンをつくった。引き落としなどの歌舞伎演出、人形浄瑠璃が重んじる装置の面白さなどを復権させたのは、それが日本人の感性に直結しているから。近代演劇の主流だった新劇は舞台の上部を使いきっていないと批判した蜷川はもともと画家志望だったのに加え、絵を重視する伝統演劇や宝塚に学んだ。結果、そのオリジナリティーは西洋で高く評価された。シェークスピアやギリシャ悲劇が思いもかけぬ手法で舞台化されていることに、西洋の観客は驚いた。
最後の最後までこだわり、もう一回やりたいと考えていた「ハムレット」。最後の演出(最多の8度目)は下町の長屋が舞台になった。夢幻能の様式を取り入れた光と闇の世界だった。車いすに酸素ボンベを積んでの鬼気迫る演出は西洋演劇の日本化という夢の集大成だっただろう。新劇は大衆から遊離し、西洋演劇を日本に根づかせることができなかった。対して蜷川演出はスターの力、演劇における視覚の力を復権させることでそれを成し遂げたといえる。
このとき(2015年1月)の病状はすでに深刻で、残された時間は多くないと本人は覚悟していた。稽古場でふりしぼる怒声を聞いているうち、激しく胸打たれた。世界を変えようともがき、闇の中を進む。ハムレットの苦しみは、政治の季節に変革を志した青年蜷川幸雄の苦しみそのものではなかったか。とりわけ思い入れの深い「ハムレット」で、ことに劇評をやり玉にあげたのも、むべなるかな。上演のたびに「わかってくれない」と闘志の火を燃やしていただろう。
最後の「ハムレット」では「演劇的転向」が告げられた。これまで心理の流れを重んじる新劇的なセリフを嫌い、説明しがたい衝動や叫びを重視してきた。が、今は一周まわって、逆にセリフの内容を確かに響かせる方向を目指したいのだと。かつてならヨシとした絶叫調のセリフであっても、内実をともなわないと感じれば、容赦ないダメを出した。
衝動的なセリフはもともと予定調和的なドラマを揺さぶる手段だった。ところが今や現実の社会生活で言葉が衝動的に発せられる。この傾向を進めれば、社会が思慮を失い、極端にふれる危険があると考えていた。「このごろセリフが気になってしょうがないんだ。今はきちんとセリフの内容を話してほしい」。蜷川演出が最後にたどりついた境地は「ハムレット」のセリフを借りれば「言葉、言葉、言葉」だった。
【謎3】「恥」の意識の源はどこにあったか
蜷川幸雄の軌跡をたどると「恥ずかしい」という意識が隠されていることがわかる。その源は唯一の自伝「演劇の力」(日本経済新聞出版社)の冒頭部に記されている。「ぼくは生まれつき自意識過剰で、ことあるごとに恥ずかしいという気持ちに襲われる」。皆に振り向かれるのがイヤだから、絶対遅刻しない。人に注目されるパーティーも嫌い。芸術祭大賞を受賞したら、自分をひきずりおろすためストリップの演出をした。
- 日劇ミュージックホールでストリップショーを演出する(1981年)
あえて自分を引き裂かれるような危地においこむ。40代から50代にかけての壮年期、わざと徹夜して意識をもうろうとさせ、アイデアがひらめくのを待った。この自己破壊衝動は通常の仕事についた場合、手ひどい失敗を招くものかもしれない。が、役者やスタッフの闘争心に火をつける演出という天職がこの衝動によって花開いた。怒りを創造のバネとした。
酒は飲まず、群れるのがイヤ。稽古が終わると家に飛んで帰る。木立に包まれた清雅な仕事部屋でお気に入りのオブジェやフィギュアに囲まれ、本を読んだりビデオを見たり。少年時代から引きこもる傾向があったというが、コミュニケーションの不得手な気むずかしい青年は演劇という場所があったからこそ生きられた。言葉を開く演劇の力を知っていたからこそ、高齢者劇団(ゴールド・シアター)や若手劇団(ネクスト・シアターなど)を輝かせることができたのだろう。
ゴールド・シアターのオーディションをぶらりと見に行ったことがある。うまくもない素人役者の寸劇にひっそりと、しかも延々つきあう蜷川幸雄がいた。あいさつすると「来たんだ」と不機嫌そうに、でもまんざらでもなさそうに言葉を返してきた。今はただ、その孤影を惜しむ。=敬称略