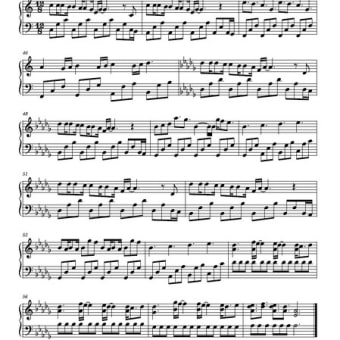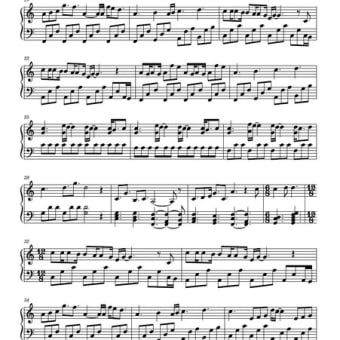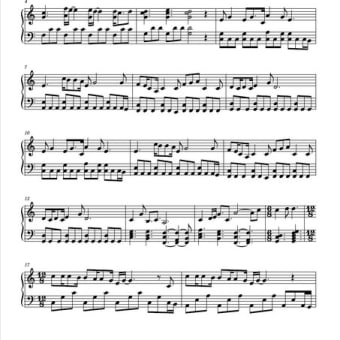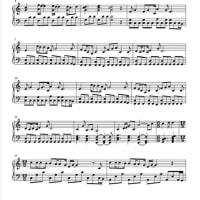私にとっては、将棋の羽生善治四冠=王位、王座、棋王、王将、だ。
もちろん、各界で活躍されている方は、みなそれぞれ
才能豊かではあるわけだが、
アスリート系は、どうしても、不断の努力が前面に出てしまいやすいし、
ビジネス系は個人が見えにくい。
芸術系も、小さい頃からコンクールめざしてがんばりました、
みたいな感じがする人が多い。
その点、羽生さんは、日頃の努力をほとんど感じさせない。
親兄弟も将棋関係者ではない。
まさに、突然現れた、天才=異能者なのだ。
棋戦で、戦う前の棋士のコメントが紹介されるが、
羽生さんのコメントはだいたいいつも同じ。
淡々と「はい、いつもどおりに戦います」
そして、いつもどおりに勝つ。Cool だ。
将棋の内容も、素人なのでよくわからないが、天才的らしい。
他の棋士が気づかないような手をよく指す。
それで終盤に逆転するから、「羽生マジック」と言われる。
羽生さんと対戦する棋士は、終盤かなり優勢でも、
「何かあるんではないか?」と疑心暗鬼になることが多いらしい。
それでますますマジックを出やすくする。
森内俊之名人との7番勝負は、
円熟期のライバル対決として、素晴らしいものだった。
今は、佐藤康光棋聖と、3つのタイトル戦を続けて戦っている。
こちらも、お互いを知り尽くしたもの同士が、
二人だけの世界で遊んでいるような感じ。
私生活が破綻していないようだ、というのが、
唯一、あまり天才らしくない点だが・・・
羽生さんのもうひとつの魅力として、
「将棋とはどういうゲームか」ということを
とてもよく考えている(ようだ)という点がある。
将棋とはどういうゲームか?、つまり、将棋観は、
人それぞれで、プロ棋士の間でも、かなり違いがありそうだ。
たとえば、佐藤康光棋聖に言わせれば、
「将棋とは殴りあいだ」となるかもしれない。
谷川九段なら「一瞬の隙を突く斬りあい」だろうか。
ずっと昔のことだが、森下九段の「将棋は、駒の連携と働きだ」
と言う観点でのNHK将棋講座「将棋相対性理論?」は印象的だった。
強い人が、こういうことをよく考えているか、というと
そうでもなさそうで、森内名人や中原元名人だと、
ほとんど何も考えていなくて、
「将棋は将棋でしょ」と言いそうな気がする。
そして、羽生さんは、どこかで、
「将棋とは、いかに相手に悪い手を指させるか、というゲームだ」
というようなことを書いていたように思う。
それによると、将棋では、中盤を過ぎると、
ある局面をさらに良くするプラスの手というのは、
ほとんど無いのだそうだ。
ほとんどの手は自分を不利にしてしまう悪手であり、
互角の状態を維持できる手もわずかしかない、ということらしい。
そうした中で、いかに自分を有利にするか、
いかに相手を斬るか、ではなくて、
いかに相手を、悪手を指さざるを得ない状況に追い込むか。
この独特の、しかし、おそらく真実を捉えている将棋観が、
いわゆる羽生マジックとか、どんな相手にも対応できる柔軟さ、に
つながっているように思える。
こう書くと、いかにも性格が悪そうだが、
盤上以外では、そうでもなさそうなのも、おもしろい。
最新の画像もっと見る
最近の「将棋・ゲーム」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事