こんにちは!はんなり伊豆高原です!
早く食べたい~~!

むぅ~~~っ!

ねぇまだぁ?



≪Happy Birthday
 ≫
≫
これはいつものゴハンと違うんだよ!
あちゃちゃんが、この世に生れて
パパとママに出会えたお祝いなんだよ!
よく我慢したね!

さぁお食べ!!
こんにちは!はんなり伊豆高原です!
早く食べたい~~!

むぅ~~~っ!

ねぇまだぁ?



≪Happy Birthday
 ≫
≫
これはいつものゴハンと違うんだよ!
あちゃちゃんが、この世に生れて
パパとママに出会えたお祝いなんだよ!
よく我慢したね!

さぁお食べ!!
 こんにちは!はんなり伊豆高原です!
こんにちは!はんなり伊豆高原です!
朝晩かなり陽が入るようになったものの、
真上に覆いかぶさる背の高~い木の枝葉が

日中の光合成を阻みます。。
夏の強烈な日射しよけになるんじゃないか?
と、都合のよい解釈に溺れたまま。。

テーブルをつくり。。


リースをつくって気をまぎらせた帰り道。。。

近所の八百屋の入口に積み上がった
大根を見て唖然!
え~~~~っ!!!

『1本100円2本でも100円?』
それって、 人参
人参 じゃないのぉ?
じゃないのぉ?
安すぎ!

決して大根だけはつくるまい!
と心にかたく誓ったのであった。。。


 こんにちは!はんなり伊豆高原です!
こんにちは!はんなり伊豆高原です!
 気持ちの良い朝の日差しを受け
気持ちの良い朝の日差しを受け

そろそろ背伸び?

 花見朝湯
花見朝湯

見つめるキミ。。

見つめるボク。。 ロミオくん

もん太クン
 いってらっしゃい!
いってらっしゃい!
さようなら!
こんにちは!はんなり伊豆高原です!
ミラクルパワースポット
【大瀬神社】
その小さな岬の先端は、
不思議がいっぱい

それは、美しい富士を望む白灯台を有する
浜より数十メートルも離れていない場所、
しかも海との高低差ほとんど無い場所に
あります。。。

淡水【神池】があるのです!
下の写真を!!

静まり返って何かしら得体の知れない雰囲気を持つ神池。。
自販機でエサを買ってばら撒いた瞬間!
超ミラクルパワー溢れる【鯉】の群れ!!
ほんの20メートル先ではこの日ウツボが泳いでいるのを見ました。。

死。。精神喪失。。不慮の危難。。
こ。。。怖すぎる。。。

さらに岬の先端に進むと御神木
天然記念物のビャクシンがパワーを纏って鎮座しています。。



 パワーの源
パワーの源



【ゆらぐ褌】

【うねるビャクシン】

【溢れる鯉】
如何がでしたか?伊豆の付け根の
≪大瀬崎≫今回紹介した場所は
総てワンコと回れます。
鯉の群れに彼ら釘付け必至!
是非皆様お立ち寄りを!!
~大瀬明神の神池~
大瀬明神の神池(おせみょうじんのかみいけ)は、静岡県沼津市西浦江梨、伊豆半島の北西端から北へ突き出した大瀬崎の先端にある、最長部の直径がおよそ100メートルほどの池である。伊豆七不思議の一つ。国の天然記念物である「ビャクシンの樹林」に囲まれてはいるものの、海から最も近いところでは距離が20メートルほど、標高も1メートルほどしかなく、海が荒れた日には海水が吹き込むにもかかわらず淡水池であり、コイやフナ、ナマズなどの淡水魚が多数生息している。駿河湾を挟んで北方およそ50キロメートルの富士山から伏流水が湧き出ている、などとする説もある一方、海水面の上下に従って水面の高さが変わるとも言われており、何故淡水池であるかは明らかにされていない。古くから池を調べたり魚や動植物を獲ったりする者には祟り(たたり)があるとされ、また実際に池の水が層状に分かれていた場合などに機材や人などが池に入ると取り返しのつかない環境破壊となる恐れが強いこと、透明度が低く池の底の観察が難しいと考えられること、などから今もって詳しい調査はなされていない。尚、引手力命神社の境内地であるため、拝観時間は日の出から日没までとされ、拝観料が必要である。また魚や動植物の採取は文化財保護法などにより固く禁じられている。。。
こんにちは!はんなり伊豆高原です!
南国でうまれ。。旅を続けながら育ち。。
ついに本州にたどり着いた≪伊豆半島≫の誇る
ミラクルパワースポット
【大瀬神社】

引手力命(ひきてちからのみこと)神社に潜入!!




いきなり【鉄の下駄】!

境内上部に【カッパ】!

中段には【天狗】!!

夥しい数の【赤い褌】!

何やら言い知れぬパワーをひしひしと感じます。。
次回さらに先へと進みます。。。つづく 

~引手力命神社~
引手力命神社(ひきてちからのみことじんじゃ、ひきたぢからのみことじんじゃ)は、静岡県沼津市西浦江梨の大瀬崎にある神社。今日では大瀬神社(おせじんじゃ)と呼ばれることが多く、他に大瀬明神(おせみょうじん)などとも称される。延喜式神名帳に記された「引手力命神社」は当社とされることが多いが、伊豆国の旧田方郡にはもう一社、静岡県伊東市十足(大室山北麓)に引手力男神社(ひきてちからおじんじゃ)がある。実際にどちらが本当の式内社「引手力命神社」であったかは決定的な史料が無いために明らかではなく、今後の更なる調査および研究が待たれる。本項では大瀬崎の引手力命神社について記す。
祭神は引手力命(ひきたぢからのみこと)とされているが、全国の主な式内社とされる神社でこの名前の神を祀るものは他に見られない。これを古事記や日本書紀にも登場する天手力雄(男)命に比定する説もあるが、一般に天手力雄(男)命が山の神とされているのに対して引手力命は海の守護の神であり、必ずしも定かではない。
創建時期は不明であるが、一説には白鳳13年(684年)に発生した大地震に伴って海底が突然三百丈余も隆起して「琵琶島(びわじま)」と呼ばれる島が出現したため、同時期の地震で多くの土地が海没した土佐国から神が土地を引いてきたのだ、と考えた人々がここに引手力命を祀ったのが最初、とも言われる。「琵琶島」はやがて砂洲の形成により陸繋島となり大瀬崎となった。
平安時代末期に源為朝と源頼朝、および北条政子は源氏の再興を祈願して当社に弓矢、兜、鏡、太刀などを奉納し、源氏の再興が叶い鎌倉幕府が成立して以降は、多くの武将たちが弓矢や太刀を奉納するようになったとされる。
室町時代には熊野国の水軍の武将であった鈴木繁伴がこの地を支配し(館の跡とみられる遺構がある)祭祀に勤しんだとされるが、その後の度重なる地震や津波で館も奉納品も全て失われた。しかし砂の中からそれらの一部が見つかるに及んで地元の人々がこれらを奉り、何時とはなしに再興されて今日に至っている。
海上安全を願う人々が赤い褌を奉納する風習があり、また漁船の進水式に関連してその漁船の縮尺模型を海上安全と豊漁を祈願して奉納する風習もあった。この関係で、漁の様子を描いた絵馬や漁船の木造模型などが多数奉納され、その一部が絵馬奉納殿に展示されている。ただ、1892年(明治25年)に発生した火災により、それ以前に奉納されていた模型は焼失してしまった。2008年現在は、それ以降に奉納された32隻のうち一部が展示されているが、模型の裏には墨書きで奉納者の氏名住所・奉納年が記録されており、明治・大正・昭和初期の駿河湾沿岸の漁船の様式も正確に再現され、また同神社の信仰圏が駿河湾の広い範囲に分布していたことが見出される。。。
こんにちは!
はんなり伊豆高原です!
富士山めざし。。

グングン進む!!

その麓に佇む湖
【山中湖】

を少し登ると、森に守られたホテル。。

カーロ・グループ1号店、2号店の
≪カーロフォレスタ山中湖≫
&
≪エルフォ≫
に出会えます!そこで!
突然キャンセル情報!!
2/11(金) 12(土)
カーロフォレスタ山中湖
こんにちは!
はんなり伊豆高原です!
久々の神社シリーズ復活!!
≪伊豆のミラクルパワースポット!≫
【大瀬神社】
の紹介です!

ダイビングのメッカとして知られる大瀬崎。
シーズンに比べると、
ダイバーは三分の一程度でしたが、
ダイビングショップやダイバーの宿が
立ち並ぶ浜沿いは、いつも賑やかです。

自然を愛するダイバー達は
もちろんワンコにもニコニコ顔!

浜が途切れたところで
突然看板が待ち受けています。。。
【ひきてちからのみこと神社】

≪大瀬神社≫です!



つづく。。。
~大瀬崎~
大瀬崎(おせざき)は、静岡県沼津市西浦江梨にある、伊豆半島の北西端から北へ駿河湾内に突き出した半島、または岬。琵琶島(びわしま)と呼ばれることがある。かつて海軍音響研究部大瀬崎実験所が設置されていた。
伝承によると、白鳳13年(684年)に発生した大地震に伴って海底が突然「三百丈余」も隆起し、琵琶島(びわしま)として出現したのが始まりとされる。その後の砂洲の形成により陸繋島となり現在の姿となった。半島としての長さは1キロメートル弱、最も狭い部分の幅は100メートル足らずである。半島の東側は遠浅の砂浜を持つ湾を成しており、海流や波が少ない。一方西側は大きな石が堆積した海岸となっている。湾内の砂浜は1974年の七夕豪雨により失われたが、その後の養浜事業によって現在では砂利浜として整備されている。
水質が良いこと、駿河湾に面し生物相が豊かなことからダイビングのメッカとして、比較的都市部に近いことも相まって1980年代末頃から全国的に知られている。ポイントは海岸の眼の前である。 「湾内」「岬の先端」、岬の外側および西側にある「柵下」「門下」「一本松」「大川下」「タマザキ」の7ビーチポイントと、いくつかのボートポイントがある。「湾内」は台風が直撃しない限りは潜れるというほどの安定したポイントのため、体験ダイビングや講習に多く使われる。水中カメラマンも多く訪れる。
また岬の東側の湾内は沼津市によって「大瀬海水浴場」が整備されている。1990年代に遠浅で透明度の高いことがマスコミで取り上げられて家族旅行先として有名となり、2006年には環境省の「快水浴場百選」に選ばれた。
海水浴場沿岸と県道17号へ通じる市道沿い(高台)には、ダイビング・海水浴双方の利用客を相手としたペンション・民宿が軒を連ねている。海水浴場沿いにあるペンションは、ダイバー向けのマリンショップと海の家を兼ねている店舗が多い。 また、私営のオートキャンプ場も営業している。
先端から300メートルほどの、標高10メートル余りの峰の上には引手力命神社(ひきてちからのみことじんじゃ、大瀬神社または大瀬明神と呼ばれることが多い)があり、崎のこれより先の部分は神社の境内地とされている。。。
 こんにちは!
こんにちは!
 はんなり伊豆高原です!
はんなり伊豆高原です!
最近はんなりで流行中!!
お散歩仲間やブログ仲間と
みんなで旅行!!
お食事は一か所に集合!
≪座卓で宴会≫
ワイワイ楽しんでるパパママをよそに。。。
彼らは自由気ままにくつろぎモード!

 うろうろ派
うろうろ派

 横寝派
横寝派 

 本気寝派
本気寝派 

 がっつり派
がっつり派

 ねばり派
ねばり派 
楽しい夜はつづく。。。














ハーラちゃん、ディーバちゃん、フィービーちゃん、アデラちゃん、
オリーブちゃん、ベスちゃん! またね!

 こんにちは!
こんにちは!
 はんなり伊豆高原です!
はんなり伊豆高原です!
江戸時代から続く
≪稲取つるし雛≫
飾り祭り開催中!!

マップなど詳しくはこちら
↓ ↓ ↓
http://www.inatorionsen.or.jp/hina_sp/index.html
~つるし雛~
雛のつるし飾り(ひなのつるしかざり)とは、江戸時代から伝わる伊豆稲取地方の風習、吊るし飾りのこと。長女の初節句に、無病息災、良縁を祈願して、雛壇の両脇に細工を吊すもの。過去においては庶民の雛壇代りでもあった。伊豆稲取では、もともとはツルシと呼ばれ特に名称はなかった。つるし飾りは、子供が成長し7歳、成人、嫁入りといった節目を迎えると、新年のどんど焼きに焚きあげてしまうため、古いものはあまり残っていない。平成5年頃より稲取の婦人会の手芸講座にてツルシ製作を通じて見直され、「雛のつるし飾り」の名称をつけられた。つるしの漢字表記「吊るし」は、縁起物には不適当なため推奨されない。平成10年、稲取温泉旅館協同組合が中心となり観光の目玉として雛のつるし飾りまつりが開催されたが、それ以後から類似した吊るし雛イベントが開催されたり、外部の製作者、節句店、手芸店などによる類似異形のつるし飾りが流通したりするなどの問題が発生。これに対して、東伊豆商工会は”稲取ももの会”を設立。また”絹の会”とともに加盟店による伊豆稲取の品質基準を満たしたつるし飾りの製作、購入を推奨している。現代では、桃(長寿)、猿っ子(魔除け)、三角(薬袋香袋)を基本として50種の細工がある。これらを5列の赤糸に各11個の細工をつるし計55個にそろえ、これを対で製作することにより110の細工がつるされたものが基本型とされる。 一般に直径30cmのさげわに170cmの長さで吊るされ、飾りの数は3、5、7、9などの奇数で組み上げられる。この理由は、前述した様に縁起物であるため、割り切れる数字(偶数)を避けてのことである。。。
 こんにちは!
こんにちは!
 はんなり伊豆高原です!
はんなり伊豆高原です!


2月3日は節分の日!
至る所で鬼の姿が見られます!
はんなりご近所ワンコ絵馬でお馴染みの、
≪神祇大社≫
でも毎年恒例の豆まきが行われました!
遠藤レポーターの突撃取材です!

境内の中はすし詰め状態。。照明が落ち、
一斉に豆まきが行われるのですが、
その中に数字の書いてある銀杏が混じっており、

その番号に応じた商品がもらえるのです!
なんて楽しい企画!!
来年は是非参加して、旅行券狙います!
~節分~
節分(せつぶん、または、せちぶん)は、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと。節分とは「季節を分ける」ことをも意味している。江戸時代以降は特に立春(毎年2月4日ごろ)の前日を指す場合が多い。以下、立春の前日の節分、およびその日に行われる各種行事について述べる。季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられており、それを追い払うための悪霊ばらい行事が執り行われる。節分の行事は宮中での年中行事であり、延喜式では、彩色した土で作成した牛と童子の人形を大内裏の各門に飾っていた。これは、平安時代頃から行われている「追儺」から生まれた。『続日本紀』によると706年(慶雲3年)にこの追儀が始まり、室町時代に使用されていた「桃の枝」への信仰にかわって、炒った豆で鬼を追い払う行事となって行った。『臥雲日件録(瑞渓周鳳)』によると、1447年(文安4年)に「鬼外福内」を唱えたと記されている。近代、上記の宮中行事が庶民に採り入れられたころから、節分当日の夕暮れ、柊の枝に鰯の頭を刺したもの(柊鰯)を戸口に立てておいたり、寺社で豆撒きをしたりするようになった。一部の地域では、縄に柊やイワシの頭を付けた物を門に掛けたりするところもある。豆を撒き、撒かれた豆を自分の年齢(数え年)の数だけ食べる。また、自分の年の数の1つ多く食べると、体が丈夫になり、風邪をひかないというならわしがあるところもある。豆は「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより、邪気を追い払い、一年の無病息災を願うという意味合いがある。寺社が邪気払いに行った豆打ちの儀式を起源とした行事であり、室町時代の書物における記載が最も古い記載であることから少なくとも日本では室町時代以降の風習であると考えられる。初期においては豆は後ろの方にまくことが始まりだった。使用する豆は、お祓いを行った炒った大豆 (炒り豆) である。北海道・東北・北陸・南九州では 落花生をまく(大豆よりも回収し易く、殻ごと撒くため地面に落ちても食べられる、等の利点がある)。豆を撒く際には掛け声をかける。掛け声は通常「鬼は外、福は内」であるが、地域や神社によってバリエーションがある。鬼を祭神または神の使いとしている神社、また方避けの寺社では「鬼は外」ではなく「鬼も内(鬼は内)」としている。家庭内での豆まきで、「鬼」の付く姓(比較的少数だが「鬼塚」、「鬼頭」など)の家庭もしくは鬼が付く地名の地域では「鬼は内」の掛け声が多いという。炒った豆を神棚に供えてから撒く地方もある。節分の時期になると、多くのスーパーマーケットでは節分にちなんだコーナーが設けられ、その中で福豆(ふくまめ)として売られている。厚紙に印刷された鬼の面が豆のおまけについている事があり、父親などがそれをかぶって鬼の役を演じて豆撒きを盛り上げる。しかし、元来は家長たる父親あるいは年男が豆を撒き鬼を追い払うものであった。小学校では5年生が年男・年女にあたる。そのため、5年生が中心となって豆まきの行事を行っているところも多い。神社仏閣と幼稚園・保育園が連携している所では園児が巫女や稚児として出る所もある。大きな神社仏閣では、節分の日に芸能人・スポーツ選手・等が来て豆をまくようなことも行なわれ、イベント化しているとも言える。以前は豆のほかに、米、麦、かちぐり、炭なども使用されたというが、豆撒きとなったのは、五穀の中でも収穫量も多く、鬼を追い払うときにぶつかって立てる音や粒の大きさが適当だったことによる。また炒り豆を使用するのは、節分は旧年の厄災を負って払い捨てられるものである為、撒いた豆から芽が出ては不都合であったためであるという。。。
 こんにちは!
こんにちは!
 はんなり伊豆高原です!
はんなり伊豆高原です!
段々畑の一番した!
ほらっ!陽が入った!!




海も見えるようになりました!



≪MY畑≫予定地も、
木の根っこを抜いて
少しだけ手を入れました!!

夏頃にはこんな感じになるかなぁ。。
想像中。。。




皆様のお口に運べるレベルの畑を目指して、
地元民への道はつづく。。。
 こんにちは!
こんにちは!
 はんなり伊豆高原です!
はんなり伊豆高原です!
2月前半空室状況のお知らせです!
2月7日(月)・・・葵・松風・夕霧・早蕨・若菜
8日(火)・・・葵・松風・蛍・早蕨・若菜・藤袴
9日(水)・・・葵・藤袴
に空きが御座います!
※ お部屋は随時埋まる可能性がありますので、ホーム・ページの空室状況でご確認頂くか、お電話でお気軽にお問い合わせ下さいませ。
はんなり伊豆高原 / 0557-54-5860

こんにちは!
はんなり伊豆高原です!
2月がスタートしました!
1月のまとめです!


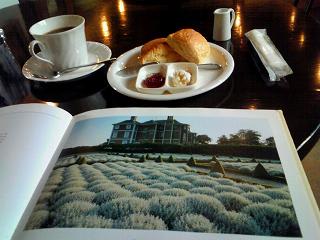










7月のご予約受付中!!