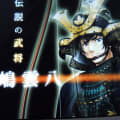前回ブログ記事の続きです。
”花手水”で知られる御裳神社に行ったところ、
今年は”尾西あじさい祭り”が中止のため、
あじさいの”花手水”は見られないとのこと…。
ここで、ふと心の中に思い浮かびました。
以前、愛知県の津島神社に行った時、
菊の”花手水”があったような気が…?
津島神社に行くと”花手水”見られるかも…。

さっそく津島神社に行ってみました。
”花手水”ありました~!手水舎には、
たくさんの花が浮かべられています。
ここの”花手水”は紫陽花だけじゃぁない。
菊あり、蘭の花あり、ガーベラあり、
ビタミンカラー(?)とってもカラフルです。
ボランティアガイドさんの説明がありました。
「津島神社の”花手水”は毎月1日になると
飾られます。花は1週間ほど持つので、
1日から1週間ほどの間、飾られています。」

「もともとは、秋になると神社に奉納された
菊の花を手水舎に浮かべていたのですが、
みんなにとても喜ばれたので、今では
オールシーズン飾られるようになりました。」
ボランティアガイドさんに出会ったこの機会に
せっかくだから、津島神社の歴史&建物など
詳しく説明していただくことになりました。

「津島神社は、戦国時代、天下をとった
織田家、豊臣家、徳川家の3家ともに
深いかかわりを持った神社です。」
「戦国を代表する三英傑、どの一族にも深く
関わった神社は他にあまり聞かないです。
まぁ、それだけ津島神社は大きなパワーを
持っているのかもしれないですね~。」
「では津島神社にある2つの門の謎、
ご存じでしょうか…?」
「津島神社にある2つの門の謎…?
知らないです。」

「津島神社には2つの歴史ある門があります。
1つは楼門…。見るからに立派な門ですね。
豊臣秀吉が寄進した門なのです。」
また本殿、拝殿の正面に、もう1つ門がある。
こちらは秀吉の息子、秀頼の寄進です。
秀吉の病気平癒を祈願して建立されました。
南門と呼ばれています。小さな門ながら、
どことなく風格ある感じがしますよね~。」

「では、この2つの門、”楼門”と”南門”、
どちらが正門なのか、わかりますか…?」
ボランティアガイドさんに尋ねられました。
「いや…、わかんないですね~。
楼門の方が立派な建物に思えるので、
正門のような気がしますし…、
本殿、拝殿の正面にあるから、南門が
正門のような気もします…。」
「正解は…、南門です…!なぜかというと、
南門のそばに”蕃塀”があるからです。」

これが”蕃塀”です。
「”蕃塀”は、尾張地方の神社で
よく見かけるものです。本殿の前にあり、
悪いものをシャットアウトする塀なんです。
”蕃塀”があるほうが正門になります。」
「ほとんどの方が、どう見ても
楼門のほうが貫禄あるのに、どうして…?
…と不思議に思われますね。

津島神社神苑の半夏生
「実は楼門、秀吉が寄進した時は、
”神社の門”ではなかったのです。
では最初、何の門だったか、
あなた、わかりますか…?」
「お寺の門だったのではないでしょうか…?
明治維新まで、神仏習合だったので、
神社とお寺が一体だったそうですね。
津島神社のお隣に、お寺があったはず…。」

津島神社の神宮寺だったお寺”宝寿院”
「正解です。明治になるまで、津島神社は
”津島牛頭天王社”とよばれ、神社とお寺、
”神宮寺”と呼ばれるお寺が一体でした。」
「この門は津島牛頭天王社に付随する、
神宮寺の楼門として建てられました。
その当時、楼門の2階には
薬師如来が祀られていたのです。」
「現在、コンクリート造りになっている、
宝物庫の場所に昔、お寺がありました。
楼門はお寺のちょうど正面になります。」

白いコンクリート造りの建物が宝物庫です。
「明治時代になって神仏分離令が出され、
一体だったお寺と神社が別々になりました。」
「一方、この時、”廃仏毀釈”と言って、多くの
お寺の建物や仏像などが破壊されています。
ここにあった神宮寺も移転しました。そして
楼門は、取り壊されることになりました。」

「ところが、貴重な秀吉ゆかりの建物を
取り壊すなんて、もったいない…!
なんとか残すことはできないだろうか…?」
「いろいろ考えて、楼門の2階に祀られていた
薬師如来を、他の場所に移しました。
そして、仏教色をすっかり排除してから、
楼門を津島神社に譲りました。」
「こうして楼門は、津島神社の門となり、
無事、取り壊しを免れたのです。」

「楼門、太平洋戦争の戦災に遭わなくて
とてもラッキーだった、と思っていましたが、
取り壊しの危機があったのですね。」
「津島神社は、神仏分離令が出た時、
神社の名前も、ご祭神も変わっています。
もとはご祭神がスサノオノミコトではなく、
牛頭天王でした。そして津島神社ではなく、
”津島牛頭天王社”と呼ばれていたのです。」
ボランティアガイドさんの説明に
聞き入りました。興味深いお話でした。
こんなお話が聞けたのも、神さまの
お計らいなのかもしれませんね。