私は、幸福の科学の信仰者でございます。
でも無神論者も、「神様なんていない。」という教義を持つ、堂々とした信仰だと思っています。
私は、共産主義(無神論)を唱えた、カール・マルクスの資本論も、「神は死んだ。」と言った、ニーチェの著作も読んではおりません。
ただ彼らは、「自身の論説の中心である無神論を、”確認”したわけではない。」
この真実は理解できます。
なぜなら、神がいらっしゃらないということを、確認する術はないからです。
同様に、「あの世なんてなかったよ。」と、あの世に行って(笑)、確認した人もいないのです。
でもまぁ、彼らとて悪気があってそんなことを唱えたかどうか。
恐らく、そうではないだろうと推測いたします。
彼らは彼らなりに、人々に幸福をもたらそうとはしていたとは思います。
共産主義の創始者カール・マルクスは、ユダヤ人です。
共産主義のユートピア思想も、労働者が指導するという彼なりの理想社会も、旧約聖書から来ているのですね。
つまり、体系化された無神論である共産主義というのは、『ユダヤ教マルクス派』というのが、一番しっくり来る分類ではないかと思いますね。
つまり、「カール・マルクスは、ユダヤの神を、信じることができなかった。」ということではないかと思います。

人はみな、死というものを怖れます。
童謡で、確か・・・、♪♪ オバケなんてないさ、オバケなんて嘘さ ♪♪ っていう歌が、あるじゃないですか。
ああいうノリが、無神論や唯物論にはあると思うのですよ。
ユダヤ教の経典、旧約聖書には、キャラクターの違う神さまが出てきますが、有名なのはヤハゥエという神さま。
このユダヤの神さまは、裁きの神ですし、妬む神で、「我が名を唱えてもいけない。」と書かれています。
この神さま、羊飼いのような存在で、人を生かしているのか、家畜(食料)と見て、峻別しているのか、さっぱりわからん存在です。
そういう宗教思想のもとでは、死後にどんなイチャモンを、神からつけられるか、全くわからんですよね。
ただでさえ死は怖ろしく、忌むべきものであるし、誰もが逃れられない、必ず通らなければならない現実なのに、それを仕切っている”神”なる存在が、羊飼いのような神であり、妬み、裁き、罰を与える、ドSキャラの神であるならば、人は結局のところ、救われないのですよ。
そんな神、信じられるか!
そんなの、あってたまるか!
だから、神などいない!
死後の世界もないから、何も怖れるものなどない!
マルクス的に言うと、こういう感じではなかったかと、私は推測しますね。
こういう流れが、共産主義や無神論には流れているんじゃないかなと、私は思っているのです。
逆の意味で、マルクスは「神は愛である」ということを、本質的には感じ取っていたかも知れませんね。
 https://www.irhpress.co.jp/
https://www.irhpress.co.jp/
結局、死を怖れる人間の本能からの逃避と、旧約聖書に記載されているドSな神観からの脱却が、無神論の本質ではないでしょうかね?
素朴な疑問ですけど、旧約聖書の神は、「妬む神」ですけど、この神様は、誰に妬んで、そして、どうして妬んでいるんでしょうね?
自分より格下の存在に、妬む必要はありませんよね。
自分より、評価の低い存在に、妬む必要もありません。
この、「妬む神」という表記には、このユダヤ神よりも、上の存在、つまり、「この神が、妬まざるを得ない存在が、実在する。」という意味が、知ってか知らずか、込められているんです。
つまり、「旧約の神というのは、唯一の神でもなければ、トップの神でもない。」ということですよ。
ですから、現代の無神論者を辿って行けば、カール・マルクスという教祖が唱えた、立派な宗教なんですけど、生前のカール・マルクスの、見抜けなかった聖書知識もありますし、科学が進み、時代が進歩し、新たな評価する母数が変わってきていますので、今一度その、無神論の教義自体を、見直さなければならない時期が、来ていると私は思うんですね。
それこそが、科学的思想を自負する、彼らの心情に沿うのではないかと、私は考える次第です。
つまり、「無神論者が本能的に忌み嫌っている神なる存在が、実はもう、実像が違ってきているんじゃないでしょうか?」
ということです。

さあ、神様を信じられない方、そして死後の世界とか、霊の存在とかを信じられない方。
今こそ、ほんのちょっとの勇気を出して、神の世界とか、死後の世界などに、目を開いてみてはいかがでしょうか。
新たな、否、真実の、そして海外の方も未来の方も納得のいく、「これぞ地球神のお考え」という神観が、幸福の科学にはありますので。
その一端が垣間見れる映画が、「さらば青春 さらば青春」という映画で、今年の5月に全国上映されますが、これがなかなか良いらしい。
ということで映画情報も、これからボチボチお届けしたいですが本日は、経典『死んでから困らない生き方』(幸福の科学出版)の一節のご紹介ですが、大川隆法幸福の科学グループ総裁が、死後の世界のことについて語ったのに、なぜだか全世界が調和してしまう話をしてしまうところが仏陀であり救世主じゃと思ってしまう一節です。
(ばく)
「あの世の真実について」書籍『悟りに到る道』より
瞑想曲「のぞむ光」

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=62
当会の世界観で他の宗教と異なっているのは、霊的な存在について、段階の違いがありながら、同時に、多様な存在があることを認めているところです。
このことは「神」にも当てはまるのです。
ところが、世界の各宗教を見ると、今、主流というか、メジャーであるのは、一神教といわれるものです。
これは、「神は一人であり、それ以外の神は偽物である」という考え方です。
キリスト教やイスラム教は一神教ですし、ユダヤ教もそうです。
こうした一神教が、たまたま、今、先進国に広がっているため、「宗教としては一神教のほうが進んでいる」と考えられています。
そして、「多神教的な宗教を持っているところ、例えば、インドのように神がたくさんいるところは遅れている。
また、『古事記』『日本書紀』等を読むと、日本にも神は大勢いるが、そういう八百万の神々がいるようなところは遅れている」と見るわけです。
このように、「一神教がすごく進んでいる」と捉えがちです。
しかし、当会の霊界観は、そういうものではありません。
やはり、「神」と呼んでもいいような、霊格の高い高級存在がいます。
それを、「神」ではなく、「天使」や「大天使」と呼ぶこともあれば、「菩薩」や「如来」と呼ぶこともありますが、いずれにせよ、霊界には、地上の人間から見ると、遙かに神に近い高級存在として、いろいろな種類の霊人が現実に大勢いるのです。(中略)
「われらの神こそ本物だ」と言う宗教は、あちこちにあるのですが、数多くいる天使、あるいは如来や菩薩たちのうちの誰かが、その宗教の教祖を指導していて、「われが神だ」と言っている場合、教祖のほうは、「その人しか神はいない」と思ってしまいます。
それで一神教になっているのです。
そのため、小さな新宗教にも一神教はたくさんあります。だいたい、それが普通のスタイルです。
したがって、「一つの宗教だけが正しく、ほかの宗教は、全部、間違っている」というわけではありません。宗教の違いの多くは、「誰が指導しているか」ということの違いにすぎないのです。
宗教が一神教になりがちなのは、そうしないと、教義や教団の行動方針が混乱しやすいからです。
複数の霊人たちが、それぞれ違うことを言うと、話の内容が、あっちに行ったり、こっちに来たりして、今風に言うと、ブレやすいのです。
宗教では、よく、「神同士が喧嘩をする」という言い方をするのですが、そうならないようにするため、神を一人に絞ることが多いわけです。
それが一神教の発生原因です。
宗教は、たとえ今は大きくなっていたとしても、発生当時を見ると、ほんとうに小さなものです。(中略)
それが、何千年かたつうちに大きくなり、各地に広がって、世界的な宗教になったときには、その小さなところに降りた神が、世界的な神のように言われ、他の神を排除するような状態になるわけです。
それが、宗教的な紛争などの原因にもなっているのです。
『死んでから困らない生き方』(幸福の科学出版)P112~118










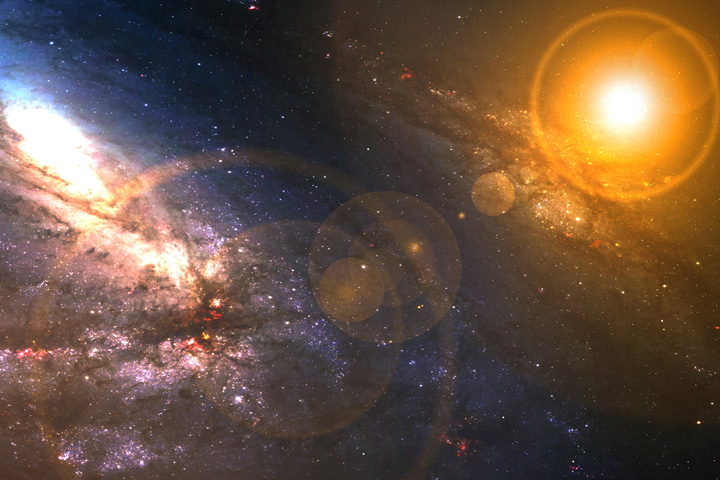









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます