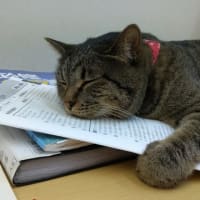一部はプラスチック成型というちょっと工作的な内容でしたが、二部はバリバリの化学!
理科好きにはたまらない(?)内容となっております。
BTB溶液、フェノールフタレイン液といったおなじみの指示薬&マローブルーというちょっと変わった指示薬(植物の花から抽出した液で、紫キャベツと同じように色が変化します)を使って、
塩酸、水酸化ナトリウム水溶液、炭酸水素ナトリウム水溶液、食塩水の液性を調べたり、
中和反応をみたりします。
これがマローブルー。
乾燥した花が試験管に封入してあり、水を入れて使います。

まず、パレットに指示薬を二、三滴ずついれて・・・
最初の色はこんな感じ。

それから調べたい薬品をまた一滴ずつ。
楽しいけれど、大変地味で、面倒な作業です(^^ゞ

そう、化学実験って、実は地味で面倒。
サイエンスショーなんかでやる実験は、
実験と言うよりはもう結果がわかっていることを
マジックショウよろしく派手なアクションと共にやるので華やかなイメージがありますが、
世紀の新発見!だって、毎日毎日同じ作業を延々延々繰り返している中から生まれるのですから、
将来理科系に進みたいなーなんて思っている人には、
こういう苦労も味わってもらいたいな、と。
中和反応なんて、超地味(笑)

ガラス棒で、一滴ずつ加えて混ぜて、
ガラス棒洗って、拭いて、
また一滴・・・
30回近く繰り返した子もいましたが、
一瞬で色が変わる、その一瞬のためだけにみんな頑張りました。
・・・でも、なかなかちょうど緑(中性)にはなかなかならないのですけどね。
(発熱反応で危険なため、極少量でやったせいなのですが…)
そして、最後はアンノウンサンプル(何かわからない水溶液)の同定。

小6の子たちは学校でまだ水溶液の性質など学習前なので、
今日の実験結果をいろいろと見比べながら、未知のサンプルが何か一生懸命考えてくれました。
中1の子はすで学習していますが、一つ一つ確認しながら慎重に進める様子が科学者らしい片鱗を見せていましたね。
指示薬や簡易試験管たては持って帰れるので、
身近な水溶液・・・たとえば、雨水、田んぼや池の水、台所用洗剤、漂白剤、食酢、石鹸水・・・etc
などの液性も調べてみると面白いね、なんて話すと、
ウンウンとみんなうなずいてくれる、とってもカワイイ科学者さん達。
ますます理科が好きになってくれたらうれしいです。