


「青チャート」か「一対一対応」かどっちの問題集がいいですか?
数学の先生でも意見が分かれたとの相談でした。
このケースでは、「一対一対応」がどうしても好きで背中を押してほしいという場合があると思います。
模試の偏差値で62程度を越えたらありかなとは思います。この場合妥当なラインは「青チャート」と答えるのかなと思います。ただ、数学の好きな先生の場合「一対一対応」が好きな感じがします。効率重視、教えてわかったら問題は解けると考えている場合は「一対一対応」推しな感じがします。
頭でわかり、体験して定着するというプロセスに至るには「ドリル」が必要な場合があるのかなと思います。偏差値で言って55ほどまでの場合は、「ドリル」教材の完成で見えてくることがあるのかと思います。
私だったら、「4STEP」。「解答があればつかうんだけどな」といわれる教材。
解答を載せているページがありました。→https://kaito.click/
同じように、生物は「セミナー生物」+赤本 で合格点 ということを言っています。
基礎を固めたら、足りないところが見えてきて、そこを補充しおさえると良いと考えます。
●4STEP
https://www.chart.co.jp/goods/item/sugaku/24347.php
●セミナー生物
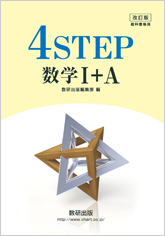
昭和大学医学部は、数学を回避し国語での受験が可能です。
「数学を勉強して何になるんですか?」とよく耳にします。(実際に会話の中で出てくることが多いのです)
「微生物群集の動態とか数式のモデルがいるのかな?」とか、「数値的な論証をするうえで解析的な能力はいるな」とか思うことはあります。昔、生物科では「生物統計学」を学んだりしたのを思い出します。
その反面、大学に入ってからの専攻によってはそこまで理系だから数学ができなくてはならないといって目くじらを立てるほどでもないかなと思うこともあります。(特に、生き物が好きな生物科のメンバーは当時数学ができることのほうが珍しかったなあと思いだします)
ただ、基礎科学であれば英語なり、応用であれば日本語の場合もありますが文字から情報を得て理解するといったことは必須です。そうすると、国語受験もある意味実利的ではないかと思います。
医学部だと「科学リーディング」とか「生命科学輪読」とかといった受験科目があって、文章で生命現象などを読めたら合格といった制度があっても面白いかなと思います。それに、すこし近いのがこの国語。
生命とか死とか医療とかに絡んだトピックであるために「必要のない能力」だという反論の余地がないのも面白いところです。文章量が多く、長いリード文で困惑する生物受験生を見ていると数学受験のほうが楽かなと思うくらいの国語の問題ですが、面白い趣向だと思います。化学や生物も「生命科学」関連分野の出題があったりで「役立つ」勉強をしてるかということを評価しようという流れなのかなと思います。
懐かしい「生物統計学」
今の生物科は勉強するのかなとおもいます。

昭和大学や酪農学園などは「入試過去問題活用宣言」に参加しています。
過去の問題と同じものが出る可能性がありますから、傾向に合わせて他大学の過去問で勉強ができます。
特に酪農学園は獣医で生物のみ個別試験ですが国立大学の基礎的な問題を再利用しています。記述も含め地道な勉強ができて文章で書けるかといったことを評価できる問題を選んでいるようです。そのため、「共通テスト+生物は個別」という様式は、生物も含め全科目共通テストの成績のみで合否を判定するのとは結果が違ってくるなと思い、面白い様式だなと思っています。
★医学部受験・獣医学部受験の相談も受け付けています。
団体・個人ともにお気軽にお問い合わせください。
horizon.tama@gmail.com
受験生物に関するいろいろな案件を受け付けています。
・授業(講義)
・個別指導
・受験カウンセリング
・問題作成など
●公式ホームページをペライチで作っています
●講義(授業)コンテンツをYouTubeでアップロードしています
horizon.tama@gmail.com までお願いします!