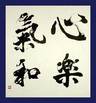後肩取り三教投げ
本部道場では、武漢ウイルス感染防止のため緊急事態発令されたことの他に、櫛田昌之指導員の逝去という痛恨の事態に置かれました。ダブルパンチです。
この世の無常の深さは、いくら考えても推し量ることはできません。パッと方向転換し、故人が晩年に打ち込んだ遺志を継承し、皆さんに楽しんでいただくしかありません。そう肚を決めました。
そこへ技を監修する依頼が来たので、撮影して資料を送りました。櫛田君がいたらなぁ?受けに使ったのに。思い出が鮮明で、いつもそこにいるような気がするよ。(監修したのはビックコミック スペリオール 2020.710発売)
さて、技の流れは以下です。
写真1897
この場面に技の名称をつけるなら
「後肩取り三教投げ」となります。
不意に背後から、主人公右肩に手をかけられた。
主人公は落ち着いて「流し目で」、右肩後の気配を見る。
この時大切なのは、敵の手が右手か左手か?
親指・小指の位置?
瞬時に判断することです。
写真1898
敵は左手で来たと判断し、三教をかける決意をしました。
自分の右肩が動かないように(自分の動静が、敵に伝わらぬように)注意します。
写真1899と1900
敵の左手合谷(ごうこく 人差し指と親指でできる谷間のこと)に主人公の親指を当て、三教の掴み方を行った場面。
写真1901と1902
主人公は己の右手片手でも三教をかけることができるが、より確実にするため主人公左手を使って、敵指先を取りに行く。
写真1908から1910
三教を片手でかける場合の写真です。
写真1911と1912
両手で三教をかける、技の効果が始まったところ。
写真1913から1917
三教が、かかり切った状態。
この時、敵の手首が痛いのではなく、敵の肩が抜けて浮いてつま先立ちに崩すことが大切。
浮かしの崩しは、合気の特徴です。
写真1918から1920
敵に三教をかける→浮かしの崩し→前方に投げ放す→残心姿勢
残心姿勢
合気道では レの字立ち
古武道では 撞木足(しゅもくあし)
といいます。
剣術に由来し、体術でも使われます。
足の形が大切です。