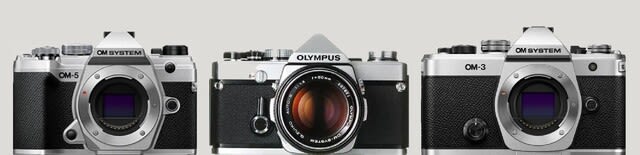キヤノンから久しぶりにコンパクトカメラが出るようです。
キヤノン「PowerShot V1」のスペックリストと発表に関する情報
この噂によれば、ミラーレスEOSのAFを持ち、超広角から標準域のレンズを持ったカメラになるようです。
スマホの普及に伴い、急速に市場を小さくしたコンパクトカメラですが、ここ数年はフジフィルムのX100ⅥやリコーGR3などの高級コンパクトが好調のようです。なのでキヤノンが新機種を投入してもさほど不思議ではないのですが、注目しているのがセンサです。
キヤノンはレンズ交換式の大型のセンサは内製ですが、コンパクトカメラ用のセンサはソニー製のセンサをもっぱら使っていました。小型のセンサーではコスト的に競争できなかったからだと思われます。またコンパクトカメラではセンサの1ピクセルのサイズが非常に小さくなるため裏面照射タイプが使用されていましたが、この技術も当時のキヤノンは持っていませんでした。
PowerShot V1はEOSと同じ内製のセンサーを使うようですが、通常の表面照射センサを使うのか、裏面照射センサを使うのかが気になっています。EOSR1やR5Ⅱでは裏面照射センサを使っているということなので、技術的にはキヤノン内製できるようですが、裏面照射という技術が低価格の機種に展開できるほどコストがこなれているかどうかは別の問題だと思います。
APS-Cサイズのグローバルシャッターを持つ比較的安価なセンサの噂もありました。こちらもセルサイズが小さくなるわけで、裏面照射は必要になるはずです。
本格的に裏面照射センサを導入するのであれば、大きな設備投資が不可欠で、それを回収するためできるだけたくさんのカメラで使用したいはずです。
キヤノン「PowerShot V1」のスペックリストと発表に関する情報
この噂によれば、ミラーレスEOSのAFを持ち、超広角から標準域のレンズを持ったカメラになるようです。
スマホの普及に伴い、急速に市場を小さくしたコンパクトカメラですが、ここ数年はフジフィルムのX100ⅥやリコーGR3などの高級コンパクトが好調のようです。なのでキヤノンが新機種を投入してもさほど不思議ではないのですが、注目しているのがセンサです。
キヤノンはレンズ交換式の大型のセンサは内製ですが、コンパクトカメラ用のセンサはソニー製のセンサをもっぱら使っていました。小型のセンサーではコスト的に競争できなかったからだと思われます。またコンパクトカメラではセンサの1ピクセルのサイズが非常に小さくなるため裏面照射タイプが使用されていましたが、この技術も当時のキヤノンは持っていませんでした。
PowerShot V1はEOSと同じ内製のセンサーを使うようですが、通常の表面照射センサを使うのか、裏面照射センサを使うのかが気になっています。EOSR1やR5Ⅱでは裏面照射センサを使っているということなので、技術的にはキヤノン内製できるようですが、裏面照射という技術が低価格の機種に展開できるほどコストがこなれているかどうかは別の問題だと思います。
APS-Cサイズのグローバルシャッターを持つ比較的安価なセンサの噂もありました。こちらもセルサイズが小さくなるわけで、裏面照射は必要になるはずです。
本格的に裏面照射センサを導入するのであれば、大きな設備投資が不可欠で、それを回収するためできるだけたくさんのカメラで使用したいはずです。