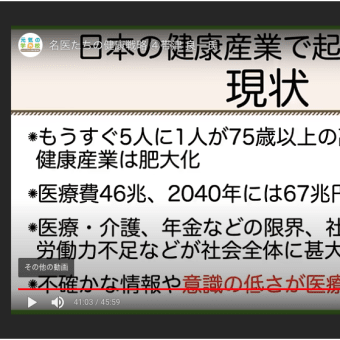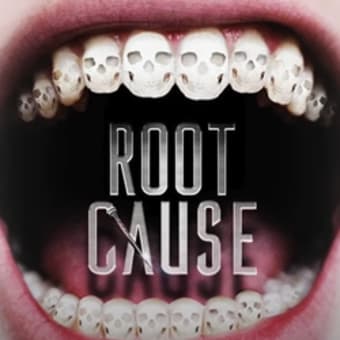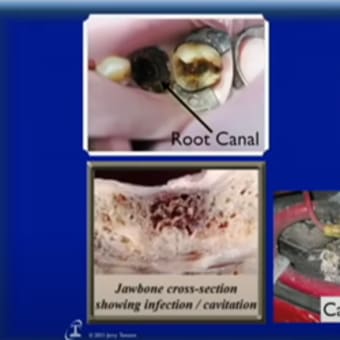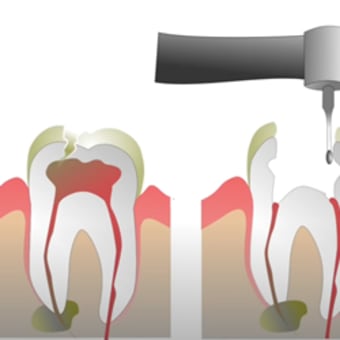こちらの図は先進国でナンバーワンのアメリカが2600カロリーの食生活で、日本がおよそ2000カロリー。ということを示したモノです。さらに摂取カロリーの内訳がおおざっぱに分類されています。
(図解「豊かさの栄養学」丸元淑生:著 参照)
左側の「分離した脂肪」とは、天ぷら油やサラダ油、ラードといったもの。分離してない、とは、肉やナッツなど食品に脂肪が含まれたものです。先進国になるほど肉や加工した植物油、砂糖などでカロリーを摂取していることがわかる。そして、減っているのはナッツ類や穀物(澱粉)、植物性蛋白(豆類など)です。
先進国やそこに仲間入りした日本はいま、肥満や生活習慣病、ストレスなど、それらに関連した病気に冒されています。その原因の多くは肉食や植物油(加工された)の摂取過剰と蛋白質の摂りすぎが根底にあるようです。
肉食をメインにすると、消化時に多くのミネラルやビタミンが消費されるという問題が最近クローズアップされています。肉類は確かに栄養も豊富でエネルギーも高いのですが、いいのはそこまでで、消化する際の負担はというと穀物や豆類の比ではない。逆に摂りすぎて別の栄養素が失われ栄養失調状態になっているのです。
よく肉料理を食べるときは野菜をいっぱい摂りなさい、というのは大事なことなのですが、何か目安があって食事しているわけではないのでバランスが判らない。マクドナルドやピザ専門店、ケンタッキーなどお馴染みのお店で好きなものを食べ、それらに見合った消化に必要なミネラルやビタミンが摂れていると思いますか?
皆さんにお教えできる答えはここでは書ききれませんが、蛋白質は3度3度一定量必要なモノで備蓄はできないといった問題もあるらしい。夕食や夜食にたくさん食べて朝抜きでは、余計に摂ったモノはすぐに排出されて、午前中必要な栄養素は結局確保されないまま過ごすことになるようだ。