347
美術学校の卒業制作展の作品作りをしている。
派手な色合いの布地を大胆にコラージュして、額縁からはみ出した布地はカットするつもりだ。
他の生徒の指導をしている教授に意見を聞いたら、それでよかろうと言われたので自信が湧いた。
348
わが家の息子も小学1年生になる。
今日は初登校の日だ。 真新しい学帽には、まだ徽章が付いてない。
きょう学校でもらうのだろう。
家の前の道路は地下鉄工事で、工事用の大きな立て坑がポッカリ空いている。
その脇を通って行くのだから、どこの親も心配で通学路に立って見守っている。
我輩も立つことにした。
349
大勢の被災者の前で有名人が哀悼のメッセージを述べている。
次に外国の有名なアーティストがギターを抱えて登壇した。
まずギターを少し奏でてからメッセージに入った。
ラ・シ・ド ド・シ・ラ・ファ ド・レ・ミ ミ・ファ・ラ・・・こんな曲だった。
350
草刈正雄似の専務を訪ねて客が来たが、あいにく出かけている。
(客)『ちょっと待たせてもらうよ。昼飯の出前を頼む。おたくの会社にも営業がいた方がいいな』と我輩に言う。
専務が戻ってきたが、向かいの店の主人と話し込んでいる。
(客)『オーイ!昼の出前はまだか?おれは腹ぺこなんだ、金はいくらでも払うぞ』
(我輩)『ハイハイ、ただいま・・』
えーと、電話番号は?
会議室のテーブルの上にいくつか電話番号はメモしてあるが・・あれでもない、これでもない・・・
351
高校時代の隣のクラスの女生徒が我が家に訪ねて来た。一目惚れの子なのだ。
母親の留守中にやってきたので、スリルがある。
彼女がトイレに行っている間に、みかんを二つ皮を剥いて用意した。
そこへ母親が帰ってきた。何でみかんが二つ、皮を剥いてあるのか尋問されそうなので、
あわてて隣の部屋へみかんを隠す。(汗)
352
温泉プールの娯楽施設。 何故かいつも土曜日の終了時間まぎわに行ってしまう。
今日もそうだ 二人の小さな息子たちに手本を見せようとクロールで泳ぎだした。
終了時間が近づいたので、プールの水は抜かれ始めてみるみる減ってゆく。
プールの底が現れるまで泳いだ。 息子たちには刺激になったようだ。
喉が渇いたので食堂に寄って茶器で水を飲もうとしたら、
食堂のおばちゃんが二人現れ、一人が『それは明日のために準備してあるので、飲んじゃダメ』という。
もう一人が『うちの女王様が怒ってます』という。
そこで『うちの女王様、怒らないで』といったら、オホホホ・・・と笑い転げていた。
342
街角の電光掲示板にきょうのテレビの番組表が表示されている。
目で追っていると、見たい番組があった。
ところが電光掲示板の上の方から、テレビ局の女性社員が我輩の目線がどの番組に留まるか観察している。
心を読まれるのがシャクなので、目線を留めないように忙しなく動かした。
傍で小学生の女の子が『熊本は大阪の観光地だよね』という。
『どうして?』と聞いたら、『だって、熊本の方が小さいじゃん』という。
『なんだ、そういうことか』
354
旅の武士の一団が、寒村のお堂の前で休憩している商人の一団と出会った。
『家康どのは、まだ葬儀を済ませてないのでは?』と商人たちに言われ、
家来はあわてて上役のところへ戻り報告。
『愚か者!とっくに済ませておるわ』と叱られ、血相変えてまた商人たちの処へ戻ってきた。
商人たちは、『切られるといけない。赤子は後ろへ隠せ』とあわてている。
355
借りている田んぼは田植えを終えたばかり。
だが泥は深い。 ズブズブと肩まで入ってしまう。
その下は硬い岩盤のようで、ここで足が届く。
母親が珍しがって見に来たので案内する。
356
戦国時代にいる。
戦が一段落して、夜になったので、野宿することになった。
馬の餌になる草が生えてる処を探して、そこで野営だ。
どんな草がいいのか、我輩には分からない。馬が知っているのではないか?
357
(我輩)『いま見てるこの夢って、どういう仕組みで見れるんだろう?』
(夢)『そんなことが、おまえに解るわけないだろう』
358
大きなホテルに団体で一週間泊まることになった。
一人一部屋で、毎日部屋を変わるようにして、
同じ部屋を2回使わないように部屋割表を作れということだ。
どうもややこしい。数学は苦手だ。
359
学生時代のクラスメートと囲碁をやっている。
使うのは碁石ではなく、磁気カードやコインだ。
相手が油断していたので、右辺のカードやコインをあらかた取ってしまった。
どうだ、勝負あっただろうと我輩は得意満面。
だが相手は冷静で、表情ひとつ変えずに盤面をじーっと見ている・・・
えっ? まだ何か手があるの・・?
360
明治時代なのか?東京の下町で祭りの準備をしているらしい。
『支法工』という櫓(やぐら)が組まれている。
その中の山車の中には大きな釜があり、熱湯が入っている。
担ぎ手はこの山車の下をくぐり抜けると無病息災でいられるという信仰がある。
山車は蔵元を一軒一軒廻って、商売繁盛・五穀豊穣を祝うのだそうだ。
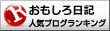
おもしろ日記ランキング

美術学校の卒業制作展の作品作りをしている。
派手な色合いの布地を大胆にコラージュして、額縁からはみ出した布地はカットするつもりだ。
他の生徒の指導をしている教授に意見を聞いたら、それでよかろうと言われたので自信が湧いた。
348
わが家の息子も小学1年生になる。
今日は初登校の日だ。 真新しい学帽には、まだ徽章が付いてない。
きょう学校でもらうのだろう。
家の前の道路は地下鉄工事で、工事用の大きな立て坑がポッカリ空いている。
その脇を通って行くのだから、どこの親も心配で通学路に立って見守っている。
我輩も立つことにした。
349
大勢の被災者の前で有名人が哀悼のメッセージを述べている。
次に外国の有名なアーティストがギターを抱えて登壇した。
まずギターを少し奏でてからメッセージに入った。
ラ・シ・ド ド・シ・ラ・ファ ド・レ・ミ ミ・ファ・ラ・・・こんな曲だった。
350
草刈正雄似の専務を訪ねて客が来たが、あいにく出かけている。
(客)『ちょっと待たせてもらうよ。昼飯の出前を頼む。おたくの会社にも営業がいた方がいいな』と我輩に言う。
専務が戻ってきたが、向かいの店の主人と話し込んでいる。
(客)『オーイ!昼の出前はまだか?おれは腹ぺこなんだ、金はいくらでも払うぞ』
(我輩)『ハイハイ、ただいま・・』
えーと、電話番号は?
会議室のテーブルの上にいくつか電話番号はメモしてあるが・・あれでもない、これでもない・・・
351
高校時代の隣のクラスの女生徒が我が家に訪ねて来た。一目惚れの子なのだ。
母親の留守中にやってきたので、スリルがある。
彼女がトイレに行っている間に、みかんを二つ皮を剥いて用意した。
そこへ母親が帰ってきた。何でみかんが二つ、皮を剥いてあるのか尋問されそうなので、
あわてて隣の部屋へみかんを隠す。(汗)
352
温泉プールの娯楽施設。 何故かいつも土曜日の終了時間まぎわに行ってしまう。
今日もそうだ 二人の小さな息子たちに手本を見せようとクロールで泳ぎだした。
終了時間が近づいたので、プールの水は抜かれ始めてみるみる減ってゆく。
プールの底が現れるまで泳いだ。 息子たちには刺激になったようだ。
喉が渇いたので食堂に寄って茶器で水を飲もうとしたら、
食堂のおばちゃんが二人現れ、一人が『それは明日のために準備してあるので、飲んじゃダメ』という。
もう一人が『うちの女王様が怒ってます』という。
そこで『うちの女王様、怒らないで』といったら、オホホホ・・・と笑い転げていた。
342
街角の電光掲示板にきょうのテレビの番組表が表示されている。
目で追っていると、見たい番組があった。
ところが電光掲示板の上の方から、テレビ局の女性社員が我輩の目線がどの番組に留まるか観察している。
心を読まれるのがシャクなので、目線を留めないように忙しなく動かした。
傍で小学生の女の子が『熊本は大阪の観光地だよね』という。
『どうして?』と聞いたら、『だって、熊本の方が小さいじゃん』という。
『なんだ、そういうことか』
354
旅の武士の一団が、寒村のお堂の前で休憩している商人の一団と出会った。
『家康どのは、まだ葬儀を済ませてないのでは?』と商人たちに言われ、
家来はあわてて上役のところへ戻り報告。
『愚か者!とっくに済ませておるわ』と叱られ、血相変えてまた商人たちの処へ戻ってきた。
商人たちは、『切られるといけない。赤子は後ろへ隠せ』とあわてている。
355
借りている田んぼは田植えを終えたばかり。
だが泥は深い。 ズブズブと肩まで入ってしまう。
その下は硬い岩盤のようで、ここで足が届く。
母親が珍しがって見に来たので案内する。
356
戦国時代にいる。
戦が一段落して、夜になったので、野宿することになった。
馬の餌になる草が生えてる処を探して、そこで野営だ。
どんな草がいいのか、我輩には分からない。馬が知っているのではないか?
357
(我輩)『いま見てるこの夢って、どういう仕組みで見れるんだろう?』
(夢)『そんなことが、おまえに解るわけないだろう』
358
大きなホテルに団体で一週間泊まることになった。
一人一部屋で、毎日部屋を変わるようにして、
同じ部屋を2回使わないように部屋割表を作れということだ。
どうもややこしい。数学は苦手だ。
359
学生時代のクラスメートと囲碁をやっている。
使うのは碁石ではなく、磁気カードやコインだ。
相手が油断していたので、右辺のカードやコインをあらかた取ってしまった。
どうだ、勝負あっただろうと我輩は得意満面。
だが相手は冷静で、表情ひとつ変えずに盤面をじーっと見ている・・・
えっ? まだ何か手があるの・・?
360
明治時代なのか?東京の下町で祭りの準備をしているらしい。
『支法工』という櫓(やぐら)が組まれている。
その中の山車の中には大きな釜があり、熱湯が入っている。
担ぎ手はこの山車の下をくぐり抜けると無病息災でいられるという信仰がある。
山車は蔵元を一軒一軒廻って、商売繁盛・五穀豊穣を祝うのだそうだ。
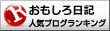
おもしろ日記ランキング




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます