マハサラカームという県があることをご存じの人は、相当タイに詳しいと思います。私自身は、今回のイサーン旅行の直前に知りました。妻がこう言ったのです。「イサーンに行くんだったら、弟のいるマハサラカームにも寄ってみたい。もう長いこと会ってないから・・・」
私が「マハ・・何とかっていう場所はどの辺にあるの?」と訊くと、「私もよくわからないけど、イサーンのどこかにあることは確かなの。」と、何とも外国人のような返事が返ってきました。それに、妻の実家のあるカムペンペット以外に弟がいるなんて初耳でした。ところが、よく聞いてみると弟ではなく「従弟」だったのです。
おそらくタイ人は、「いとこ」という言葉を実際の会話ではあまり使わないのだと思います。辞書で引くと「ルークピー・ルークノーン」となります。妻は従姉妹、従兄弟のことは、「お兄さん」とか「お姉さん」、「弟」とか「妹」と言います。日本人からすると奇異に感じるのですが、おそらく「いとこ」という、性別がはっきりしない言葉をタイ人は口にしないのでしょう。
さて旅行の話の続きをしましょう。
最初はマハサラカームの弟には、コンケーンに着いた日の夜会いに行くことを考えていました。なぜかというと、妻の弟はいつも仕事から帰るのが夜8時ごろで、昼間は会えないからです。ところが、コンケーンから何回電話しても応答がありません。奥さんに電話しても、なしのつぶて。数日前に連絡してあったので、私たちが今晩行くことは認識しているはずなのに・・・。家の場所もよくわからないので、私たちは行くのをあきらめかけました。そうしたら、夜も9時半を過ぎてからホテルにいる妻に、向こうから電話がかかってきました。
でも遅すぎました。事情を話して「またの機会に・・・」と妻が言った瞬間、次の日は金曜日でしたが、弟の仕事が休みだということがわかりました。それならば、ウドンタニに行く前に、朝訪問することにしました。チョーク・ディー(ラッキー)だったのです。

マハサラカーム県はコンケーンの南東に隣接しています。弟の家は地図で青い×をつけたあたりにありました。東のローイエット県との県境にごく近い場所でした。地図では近いように見えますが、コンケーン市内からは100キロほどあります。
3月20日(金)の朝9時ごろ、コンケーンの美しいお寺、ワット・ノンワンを出発し、私たちは黄色い線をつけた208号線を通ってマハサラカームに入りました。

(マハサラカーム市の中心部から300メートルくらいのところ)
マハサラカーム県は人口がおよそ95万人で、お隣のコンケーン県の半分ほど。面積のわりには人口の少ない田舎です。県内のあちこちに分散して存在する「マハサラカーム大学」以外はあまり知られていない、ひっそりと佇む地域です。
午前10時半ごろ、市内を通過したところで妻が弟に電話し、詳しい場所を訪ねました。あと10キロくらい行ったところで、幹線道路までバイクで迎えに行くと言うのです。どうやら田園地帯にあるようです。

弟の家から300メートルくらいのところで撮影しました。牛を放牧していました。ディス・イズ・イサーンなのかどうかわかりませんが、こういう風景は好きです。

こちらは弟の家からわずかに50メートルのところです。家は、この手前の集落にありました。

だいたい30戸か40戸くらいの家が集中していました。左が弟のO(オー)さんの家です。

妻の隣にいるOさん(38歳)は4人家族で、一番左に控えめに写っている奥さんはマハサラカーム県の出身です。Oさん自身は、妻と同じカムペンペット生まれですが、もう10年以上も里帰りしていないそうです。タイ人にしては珍しいことです。何か事情がありそうです。Oさんの隣の男の子は中学3年、後ろの子はまだ4歳です。妻とOさんは、実は20年以上も会っていませんでした。

11時過ぎでしたが、奥さんと娘の2人でバイクに乗って近所から買い出してきたお昼御飯です。

田舎でもこれくらいの料理はいつでも手に入ります。全部で500バーツです。大きい魚2匹が300バーツで、チェンマイよりも少し高めの感じです。イサーンでは、魚は決して安くはないのでしょう。


こちらはラープ・ムー。魚醤とライムで味付けし、唐辛子などを加えた豚肉料理です。タイ(とくにイサーン)では豚を生で食べることもあります。とても危険です。もちろんこれは過熱した挽肉を使っています。

これはご存じソムタム。今回の旅行では、ソムタムを4回食しましたが、どれもさすが本場だけあって、とてもおいしかったです。

この鳥もおいしく、中学生の息子さんは、ひたすらこれとカオニヤオ(もち米)だけを食べていました。

Oさんは、お隣のローイエット県にある、世界的に超有名なスポーツ用品メーカーに勤めています。そこはスポーツ用の衣料品を製造している工場で、イングランドをはじめ、世界の超有名なサッカーチームのユニホームも作っています。工場への立ち入りは厳しく制限されていて、写真撮影はおろか、携帯電話の持ち込みも一切禁止されているそうです。どうりで、前日の夜7時頃電話しても繋がらなかったわけです。肝心の賃金は、そんな有名企業の工場でも、一日たったの300バーツなのだそうです。収入を補うために、普段は奥さんも食品を売り歩いています。
ところで、妻がOさんに会いたがったのには理由がありました。親戚なので、100キロとは言え近くを通れば会うのは自然です。それ以上の理由とは、妻がまだ16歳、Oさんが12歳のときのある出来事でした。2人がまだカムペンペットで暮らしていたころのエピソードです。
そのころ妻の実家は、今もそうですが、大変貧乏でした。ところが父親は大酒飲みで博打好き。おまけに女も好きで、三拍子そろった道楽者でした。(現在67歳で、私より3つだけ年上の父親は、今は当時の見る影もなく、おとなしく暮らしています。)今と違って25年前のタイの田舎で、親がお金に困ったときにやることは大体決まっていました。いろいろありますが、妻の父親が選択したのは、長女(私の妻)を金持ちの男性に無理やり嫁がせることでした。
若い女性をいわば“物色している”見ず知らずの男性のところへ売られるのはとても辛いことでした。当然内心では激しく抵抗しました。でも、父親がろくに仕事をしないので、7歳の時から家族のために労働に従事するような性格の女性が親に逆らうことはなかなかできません。タイでは、(今でも)親の言う通りにしないことは、批難されるべきことなのです。
苦境に陥った妻を力ずくで救ったのが12歳のOさんでした。妻の気持ちを知ったO少年は、躊躇する妻をバイクに乗せ、10数キロ離れたバンコク行きのバスの駅まで走ったのです。正義の味方、月光仮面です。あとでO少年が酷い目に遭うことを心配する妻に、少年はこう言い放ったそうです。「もしヤクザのような人たちを連れてきたとしても、まだ子供だから殺されることはないはずだ。痛い目にあうことは全然平気だ。お姉さん、俺のことは何も心配するな。」
O少年に背中を押され、16歳だった妻はバンコクへひとりで旅立ちました。一度も行ったことのない大都会に叔母さんを訪ね、そこで新しい人生を始めました。その叔母さんは、酷い父親の妹なのです。でも彼女は、逃げてきた妻のことは一切実家に知らせませんでした。妻はバンコクでいろいろな現場労働に従事しました。建築現場で働いたこともあります。おもちゃを作る工場もありました。そして、19歳の時に日本へ渡ったのです。そこには過酷な現実が待ち構えていました。それについては、いつかは書く機会が訪れるでしょうから、ここでは省略です。
さて、Oさんの家を写させてもらいました。

外観は2階があるように見えていましたが、階段は取り払われていて、使っている部屋はひとつだけでした。リビング+寝室というわけです。ダイニングは始めの写真にあったように、もちろん外です。

電気製品は、どれも中古品を長く使っているそうです。質素な暮らしぶりは、悪いことをせずまじめに働いている証拠ではないかと、Oさんの家庭を見ていると思います。

大きなマットレスは、部屋の反対側にも、ひとつありました。この写真を見て妻が気づいたのですが、奥の戸棚にはタイ式の枕が山ほど詰め込まれています。なぜかというと、人にあげるために蓄えてあるのだそうです。私たちは貰いませんでしたけど・・・

タイ式と言うのかどうかわかりませんが、水瓶です。タイの田舎はイサーンでなくても、まだこれを使っているでしょう。何だか懐かしいような気分になるから不思議です。ここに貯めておいて食器洗いや洗濯などに使うのです。イサーンへ行くと、やはり一昔前の日本の暮らしを思い出させてくれますね。
Oさんの家には2時間ほど滞在しました。お昼過ぎにいよいよ今回の旅のメインであるウドンタニを目指して車を再び走らせることにしました。
ブログランキングに参加しています。よろしかったら、お手数ですが引き続きクリックをお願いします。











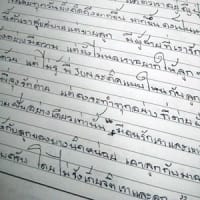














国際結婚の先輩・タイ暮らしされている方なので、参考にして、タイのことを勉強させてもらっています。
私は、マハサラカム県カンタラウィチャイ郡にタイ人の妻とこどもたちと暮らしています。
これからも宜しくお願いします。
マハサラカム県のいとこさんの暮らしは普通ですね。
中のくらしです。
月収が1万あっても、贅沢はできない暮らしです。
電化製品も壊れるまで使いますね。
生活に余裕はありません。でも、イサーン人は笑顔ですよ。日本よりね。
大学があるから経済がなりたっている県でしょうね。
妻の従弟の暮らしているのは、大学の農学部の近くでした。なぜかそこは写真を撮り忘れたのですが、素晴らしい直線道路に面している美しいキャンパスだったのが印象的でした。
イサーンという言葉の響きに何か不思議な魅力がありますね。日本の東北地方が奥深い何かを秘めているのと、ちょっと似ているような気がしないでもないです。
こちらこそ、今後ともよろしくお願いします。