秦郁彦氏の著書『南京事件』(1986年/昭和61年版)への批判は4回目となる。
第一章、第二章への批判について、くり返し述べたが、秦氏の史実探究の手法として、史料批判(テキスト・クリティーク/text critique)」と呼ばれる必要な情報の取捨や評価をする手法を用いているとされているが、実際には前提条件として【南京虐殺】が前提条件にあり、それに叶う史料を取捨評価するという全く公平性も科学的でもない【史料批判】の誤った用法で、この【南京攻略戦】における【報道】と【外国人証言】及び【東京裁判】を分析評価している。
尚、蘆溝橋事件は、1937年7月7日夜、夜間演習中の日本軍に対する支那側からの射撃に端を発する、支那軍の敵対行動による日本軍との紛争のことである。
では、【第三章 蘆溝橋から南京まで】も見ていくことにする。
第三章冒頭、華北の戦闘について米国爆撃調査団の報告の一節から始まる。
引用《P.54 「一九三七年の華北侵略は、大戦争になるという予想なしに行われたものであって、これは本調査団が行った多数の日本将校の訊問によって確証されるところである。当時、国策の遂行に責任のあった者たちは、中国政府がただちに日本の要求に屈して、日本の傀儡の地位にみずからを調整していくであろう信じていた。
中国全土を占領することは必要とも、望ましいとも考えたことはなかった……交渉で、あるいは威嚇であとは万事、片がつくと考えていた」》を引用し次のように結んでいる。《いわゆる拡大派と不拡大派の対立に代表される政策決定の混乱が捨象されていることを除けば、日中戦争の発端、ひいては全体の正確を簡潔、適確に表現した説明だと言えよう。》
つまり、冒頭に於ける【秦氏の見解】は、日本及び日本軍について、【当初から立案され計画的に実行した】作戦行為では無いと言う認識を示され居ることは重要である。
まず最初に蘆溝橋から始まる支那事変に於、重要な条約や協定が存在する。それは、次の7つであろう。
・北京議定書(義和団の乱)調印(1901年9月7日)。(北平での日本軍の駐留権)
・九カ国条約(Nine-Power Treaty)(1922年)締結
ワシントン会議での、米国・英・オランダ・伊・仏・ベルギー・ポルトガル・日本・中華民国間での条約
・ケロッグ=ブリアン条約(不戦条約)を大日本帝国批准(1929年6月27日)
・第一次上海事変停戦協定(1932年5月5日)
・塘沽停戦協定締結(1933年5月31日)(柳条湖事件に始まる満州事変の軍事的衝突は停止)
・梅津・何応欽協定締結(1935年6月10日)(排日抗日運動の停止)
・土肥原・秦徳純(中華民国代表)協定が締結(1935年6月27日)(排日抗日運動の停止)
支那事変については、上の7つの約束事を支那側が逐一全て破ったことによって日本は戦争に巻きこまれていったと言っても過言ではない。本来降りかかった火の粉は払うのは、安全保障としては致し方がないはずである。支那事変は支那側の協定や条約不履行から始まった。九ヶ国条約とケロッグ=ブリアン条約に日本が違反しているとの米国の主張があるが、実際のところ、ソ連は九ヶ国条約とケロッグ=ブリアン条約には、加盟せず日本にとっての最大の脅威が野放し状態であったことと、この二つの条約に於ける【侵略】の定義と、【支那の国境】が明記されていないことなどから、日本にとって極東に於ける非常に不利で危険な条約であったのは確かである。
《いわゆる拡大派と不拡大派の対立に代表される政策決定の混乱が捨象されていることを除けば》とあるが、この混乱は、上海エリアで、支那軍の包囲が始まった後の話であり、そもそも何度も冀察自治政府との停戦の約束が度々為されては、支那軍より破られている。しかも、7月11日に近衛内閣が北支派兵を決定してはいるが、7月12日に蒋介石側は冀察自治政府との【停戦等の約諾】は【不承認】を通告した上、蒋介石直系の中央軍及び地方雑軍各部隊に北支対する集結動員を下令している。確かに、近衛内閣が先で、蒋介石が後ではあるが、7月4日蘆溝橋事件の3日前に国共合作の宣言が行われていて、日本の主敵である共産国家のソビエト連邦という共産主義勢力と手を結んだ段階で日本は大きな【脅威】を北(ソ連)と西(蒋介石政権・共産軍)に持ったことにほかならないと書かねばならないはずである。
《すなわち、「一面抵抗、一面交渉」を標語に日本との衝突を回避しながら、念願の本土統一をほぼ達成した中国は、一九三六年頃から国共合作を軸とする抗日統一戦線を形成し、これ以上の対日譲歩を許さない姿勢に固まりつつあった。》と述べ、それを受けて《しかし、日本政府も軍部も、こうした中国ナショナリズムの新しい潮流を認識せず、武力による威嚇か、悪くても一撃を加えるだけで中国は屈服するだろうと楽観し、マスコミも世論も中国を軽侮しつづけてきた固定観念から、安易に「暴支膺懲」を合唱した。》とお書きになって居られるが、西の脅威【蒋介石・共産軍】となった支那軍の攻撃を黙って受けて、北支から日本人が排除されれば良かったとでも言いたいのであろうか。【暴支膺懲】の蘆溝橋からの一連の動きを見ていると本来の意味は、【防衛】と【脅威】の排除である。《安易》などと考えた秦氏の思考は到底理解できない。
日本軍のその後の行動は、蘆溝橋ある北平近辺に集結した14万にのぼる支那軍と対峙し7月19日頃、支那側の日本軍偵察機への攻撃から、本格的な支那軍との衝突が開始されている。その間にも、戦闘を停止すべく英国の駐支対支ヒューゲッセンが各国と交渉を持ち、そして日本側も南京の蒋介石政権への停戦を求めているにもかかわらず、蒋介石政権は双方同時軍事行動の停止、第3国の調停、冀察自治政府との約諾を認めないという3点をあくまで主張し、日本の要求に応じる様子もなく、同日配備全部隊への抗日指令を出すに至っている。
しかし、7月21日冀察自治政府の宋哲元は、日本との交渉で撤退を誓約をするなど、蒋介石政権との齟齬が見られる混乱ぶりで、その最中7月25日廊坊事件が発生し、冀察自治政府軍に於も統制が取れないない混乱状況である。その為、許される自衛的復仇による攻撃を日本側が開始し、廊坊周辺の支那軍事拠点を占拠するに至る。
これ等のことを鑑みても、【暴支膺懲】が秦氏の言われる【安易】な【懲らしめ】ではなく、【防衛と脅威の排除】を目的としていたものに過ぎないのは明らかである。
さらに、7月27日には、蒋介石政権は「(現地協定について)平和貫徹の徴衷から敢えて反対しなかった」「一切の責任は日本側にあり」という声明を発する始末。支那独特の【殴打して】それを【相手の責任にする】と言う【責任転嫁】の手法である。
それに対し、7月28日には、近衛首相は支那との抗争拡大はアジアの力を弱めるため望まないという談話をだしている。だが、嘲笑うかのように7月29日の未明、通州では冀東保安隊と29軍の敗残兵による残虐非道な【民間人(非戦闘員)】に対する【通州事件】が起こっている。しかし、これに日本軍が激昂して、北支の奥へ戦線が広がっている訳ではなく、7月末迄には北支の北平と冀東、宛平、保定を占領し、日本軍の軍事作戦としては一旦止まっている。7月31日には天津市で治安維持会が立ち上がり。8月4には北平を占拠にて大閲兵式を行っている。
しかし、秦氏は次のように、《七月十一日、近衛内閣は五個師団の華北派遣を声明、七月末、北京、天津地区を占領した日本軍は、増援兵力の到来を待って南下作戦を開始した。八月三十一日には、北支那方面軍(司令官寺内寿一大将)が編成され、指揮下の第一軍と第二軍は中部河北省の省都保定をめざして進撃、別に第五師団は山西省へ向かい、関東軍もチャハル省に出動する。
北支那方面軍の作戦は予定以上の速さで進み、九月二十四日保定を占領、なおも追撃を続行して十月十日石家荘を攻略した。》とまるで、連続した攻撃継続が為されているかのような記述である。これは余りに事実と違うイメージを読者に与えようとするミスリードである。
P.55 最終行《一度サヤを払った軍刀は簡単には収まらないのが軍の論理である。参謀本部が当初指示していた保定まで、という追撃制令線は早くも空文となった。》(8月31日から11月9日 省都太原占領)という記述にしても、8月2日に支那軍29軍が平漢津浦沿線に再集結し、143師も平綏線張家口に侵軍を再度開始している。又、8月4日には陜西共産軍も平津地方の後方攪乱工作に参加、8月8日には中央軍(89師、86師、113師、21師)集結北上し察北へ侵出を開始している。つまり、日本軍から見た場合、【脅威】への対処であるはずが、秦氏のフィルターを通すと【日本軍の行き過ぎた軍事行為】という解釈に代わってしまう。
そして異常な解釈は次へ続く、P.56 16行《追撃戦は味方同士の先陣競争を招きやすい。「○○部隊、一番乗り」という派手な新聞報道も第一線の競争意識を煽った。参謀本部は何度も限界線を指示して、南下競争を押さえようと試みたが、はやり立つ第一線部隊を押さえるのは困難で、結局は既成事実を追認する形となり、作戦区域はいたずらに拡大した。
同様の弊害は華中戦線でも再現し、南京事件を誘発する一因となる。》という記述であるが、そもそも軍の行動が【新聞報道】による競争意識がどれ程影響したかも不明で、【集結】し再度攻撃を仕掛けてくる支那軍に対して、安全を確保するためにはやむを得ないという判断は前線の状態からも明らかであり、日本軍が《はやり立って作戦区域をいたずらに拡大した》訳でもない。
しかも、《南京事件を誘発する一因となる。》という記述がある。第一章、第二章での記述で確定し【南京アトローシティ】は、確実に存在したことになっている。しかしながら第一章、第二章共に、【御自身が用いる史料の客観的な分析法】ではなく、その基準は本来重要な【史料】を捨て、どう考えても【史料価値が薄い】史料を選択するというもので、その様な基準で選んだ史料を根拠に【南京アトローシティ(内虐殺)】があったとしている根拠が無い【異常な】思い込みによる秦氏の【誤認識】に過ぎない。
P.57 2行目《全面戦争へ拡大 華北の戦火は、列国権益の錯綜する華中第一の国際都市である上海に波及せずにはすまなかった。》との記述にしてもそうだが、華北の戦火が上海へと移るにはそれ相応の理由があるはずで、その経緯を記述されていない、7月31日はソ連との密約が結ばれ、蒋介石と汪兆銘は抗日の長期交戦とテロ活動を宣言するに至り、一旦排除した広西省の白崇禧を南京に招聘し、国防会議(四中全会)8月4日に開き善後策を協議している。この後、青島に於も漢口に於いても日本人居留民に対する排日行動が繰り返され、日本人居留民は避難をせざるを得なくなっている。
なぜか【南京】でも8月5日、6日当たりから支那一般人が避難を始めている。蒋介石に信頼が寄せられていなかったのであろうか。
8月8日には、北平で治安維持の日本軍による声明が発表され、治安が回復していることが明らかになっている。この事を受けたのか、中央軍(89師、86師、113師、21師)が、察北へ移動を開始し、上海に於、停戦協定がある地区に保安隊を増員し、正規軍を配置しだした。【上海停戦協定】への違反行為である。つまり、ここでも支那側から【協定破り】が発端であるのである。こうした事実を無視しながら、秦氏の論攷は続けられる。
余談だが、この上海停戦協定(1932年)が結ばれていた最中、上海虹口で、朝鮮人の尹奉吉が爆弾を爆発させて白川義則大将、河端貞次上海日本人居留民団行政委員長が死亡し、野村吉三郎中将、植田謙吉中将、村井倉松総領事、重光葵公使らが重傷を負った上海天長節爆弾事件がおこる。この時この尹奉吉を乗車させて犯行現場に連れて行ったのが、南京安全区のメンバーの一人である【ジョージ・A・フィッチ】で、しかもその他の金九を含むメンバーを一ヵ月に亘り上海の自宅に匿っていた。そういう人物がいたいう重要な情報は、秦氏は記載することはない。かなりの抗日に絡む人物の証言を第一章では、南京での虐殺の目撃者として掲載している。(実際には、目撃していない偽情報ということは、安全委員会の日本当局者に向けた要望や抗議、他国の外務省にあてた陳述を記した『南京安全区当案』やスマイスの手紙やラーベの日記などを、分析された松村俊夫氏の論文で明らかになっている。
話を元に戻すと、7月30日から8月9日迄、日本側の停戦のための努力は続けられ、船津振一郎を起用した和平工作が進められていたが、8月9日に大山が大山勇夫海軍大尉・斉藤一等兵殺害事件がおこり、船津和平工作の会合が流れてしまう。そして8月11日に中央軍3個師団(約三万)が上海を守る日本海軍陸戦隊(四千)に対して攻撃をしかけることで、第二次上海事変が始まる。
日本軍の出兵は、次のような秦氏の指摘があるように《上海に出兵したものの、拡大への不安から兵力を出し惜しみ、苦戦するとそのつど追加投入して、さらに損害を増すという拙劣な対応を重ねた。》は否めない。
これは、日本側があくまで不拡大派(石原完爾ら)を考えを中心に据え、大兵力を用いて一挙に片を付ける作戦を用いなかった証左でもある。大兵力を用いて即決をする考えは、上海派遣軍を率いた松井石根大将の考えでもあるが、それを採用しなかったのは、日本側が不拡大が主流であったことを示している。
しかし、《一方で、戦線を拡大しながら和平工作を進めるが、条件の寛厳で内部対立をひき起こすというぐあいであった。》とは、一体どの和平工作であろうか、船津和平工作はかなり支那側にとって有利な条件で、後のトラウトマン工作にしても、ほぼ同様の条件での停戦条件である。《条件の寛厳で内部対立をひき起こす》とは、日本国の何の組織・派閥間の内部対立をひき起こしたのか記載はない。
因みに、船津和平工作の内容は、(wikiトラウトマン工作参照)
①塘沽停戦協定、梅津・何応欽協定、土肥原・秦徳純協定の解消。
②廬溝橋付近の非武装地帯の設定。
③冀察・冀東両政府の解消と国府の任意行政。
④増派日本軍の引揚げ。
国交調整案としては以下の条件
①満州国の事実上の承認。
②日中防共協定の締結。
③排日の停止。
④特殊貿易・自由飛行の停止。
である、
トラウトマン和平工作の内容は、(wikiトラウトマン工作参照)
①外蒙と同じ国際的地位を持つ内蒙自治政府の樹立。
②華北に、満州国境より天津、北京にわたる非武装地帯を設定、中国警察隊が治安維持。ただちに和平が成立するときは華北の全行政権は南京政府に委ねられるが、日本としては長官には親日的人物を希望する。もし直ちに和平が成立しない場合は新しい行政機関を設ける必要がある。この新機関は平和が結ばれた後にもその機能を継続する(ただし今日までのところ日本側には華北新政権を設立する意向はない。)。
③上海に非武装地帯を拡大し、国際警察により管理する。
④排日政策の停止。
⑤中ソ不可侵条約と矛盾しない形での共同防共。
⑥日本製品に対する関税引き下げ。
⑦中国における外国人の権利の尊重。
である。
これに対し、秦氏は《当初は比較的寛大な条件を提示し》と、比較的という比喩を使って過小評価をしている。数々の条約や協定を破り日本国に対し攻撃を加えつづけた支那側に対する日本側の譲歩案とも言える条件に対するこの過小評価は異常な評価としか言えない。
そして続く文章で《最終態度を決めかねているうちに、日本軍は首都南京を攻め落としてしまう。》とあるが、10月27日には上海での最後の支那側防衛地点の大場鎮、江湾鎮が陥落し、蒋介石が目的とした上海からの日本軍の排斥に失敗し、ドイツから送りこまれたドイツ人軍事顧問団の指示の元造り上げた近代的な軍隊の大半を失った訳であり、完全な支那側の敗戦である。その様な状態の中、11月5日トラウトマンを介して和平条件は蒋介石側に伝えられているが、その内容を知っているのは蒋介石と孔祥煕のみで、その段階で蒋介石からの返答は、ディルクセン駐日ドイツ大使を通じて日本に対して次の実質拒否の返答している。(wikiトラウトマン工作参照)
①北支:北支の主権領土及行政の完整を確保し得れは経済開発、及資源の供給に関し相当の譲歩をなす。各国駐兵権を全部放棄せしむれは最も可なるも、然らされは日本の駐兵は義和団条約規定の地域とし、兵カは列国との振合に応し別に条約を以て定む。
②上海:
(a)8月13日以前の原状に復す
(b)上海停戦協定所定の地域内に於て、武装団体防御施設禁止に関するか如き事項は国際協定を以て規定す。日本及列国の上海に於ける駐兵及軍事施設は租界守備区誠に必要なる最小限度に減し、其兵かは現共同委員会又は別の委員会に於て研究決定す、右有効期限を当分5年とす。
(c)前項区域は略現停戦協定区域とし之を著しく拡張するは不可なり。
蒋介石はの判断は現状を直視出来ずにいるのは明らかで、11月3日からのブリュッセル会議(九ヶ国条約加盟国)に対し、制裁決議が為されるかどうかに期待するという、劣勢を挽回するために列強の縋ろうとする愚かな判断したと言うことである。《国際連盟、九ヶ国条約加盟国による対日制裁が見こみ薄となり、米、英、ドイツなどの利害関係国も「同情はしても傍観するだけ」》という状態が理解されると、ようやく各閣僚等に各国の思惑も去りながら、支那側の行為(共同租界やその他港湾での外国権益施設や船舶に対する爆撃などもあり)を無視して日本国のみ違反とは出来なかったはずである。
そもそも秦氏もお書きになっているが、《「重火器、戦車、トラック、通信機材、弾薬はきわめて劣弱で、海軍、空軍は問題にならないほどの格差」あった。》中で、日本軍との直接対決をするというのは、軍事関係者としては全くの無能者のすることで、日本の太平洋戦争の様に逃げ道のない状態と違い、わざわざ全面戦闘に及んだことは支那国民の生命財産を顧みないあきれ果てる行為と言わざるを得無い。
しかしながら、《国際連盟、九ヶ国条約加盟国による対日制裁が見こみ薄となり…中略…傍観するだけ」》を受けて次に続くのが、《中国駐在のトラウトマン独大使を仲介者とする和平工作が生まれた。日本側は「渡りに舟」と飛びつき》この認識は何であろうか意味不明である。11月21日には無錫が陥落し、敗戦濃厚の情勢では、本来《「渡りに舟」と飛びつき》となるのは支那側の筈である。事実慌てたように11月28日に政府・軍主要メンバーを招集しトラウトマン工作の条件を示し協議をしている。その中では秦氏の言う《比較的》ではなく【好条件】と受け止められ受け入れ意見が大勢を占め蒋介石も受け入れを受諾し、12月2日にトラウトマン大使に受け入れを伝達するが、蒋介石自身の面子と反日の意識(「日本に対してはあえて信用できない。日本は条約を平気で違約し、話もあてにならない」)が強すぎて更に条件wik引用《「華北の行政主権は、どこまでも維持されねばならぬ。この範囲においてならば、これら条件を談判の基礎とすることができる。」ただし「日本が戦勝国の態度を以て臨み、この条件を最後通牒としてはならない」》を付け留保を続け、【最良の条件】で日本と和平交渉できるタイミングを逸してしまったのは蒋介石である。本来ならば、こういった無能のそしりを受けるべきであろう。そのような人物をその国の指導者に据えた悲劇というべきである。
しかし、秦氏の認識は中身を飛ばして先に飛び、《蒋政権との間で戦争を収拾しようと焦慮して、かずかずの和平工作を試みたが、いずれも成功せず、日中戦争は八年にわたる長期戦へ移行した。》と結論づけている。【汪兆銘政権を日本の傀儡政権で民心が得られなかった】とする根拠は何処にあったのであろうか。1月23日の汪兆銘のブレーンであった高宗武と陶希聖が【日華新関係調整要綱】を新聞紙で暴露した上の香港逃亡したことや、西義顕、金雄白等離反のことを指しているのかも知れないが、これらの人物と、日本側の影佐禎昭、今井武夫(桐工作という蒋介石との和平工作の中心人物)、西園寺公一(外交官、ソ連スパイ、支那共産党員)などの回想録を中心に史料を扱った事は容易に推測できる。それは支那における有力者達の離反等のことで、【民心=一般支那民衆の心情】とは又違ったと考え無ければならないはずである。
何故なら、南京では順調に人口が戻り、南京戦4年後、汪兆銘政権発足(1940年)の翌年1941年(昭和16年)3月末の統計には619,406人、在留邦人11,791人となっている。そして、秦氏の著書の参考史料・文献には、日本軍が代理統治していた3年間と汪兆銘政権での支那人の生活などについて書かれた史料は見られない。南京攻略戦後からの3年間とその後終戦までを、支那人民に対して【日本の傀儡政権=悪政】と勝手に想像した【異常な】記述である。
ヘッダ・モリソン(Hedda Morrison)というドイツ人写真家が1933年〜1944年中国に滞在し、1940年代からの南京のポートレイトや風景を撮しているが、そこには穏やかな風景や人々の暮らししか写っていない。
秦氏のおかしな見解は未だ未だある、P.61 3行目 上海派遣軍の出征での《上海に出兵したものの、拡大への不安から兵力を出し惜しみ、苦戦するとそのつど追加投入して、さらに損害を増すという拙劣な対応を重ねた。》と批判して松井大将が大兵力を用いるのが結果正しいにもかかわらず、《松井は当初から戦場を上海に局限するのは無理で、もう少し大兵力を投じて》という松井大将の言を《南京まで行くべきだという松井の信念は変わらないどころか、執念にまで高まったようだ。》の野心のように記述をし、松井大将に個人的恨みがあるかのような【異常】な思い込みを披露している。
《外征軍の司令官が、出発の前から与えられた基本任務の変更を迫るのは異様というほかはなく、のちに起きた松井軍の軍紀崩壊の遠因は、ここに発したと見ることもできよう。》と記述されているが、《軍紀崩壊の遠因》とあるが、実際に軍紀が崩壊していれば、勝てる戦いも勝てるはずもないのが事実だが、後に続く《P.63 第十軍の杭州湾上陸》以後の第十軍の独断専行を以て《軍紀崩壊》との理由にされているが、実際の軍紀崩壊の具体的な実情は何も記述がない。
11月26日に大場鎮が陥落し、第十軍杭州湾北岸の上陸作戦は、11月5日に決行され、同時に第16師団も揚子江白茆口からも上陸作戦を敢行している。11月7日には上海を確実に確保したことは両部隊とも知り得ているはずである。秦氏は《十月二十日、第十軍司令官に与えられた任務も、「上海派遣軍の任務達成を容易ならしむ」と示されていた。》と書かれているが、『南京戦史』(偕行社)P.533の【作戦命令の部】下段の10月20日の臨参命第百三十八号では、《二、中支那方面軍司令官ノ任務ハ海軍ト協力シテ敵ノ折セシメ戦局終結ノ動機ヲ獲得スル目的ヲ以テ上海附掃滅スルニ在リ》とあり、その上部組織への命令の目的が《戦局終結ノ動機ヲ獲得スル目的》という文言を含んでいることから、大場鎮等上海の主要支那陣地が陥落した以上は、《「上海派遣軍の任務達成を容易ならしむ」》は、古い命令となっていることは明らかである。更に11月7日に中支那方面軍が編成されの中方作命第一号の中支那方面軍命令においても《三、第十軍ハ主力ヲ以テ松江附近ニ進出シテ上海派遣軍ノ蘇州河南方地区ニ於ケル作戦ニ協力スルト共ニ崑山方面ニ対スル爾後ノ攻撃ヲ準備スヘシ》となっており、第十軍もその通りに動いている。
秦氏の記述では、《P.75 1行目 十一月十五日、第十軍司令部は軍司令官も臨席して幕僚会議を開き、「軍全力ヲ以テ独断南京追撃ヲ敢行スル」ことを決した。》となっているが、11月15日頃は、長江の福山・常熟・蘇州・平望・嘉興・乍浦鎮を結ぶ南北の大きな支那の第2防衛ラインに一部の隊が達しただけで主力部隊は達していない。
そして、さらに秦氏の記述では《第十軍が独断で南京へ向かって追撃に移ったのを参謀部が知ったのは、十一月十九日であった。》とあるが、11月19日頃はようやく蘇州を押さえ第2防衛ラインを破ったばかりである。15日このような決定をして19日に南京へ向かう次の主要拠点の【無錫】占領は21日である。確かに11月20日松井集団参謀長宛に《丁集団ヨリ湖州ヲ経テ南京ニ向ヒ全力ヲ以テスル追撃ヲ部署セル旨報告シ来レル処右ハ臨命第六〇〇号(作戦地区ノ件)指示ノ範囲ヲ脱逸スルモノト認メラルルニ付為に》とあるので、追撃を敢行したことは確かでようではある。
しかし、松井石根大将の日記には、これについて何等記載無く。参謀の飯沼守少将日記にも《10A(第十軍)ハ南京ニ向ヒ各兵団ニ追撃ヲ命ス昨夜ノ位置、18D南潯鎮、国崎支隊其西方、114嘉興、6D松江》とあるのみで、中支那方面軍では驚いたり慌てたりしている節はない。未だ、蒋介石政権との和平進捗しない状態に置いて、臨参命第百三十八号《戦局終結ノ動機ヲ獲得スル目的》から判断しても、自然な戦闘の流れに成ると考えられる。
当初の松井石根大将の構想から考えても、和平が為されていない状態では、解決を求めるため南京を目指すのは自明であり、11月22日には、日本国中央へ南京攻略への具申書を出していることから、何等《軍紀崩壊》でも《第十軍を押さえる立場にある方面軍が、たちまち同調して軍中央部を突きあげた》や《上海派遣軍をひきいる立場から第十軍とのライバル意識を刺激されたのかも知れない》を証明するものは何もない。本来なら流れ上【南京へ向かうこと】は当然の成り行きとすべきであるにもかかわらず、秦氏の考察と見解は非常におかしなものである。
それが事実、11月25日に無錫、11月28日に宜興を抜かれたことにようやく蒋介石はトラウトマン工作の条件を政府・軍首脳に回覧させている。日本軍の南京への進軍はある意味効果があったと評価すべきである。しかしながら、この後も和平に応じることはなかったのは蒋介石の【立場の保身】や【面子】の問題と考えられる。
もう一つ、この章に於ける異常な見解は、日本軍が出した損害から、《P.66 3行目 それでも何とか上海の堅陣を破れたのは、日本軍が戦車、飛行機、軍艦など中国に乏しい近代兵器をつぎこんで、地上火力の不足を補ったせいであった。》と書いているにもかかわらず、《この戦訓は十分に検討されることなく、ノモンハン、太平洋戦争で、日本軍はますます肉弾万能へ傾斜して行く。》という部分であろうか。資源の少ない日本が、人材を損耗する【肉弾戦】奨励するはずもなく、資源力の大きなアメリカとの戦争による損耗と資源が足りず無理な戦闘法を取らざるを得なかったことを【肉弾戦への傾斜】とするのは、余程【日本人を馬鹿にした】記述であろう。
又、《上海の惨烈な体験が、生き残りの兵士たちの間に強烈な復讐感情を植えつけ、…中略…のちに南京アトローシティを誘発する一因となったことは否定できない。》という見解もおかしく、南京攻略戦の主要部隊は、第十軍と第16師団で、上海戦で損耗の激しい上海派遣軍は、後続援助部隊に回っている。又【南京アトローシティの一因】と書かれているが、第一章、第二章の段階で根拠が存在のないことを示していることは、もう既に示したが、【結果】が存在しないのに【一因】とするのは【あり得ない】ことである。
秦氏は、捕虜の違法殺害が、【南京虐殺】というものの大きなウェイトを占めていると考えられておられるようで、《上海戦とひきつづく追撃戦段階における日本軍の非行は、具体的資料が乏しく今後の検討課題に属すが、目に触れた範囲での情報を拾っておく。》と書いた上で、P.68の上海戦の捕虜処分について記述されている。
その前に、戦後日本は正規兵を持たず、法的にもよく知られていない。【正規兵】の法的要件を理解しなければならないはずである。前原光雄著『国際法講義 下』金文堂書店 昭和15年刊のP.68 3行目の第一款 戦闘員の章に、正規兵について述べられている。
《一 正規軍 正規軍とは國家によって任命された指揮者の下に立つ組織せられた軍隊で、外見的に認識し得る徽章(一般に制服)を有するものである。
軍隊が如何に組織せられるかは各國の國内法によって定まるので、國際法の関與するところではない。正規軍は通常国家の兵力の主要な部分を構成するのであって、これが戦闘員であるということは云ふまでもない。》
この事を、理解していないと俘虜(捕虜)の処刑が全て【違法】となってしまうので説明する必要があったはずである。
しかし、秦氏は法学部出身であるあるにもかかわらず、【正規兵】というものを説明していない。非常に誠に不親切でミスリードを誘うため敢えてしていないと受け取られても仕方がないであろう。
P.68《第三師団の歩兵第三十四連隊で、大場鎮の戦闘での「鹵獲表」に、俘虜一二二名とかかげ、「俘虜の大部分は師団に送致せるも、一部は戦場に於処分せり」(歩兵第三十四連隊「自昭和一二年十月十六日至昭和一二年十月二十七日大場鎮附近戦闘詳報」)》と《第十三師団の歩兵第百十六連隊の戦闘詳報で、「俘虜准士官下士官二九」として、「俘虜は全部戦闘中なるを以て之を射殺せり」(歩兵第百十六連隊「自昭和一二年十月二十一日至昭和一二年十一月一日劉家行西方地区に於ける戦闘詳報」)とある。》
まず、文章を読む限り、【俘虜】=【捕虜】と考えられているが、実は【便衣】となった【正規兵】とくに分けた記載が無いため【俘虜】とは、それらの【捕虜】の扱いを受ける【権利】をゆうする【正規兵】とは限らないことが一点、それは《一部は戦場に於処分せり》で、すべての【俘虜】を処刑したのではなく、何等かの不記載の理由から一部の兵士のみ処刑したと言う事が判ることと、【戦闘】継続中においては、【捕虜】となりえず【殺害】もやむを得ない。国際法学者の信夫淳平氏は、【助命は部隊全員乞降の場合のみ】という見解を示している。つまりこの第13師団116連隊の【俘虜射殺】には【違法性】が無いと言うことである。
秦氏は、東京大学【法学部】の御出身者であるにもかかわらず、どうも法的根拠からこの2件を分析することなく、更には、これを正当化するために、曽根一夫『私記南京虐殺』と言う人物の回想録を引用している。《占領した敵陣地のトーチカ内に敵兵が三人潜んでいた。》この段階で、戦闘中であれば、《処刑》も已む得ない《違法行為》ではない。
実際の所、回想録やオーラルヒストリーは、事後の政治的主張や記憶違い、忘却が入りこむ余地があり、出来る限り南京事件についてそれらを排するのが無難と考えるが、秦氏のテキストクリティークの重要度からも下位に準じてあるはずが、実際は事象の確定への根拠に暗に使っている。こういったやり方は、秦氏の特徴で、自身の奨める検証手法とは矛盾するものである。
《戦闘詳報は後世に残る公文書であり、作成に当たっては都合の悪い部分は適当に加除して体裁を整えるのが慣行になっていた。》と記述し、戦闘詳報が公文書ではあるが、正確性を記するものでは無いと書きつつ、《その戦闘詳報に国際法違反の行為を堂々と記載したのは、すでに捕虜殺害は当然という気分が全軍に行きわたっていたことを物語る。》と結論づけておられるが、現実には前述の第3師団34連隊および第13師団116連隊の記述のように、【国際法】に反するものでなく、【俘虜】はその兵士の状態、つまり【正装】か【便衣】かに関わらず、【俘虜】若しくは【捕虜】と記述され、その投降や鹵獲の時期の状態も不明であることから、その処刑及び殺害が【国際法】に違反したかどうか迄は判然としないにもかかわらず、《国際法違反の行為》との決めつけのは、秦氏の見識は本当に日本軍とその兵卒に対して【悪意に満ちている】と言わざるを得無い。
P.69からは、朝日新聞の本多勝一氏と南京攻略戦から30年も経った、国民党との内乱や文化大革命の最中に取材された『中国の旅』での内容を用いて、日本軍の上海からの行程での不法行為を挙げている。『中国の旅』の支那の証言者にはおきまりのフレーズがあり、【毛主席への感謝の言葉】と【『日本軍国主義を、日本の人民と力をあわせて、どうしても阻止無ければなりません。」】というあきらかに支那のプロパガンダの文言が入っている。つまり本多勝一氏が行ったのは、支那共産党の抗日プロパガンダを日本で広めたに過ぎず、正確な史料でも何でもないのは明白にもかかわらず、秦郁彦氏はそれを無視して、日本軍の【不法行為】の根拠の材料にしている。
又、松本重治氏の引用をされているが、これも又非常におかしく。《柳川第十軍の進撃が早いのは、「将兵のあいだに『掠奪・強姦勝手放題』という暗黙の諒解があるからだ」(『上海時代』下)との風聞が現地記者の間に流れていた、と書いているが、この風聞は根拠の無いものではなかった。》と引用して独り納得されているが、全く失笑を禁じ得ない。例えば、小学校へ通うA君とB君が居て、A君はまっすぐ学校へ行き、B君は途中の文具屋で良いものは何か無いかと探してから学校へ行った。歩く速度は同じとする。さてどちらが先に着いたであろうか。答えはA君であろう。
動機という側面からの、記述のつもりであろうが、仮に日本軍が掠奪した食品以外の物資を抱えて、前に前進したりしている状況はどうであろうか。補給部隊もままならないと記述しているわりに、掠奪した物資を後送している史料が見つかっているとでも云うのであろうか。
松本重治氏にしても秦氏にしても、小学生の低学年でも判るような論理的な思考が出来ないのは、理解に苦しむ。松本重治氏については、自らその著書でオールドリベラルを標榜し、西園寺公一氏など極めて共産系に近い人物だが、それに秦氏は注釈も入れず、テキストクリティークもせずに其儘引用しているのは、異常というより他はない。
P.69 12行目 【山川草木すべて敵なり】と銘打った記述では、平松鷹史氏『郷土部隊奮戦史』、従軍カメラマンの河野公輝氏の回想、宮下手記『徒桜』を用いて、第十軍の【不法行為】への指示又は容認をしていたと記述されているが、実際には《第十軍の命令綴にはこの種の資料は欠けている》と御自身でも記述しているし、更に余程都合が悪かったのか他の文字より小さな文字にして《*杭州湾上陸前に交付された第十軍の「軍参謀長注意事項」(池谷資料)には、軍紀の厳守、不必要な家屋の焼却の禁止、弾薬の節約、生水飲用の禁止などと並んで、「七、支那住民に対する注意」という項目があり、住民には老人、女、子供といえど危険なことがあるから注意せよ、と戒め、斯の如き行為を認めし場合に於ては些も仮借することなく断乎たる処置を執るべし」としている。誤解を招きやすい表現であり、末端に伝達されるときには、宮下証言のような趣旨で伝わった可能性がある。》と記述されているが、これを読むと【抗日運動】があり、【支那人民間人と雖も信用できない】状態があったことを示す史料にかかわらず、全く逆の【第十軍】不法行為容認の《誤解を招きやすい表現》として自己主張の云い訳に使っている。
この第三章の結論として、秦氏は日本軍の【蘆溝橋から上海、南京戦】の日本軍の不法行為の一因を【軍紀崩壊】とされているが、実際には【根拠の薄い】回想録などを用いて、日本軍の全体の動きを異常な動きの様に見せているだけであり、実際には【軍紀崩壊】などもなく日本軍の軍事行動はそのまま続き南京へ追撃戦で移行したというのが事実である。そこには秦氏の言うところの【南京アトロシティー】の【一因】も存在しない。











![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3e/bf/4e958b0df4dae2efaae311bc7490fe2e.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/3e/ee4f6f211c5fcfde5f98514db31e6345.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/db/dbf0c4de83642bebaa9db2fe1ec7791f.png)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/aa/4b6f78386db8398965d5ab7d3cf8c31d.jpg)
![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/8f/275e903ac5a3597f90f2780b38ec6818.png)
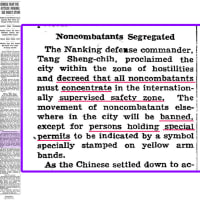

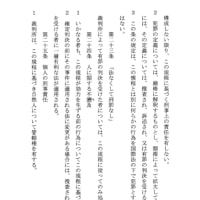

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます