僕はわが日本が高度経済成長期と言われた時代に、北九州の片田舎で少年期を過ごしました。
駄菓子屋のお菓子の値段が毎年変わっていくの実感しつつも、まだ古き良き日本の姿を留めていた時代であったと思っています。
自然環境は豊かで、田んぼや用水路には様々な生き物があふれておりました。
今では絶滅危惧種のメダカなど、ちょっと水があるところであればいくらでも居ました。
このような環境で育ったので、川で釣りをしたり魚捕りをしたりするのは、ごく普通の遊びでした。
釣りはからっきしダメなほうですが、魚はときどき捕ってきてバケツで飼い、すぐに死なすという事を繰り返しました。
もっとも、子供の頃は魚より昆虫のほうが好きだった気がします。
虫捕り子供に気を付けろ・・・とカブトムシに恐れられたかは解りませんが、大人の目線で見ると子供って残酷な生き物ですね。(笑)
わが一家が神奈川県に引っ越した事もあり、虫捕りも魚捕りも自然に卒業しました。
それから幾たびかの年月を経て、突然変異的に淡水のハゼに興味を持つ事になります。(子供に返ったか?)
少年時代の経験と記憶を頼りに、すぐに川で魚捕りをして自宅の水槽で飼育するようになります。
もっとも、最初のターゲットはハゼでは無くエビでしたが、もうひとつの偶然によりヨシノボリを飼うようになりました。
川での魚捕りと自宅の水槽での飼育というのが、当初的な川のハゼとの関りでした。
採集した魚を観察ケースに入れて撮影する事や、水槽の魚を撮影した画像をアップされたりしているのをネットで知ります。
防水タイプのデジカメが世に出るようになると、カメラ好きの血が騒ぎ川用に調達しまます。
当初は、うっかり水ポチャしても大丈夫という余裕的な考えで、水中撮影をする考えはありませんでした。
沖縄の川へ行くようになり、思いつきで水中写真を撮ってみたのが、水中写真を始める最初のきっかけになりました。
ボケボケの酷いデキでしたが、ほんのお遊びでちょっとだけやってみただけの事なので気にもしませんでした。
本格的に、採集から撮影にシフトしたのは、撮影限定で川へ行く機会を得てからです。
そして、ある人との出会いによりデジタル一眼の導入に踏み切りました。
カメラは高校生の頃から好きでしたが、お金もかかりますし発展途上期にあったデジタル一眼を長い事「越えない一線」としていたのです。
水中写真を始めてからは内地の川へ行く機会も少なくなり、もっぱら沖縄方面での淡水ハゼの水中撮影が活動の中心となっています。
撮影は防水仕様のカメラでの水中撮影がほとんどですが、同定や水中撮影が困難な場合は観察ケースで撮影する事もあります。
このため、水中撮影時でも最低限の採集道具は用意してあります。
前述のように、魚捕りから淡水魚と関わりが始まった者なので、採集そのものを否定するつもりはありません。
親しい方からお誘いいただければ、都合がつく限りご一緒いたします。
種を問わず、採集はその場所におけるその種の資源量に配慮して行うべきだと思っています。
例外はあるかもしれませんが、淡水魚の生息環境が厳しい昨今、採集圧による深刻な影響は避けねばなりません。
淡水魚は、基本的に生息環境さえ健全であれば爆発的に数を増やすポテンシャルを持っているので、資源量に問題さえ無ければ節度をわきまえた個人レベルの採集に大きな問題は無いと思います。(その道のプロの採集は根本的にレベルが異なります。)
水槽での飼育は現在でも続けていて、魚を水槽で飼育する事を否定するつもりはありません。
ただ、アクアリストとして、飼育した魚は最後まで自分で責任を持って面倒を見るべきだと思っています。
ハゼはキチンと面倒を見れば、かなり長生きする魚ですし、そもそも縄張りを持ち闘争をする魚でもあります。
いち個人が相当に頑張った所で、無限に水槽を増やす続ける事はできないでしょうから、個人で飼育できる個体数には自ずと限りがあると思います。
魚を持ち帰る際には、個人宅の設備で無理なく飼育できる個体数にしておくが相当と考えます。
<はじめに>に戻る
<ポリシーについて>に続く
<index>
駄菓子屋のお菓子の値段が毎年変わっていくの実感しつつも、まだ古き良き日本の姿を留めていた時代であったと思っています。
自然環境は豊かで、田んぼや用水路には様々な生き物があふれておりました。
今では絶滅危惧種のメダカなど、ちょっと水があるところであればいくらでも居ました。
このような環境で育ったので、川で釣りをしたり魚捕りをしたりするのは、ごく普通の遊びでした。
釣りはからっきしダメなほうですが、魚はときどき捕ってきてバケツで飼い、すぐに死なすという事を繰り返しました。
もっとも、子供の頃は魚より昆虫のほうが好きだった気がします。
虫捕り子供に気を付けろ・・・とカブトムシに恐れられたかは解りませんが、大人の目線で見ると子供って残酷な生き物ですね。(笑)
わが一家が神奈川県に引っ越した事もあり、虫捕りも魚捕りも自然に卒業しました。
それから幾たびかの年月を経て、突然変異的に淡水のハゼに興味を持つ事になります。(子供に返ったか?)
少年時代の経験と記憶を頼りに、すぐに川で魚捕りをして自宅の水槽で飼育するようになります。
もっとも、最初のターゲットはハゼでは無くエビでしたが、もうひとつの偶然によりヨシノボリを飼うようになりました。
川での魚捕りと自宅の水槽での飼育というのが、当初的な川のハゼとの関りでした。
採集した魚を観察ケースに入れて撮影する事や、水槽の魚を撮影した画像をアップされたりしているのをネットで知ります。
防水タイプのデジカメが世に出るようになると、カメラ好きの血が騒ぎ川用に調達しまます。
当初は、うっかり水ポチャしても大丈夫という余裕的な考えで、水中撮影をする考えはありませんでした。
沖縄の川へ行くようになり、思いつきで水中写真を撮ってみたのが、水中写真を始める最初のきっかけになりました。
ボケボケの酷いデキでしたが、ほんのお遊びでちょっとだけやってみただけの事なので気にもしませんでした。
本格的に、採集から撮影にシフトしたのは、撮影限定で川へ行く機会を得てからです。
そして、ある人との出会いによりデジタル一眼の導入に踏み切りました。
カメラは高校生の頃から好きでしたが、お金もかかりますし発展途上期にあったデジタル一眼を長い事「越えない一線」としていたのです。
水中写真を始めてからは内地の川へ行く機会も少なくなり、もっぱら沖縄方面での淡水ハゼの水中撮影が活動の中心となっています。
撮影は防水仕様のカメラでの水中撮影がほとんどですが、同定や水中撮影が困難な場合は観察ケースで撮影する事もあります。
このため、水中撮影時でも最低限の採集道具は用意してあります。
前述のように、魚捕りから淡水魚と関わりが始まった者なので、採集そのものを否定するつもりはありません。
親しい方からお誘いいただければ、都合がつく限りご一緒いたします。
種を問わず、採集はその場所におけるその種の資源量に配慮して行うべきだと思っています。
例外はあるかもしれませんが、淡水魚の生息環境が厳しい昨今、採集圧による深刻な影響は避けねばなりません。
淡水魚は、基本的に生息環境さえ健全であれば爆発的に数を増やすポテンシャルを持っているので、資源量に問題さえ無ければ節度をわきまえた個人レベルの採集に大きな問題は無いと思います。(その道のプロの採集は根本的にレベルが異なります。)
水槽での飼育は現在でも続けていて、魚を水槽で飼育する事を否定するつもりはありません。
ただ、アクアリストとして、飼育した魚は最後まで自分で責任を持って面倒を見るべきだと思っています。
ハゼはキチンと面倒を見れば、かなり長生きする魚ですし、そもそも縄張りを持ち闘争をする魚でもあります。
いち個人が相当に頑張った所で、無限に水槽を増やす続ける事はできないでしょうから、個人で飼育できる個体数には自ずと限りがあると思います。
魚を持ち帰る際には、個人宅の設備で無理なく飼育できる個体数にしておくが相当と考えます。
<はじめに>に戻る
<ポリシーについて>に続く
<index>



















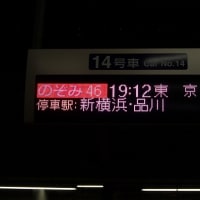
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます