消費税軽減税率について与党税制協議会から公表された3つの案を解説した記事。
筆者が最も可能性が高いと考えている「生鮮食料品」を対象とする案を例にとって、おかしな点を指摘しています。
「与党協の資料を見ると、生鮮食料品の定義は食品表示法(消費者庁所管)の規定に従うとの記述がある。これは、税法独自で生鮮食料品を定義すると、事業者に二重管理が生じるなど混乱の元になるという理由である。」
「・・・単品では生鮮食料品でも、組み合わせるとそうではなくなる。これが食品表示法の定義である。単身者や高齢者にとって利便性の高いカット野菜の盛り合わせも標準税率ということでは、世の中の理解も得にくいと思われる。」
「第2点目は、食料品の「組み合わせ商品」の値付けの問題である。
・・・
与党協の資料では、「サーモンの刺身」と「いくらのしょうゆ漬け」をギフトセットとして別個に包装して販売する場合には、「サーモンの刺身」は生鮮食料品として軽減税率の対象となる。しかし別個に包装しない場合には、全体が標準税率となる。「カット野菜」と「ドレッシング」も、別々の商品で販売すれば「カット野菜」は軽減税率になるとの事例が掲載されている。
また「商品が不可分でない場合」には、軽減対象とそうでない商品のそれぞれの時価で案分して課税計算をすることになる。
フルーツの盛り合わせ(不可分でない場合)を考えてみよう。お歳暮やお中元には、メロンとジュースが(別個に)セットとなっている商品が出回る。メロンは生鮮だがジュースは生鮮ではないので標準税率となる。業者は、両方の原価比率を計算して値段・税率を決めなければならない。」
欧州の例が紹介されています。
「たとえば、セット商品について英国で聞いた話では、クリスマスシーズンにバスケットの中にチョコレートやワインなど税率の異なる商品を入れて販売する場合、事前に税務当局と相談して、商品の比率に応じた税率を「個別に合意する」そうだ。わが国でもそうなることが予想される。
もう1つ、容器の方が中身より高価な商品の取り扱いは厄介だ。銀食器(標準税率)に入って販売されるマスタード(軽減税率)の税率がドイツで裁判になった例がある。」
所得階層別の負担軽減額については・・・
「低所得者というと、第1分位の世帯(低い方から2割)であろう。生鮮食料品軽減税率によって受ける利益は年間2325円、一方第5分位(上位2割)は4938円と、軽減税率は高所得者優遇であることは明確に表れている。数千円のために、わが国経済には多大の手間がかかる。」
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
〈衝撃の経営危機〉脱毛サロン「ミュゼプラチナム」の全取締役が解任。給与は連続で遅配、SNSでは「ふざけんなよ!」(文春オンラインより)
農林中金の奥理事長が辞任へ、外債投資による多額損失で-関係者(ブルームバーグより)
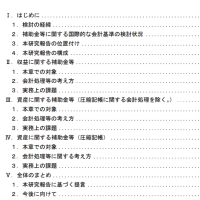
「補助金等の会計処理及び開示に関する研究報告」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
コロナ補助金で急拡大! 都心超一等地ビルに移転したコンサル会社の「計算違い」(現代ビジネスより)
株主代表訴訟に関するお知らせ(前代表取締役に対し損害賠償を請求する株主代表訴訟を提起)(電気興業)

「受託業務に係る内部統制の保証報告書の発行状況に関する研究文書」の公表について(日本公認会計士協会)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事
