
スーちゃんのくいしんぼうは止まらない。無類の料理好きで、なによりも「おいしい」と笑顔で喜んでもらえることが本人の生きがいだった。「わたし、お釈迦様の日に生まれたからね」と本人ひとりで納得していた。
我が家では、毎年、大みそかの日に、治療室が配膳室へと変身した。お重が30個から40個並び、台所から運ばれる数々のお料理を娘が盛り付けていく。スーちゃん、とても手際よく、また、ほめ上手だったようで、娘もついついよく働いたという。
スーちゃんは、年末にマコちゃんから10万円のお小遣いをもらっていた。1960年代の10万円は、そこそこの価値である。その全額が、ものの見事に食材に化ける。小豆、利尻昆布、どんこしいたけ、日本酒、お好みの小豆島の醤油など。
これら上質な素材を使い、スーちゃんがひいた御出汁でつくる大きなだし巻き卵や、かしわやレンコンがバランスよく入った筑前煮、そして、銘柄指定のかまぼこやら手作りポテトサラダのハム巻きなどなど。色どりもにぎやかなおせち料理が山のように出来上がる。20軒分は軽くあったように思う。毎年、21時にはできあがり、それからご近所さんに配達をする。1軒10円の配達賃をもらっていた記憶がある。身寄りのない人やいつもお世話になっているお隣さん、ご近所さん、一人暮らしのご老人、小一時間かけて娘二人で配達をした。
スーちゃんは、頼まれてやっていたわけではない。ただただ、好きでやっていたのだ。なにぶん数が多いため、材料費は、10万円でも足りないらしかった。そのたびに、マコちゃんから「節約、節約。御ケチ料理をつくればいい」と言われていた。娘の目には、豪華に見えていたが、食いしん坊としてはもっともっと使いたい素材があり、作りたい献立があったのだろう。
娘が家を離れてからも、規模を縮小して続いていたから、少なくとも30年間は、毎年、近所に配っていた。
後に、マコちゃんが逝き、一人暮らしを始めたスーちゃんのもとには、毎日どこからともなく手作り料理が集まってきた。誰かが持ってきてくれて、時に複数のお皿が届くこともあった。
善意は、巡る。
かつてスーちゃんのおせち料理になんらかのかたちで触れた人が持ってきてくれていたのだろうか。そう、信じたいものだと、いつも、ほほえましくこたつの上にあるお皿を見ていた。スーちゃんは「あんまり、おいしくないんよね」とつぶやいていたが、幸せな光景であった。















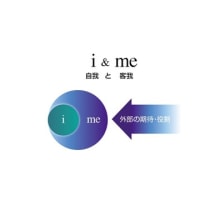



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます