7割の人が「憮然=腹立て」と誤用、文化庁の国語世論調査(読売新聞) - goo ニュース
俺自身もカン違いしてたなあ。
それを承知して自覚した前提で書いてみる。
「煮詰まる」は、その表現自体、「煮詰まってるんだから結果が出る」ような印象はない。
「煮詰まって」る状態で“結果が出る結果”が出るわけがない、と思ってしまう。
結果が出るまでに大変だったという表現だろうけど、とても最終的に結果が出るような明るいイメージがない表現だ。
だからそう誤解が生まれるのもわからんでもない。
「檄を飛ばす」は、漢字を「激」として「激しく励ます」みたいな印象で定着してしまってるのもあると思う。
でも、それでもテレビなどで「監督は選手たちに檄を飛ばしました」って聞くと、とても監督が自分の考えを選手に伝えて“同意を求めてる”ようには受け取れない。
監督は選手に同意を求めるもんでもないだろうし。
やっぱりガツンと怒ったり「しっかりせんかっ!」って励ましてるような、そんなイメージがある。
「憮然とした」というのもそう。
なんかこう、ふてくされてるような印象があるコトバだと思ってた。
「怒られて憮然とした態度で」、っていう表現も聞くし。
そういうのを聞いた時に「失望」とか「ぼんやり」というイメージはない。
ふくれっ面でふてくされてるようなイメージが強い。
「足元をすくわれる」も、そう。
「さわり」もそう。
こういう誤解というか間違ったままイメージが定着してしまうのは、テレビとかメディアのせいなのかな?
ま、間違ったイメージがついてる自分たちがいけないんだろうけど、こんだけ多くの割合の人が自然とそういうイメージを持ってるのも事実。
さらに、暴論を承知で言うと、それなら、多数決の原理で、もうそういう意味にしちゃえば?、とも思う。
どうせこれからもそういう表現は誤解されたまま次の世代に伝わっていくんだろうし、メディアでもこういうかんじで使われて大多数の人が自然と耳に入ってそういうイメージが定着していく。
10数%の“正解者”がその正解を知ってても逆に周りは「?」ってなるかもしれないし。
「情けは人の為ならず」ってのも、「人に情けをかけると人の為にならない(だから、あまり人になんでもかんでも情けをかけてやさしくするのもよくない)」という意味にとられがちだけど、ホントの意味は・・・?


















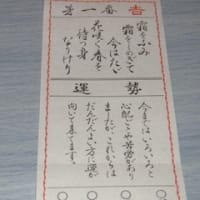

あ、なるほど、「できあがりが近い」っていう「煮詰まり」なんですねー。
そして、確かに「行きづまる」と混同してるなあ。
大事にしたい部分もあるし、それが本筋なんすけどね、どうもゆがんだまま自然と身についてしまうと、こういうクセを直すのが大変になってしまいます~。
「煮詰まった」ということは出来上がりが近いと感じ易いようにも思えます
行きづまると混ざっているんだろうけれど
「詰める」っていえば最後や詳細をきちんと片付けるという意味もあるし。。。
言葉の意味はどうしてもぶれてくるものだとは思いますが
古い読み物が読みにくくなるだけでも損失になるし
できるだけ変化を少なくしようと努力してもいいと私は思います