あなたも遺産相続トラブルに巻き込まれる(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
「相続」の業務は、行政書士も扱う人がいるし、司法書士が不動産登記と絡めてやってることもある。
俺は相続はやってないし、要領もわかんない。わかんないんでたいてい職場の別の事務員の人に振ってるけど、戸籍を読むことから民法にのっとった基本的なことまで、実務ではそれが興味深いと思える。
・・・でも、見ててそう思うだけで、なんかややこしそうで俺は自分からやろうとまではしてないけど(!)。
亡くなった人の戸籍を読んでいくと、出生から亡くなるまでの経緯がわかる。
他に子供がいないか、そういうことをさかのぼってチェックしないといけない。
たとえば、男性Aさんが亡くなったとする。
Aさんには奥さんBと、子供がC、Dとふたりいる。
それだけならAさんの財産は、原則として奥さんに半分、子供Cに4分の1、Dに4分の1、で渡る。
ところが、もしAさんが生前、別のとこで子供を作ってたら・・・その別のとこの子Eにも相続権が発生する。となると、奥さんBや子C、Dがもらう財産が変わる。
そういうこともあるので、Aさんが生まれてからの戸籍の動きを追わないといけない。
俺もそういう理屈はわかるんだけど、そこまで戸籍を読んで、俗に言う“戸籍を追いかける”ってのがややこしそうで、そこまでひとりでやったことない。
また別のケースで、たとえば、男性Aさんが亡くなったが、Aさんはこれまで結婚しておらず、奥さんも子供もいない。Aさんの両親はすでになくなっており、兄弟B、C、Dの3人がいる・・。
そんな場合、まずAさんにホントにこれまで奥さんも子供もいないかAさんの戸籍を出生までさかのぼる。それでAさんに結婚歴がない、子供がいないと確認する。
すでに両親(祖父母も)が亡くなってるので、Aさんの相続人はAさんの兄弟B、C、Dになる。
で、次に、兄弟B、C、D以外にAさんの兄弟がいないか見ていく。
つまり、Aさんの両親の出生まで戸籍をさかのぼって、他に兄弟(ハラ違い、タネ違いの兄弟)がいないかを見る。もしそこでAさんやその兄弟が知らない別の兄弟がいたら、その会ったこともないような人も一応相続人となる。
そういうことも、ちゃんと戸籍で確認しないといけない。
相続の基本的な業務って、そういうことらしい。
・・いろんな経歴の人がいるけど、その親の戸籍までさかのぼって見たり、戸籍を変えてきた人については日本各地に戸籍を請求したりもする。
それで古い戸籍を取り寄せると明治より前の、江戸時代の元号の生まれの人がいたりもする。それはそれで妙に感心したり「へえ」って思ったりもする。もちろんすでに亡くなってる人だけど、寛永だか文禄だか生まれとかの記録があることがすごいと思えてしまう(素人丸出しだけど)。
相続の話を周りの人や顧客にすると、あまり知らない人は「いやあ、ウチにはそんな財産はないから」と言う人もいる。
俺もかつてそうだった。
でも、実際はあとになって、亡くなってから何年もたってから相続の手続きとか故人名義の不動産の手続きをすることがある。
財産のある、なし、ではなく、相続税がかかる、かからないの規模にかかわらず、亡くなった人がなにかしら持ってるものがあれば、不動産でも貯金でもそれを亡くなったあとどうするのか、そういう手続きが必要になる。
司法書士や行政書士は、そういう遺産を相続人でどう分けるか、分割協議書なるものも作ったりもする。
俺は作ったことないけど、読んでて特別難しいものではなさそう。
この建物は誰にあげる、この貯金は誰にあげる、っていろいろ書いてる。さらに細かいことを書いてたりもしてるけど、それで相続人が実印で印鑑押してその内容で故人の財産を分割、相続していく。
遺言書も、俺は今の仕事の関係で遺言の“証人”になったこともある。
詳細は割愛するけど、亡くなろうとする人(余命があまりない人)について、病院まで行って遺言をもらう手続きをするのはつらかったり重かったりする。
でも、手続きとしては、ちゃんと亡くなったあとに問題が起きないように本人の意思をちゃんと汲み取って確認して書面に反映させないといけないので、つらくても仕事はまっとうしないといけない。
人は必ず亡くなる。
司法書士や行政書士はそういう書類を作ったり手続きをする業務がある。
社労士なら、亡くなった人の遺族給付があったりもするだろう。
サムライには、人が亡くなった時に携わる仕事がある。


















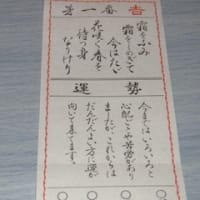

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます